
冬は、汗をかく機会があまりなく水分を失っている自覚も少ないため、飲料摂取量が少なくなってしまう傾向にあります。空気の乾燥により体の水分も失われやすく、脱水を引き起こす可能性が高い季節といえます。また、ノロウイルスやインフルエンザなど、感染症にかかりやすい季節でもあるため、下痢や嘔吐で脱水症に陥ってしまう人も珍しくありません。今回は、そんな冬場の水分補給をより効果的にする、「電解質」についてご紹介します。
◆電解質とは?
電解質とは、水に溶けると電気を通す性質をもった物質のことです。人間の体の水分(体液)には、もともと電解質が含まれています。水中では電解質は電気を帯びたイオンになり、体内の水分量やpHを一定に保ったり、神経細胞や筋肉細胞の働きにかかわったりしています。
電解質はそれぞれバランスを取りながら、生命の維持に重要な役割を果たしています。そのため、バランスが崩れてしまうと腎機能やホルモンの働きが低下し、命にかかわることもあるのです。
◆おもな電解質とその役割
おもな電解質は、ナトリウム・クロール・カリウム・マグネシウム・カルシウムの5つです。これらは、5大栄養素のうちのミネラルに属します。こちらでは、それぞれの働きや性質をご紹介します。
 ・ナトリウム (Na)
・ナトリウム (Na)
ナトリウムは、体の水分や浸透圧を調節する働きを持っています。神経伝達や筋肉の収縮にも深いかかわりをもつ成分です。
 ・クロール(Cl)
・クロール(Cl)
大部分のクロールはナトリウムとともに存在しており、体の水分量や浸透圧の調節などを行っています。胃酸の分泌や酸塩基平衡の維持にもかかわる成分です。
 ・カリウム(K)
・カリウム(K)
神経伝達や筋肉の収縮、心臓の収縮にかかわります。カリウムが低くなると神経麻痺や摂食障害、高くなると不整脈や腎不全などが起こる可能性が高く、生命維持に大きな役割を果たしている重要な成分です。
 ・マグネシウム(Mg)
・マグネシウム(Mg)
マグネシウムは神経や筋肉を正常に機能させ、骨や歯を作る働きをもちます。また、体内にある酵素も、マグネシウムがなければ正常に機能しません。カルシウムやカリウムの代謝にもかかわる成分です。
 ・カルシウム(Ca)
・カルシウム(Ca)
カルシウムは、骨や歯を作ったり、血液を凝固させたりする働きをしています。体内のカルシウムの99%は、骨や歯などに蓄えられており、血中のカルシウム濃度が低下すると、骨から血液中に移動して濃度を保っています。
◆より効果的に水分補給するためのポイント
 普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。
普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。
電解質を失った状態で水を飲んだ場合は、一時的に体液が増え、体液における電解質の濃度が下がります。すると体は、電解質の濃度を一定に保とうとして、過剰な水分を尿として排出してしまうのです。結果として体液量が回復できず、水分補給ができていない状態を「自発的脱水」と呼びます。このような場合、電解質を含む飲料で水分補給すれば、体液を薄めずに水分補給ができます。水分とともに電解質を失った場合は、経口補水液やイオン飲料で水分補給することが大切です。
脱水症の予防には、塩分濃度が0.1~0.2%のスポーツドリンクなどが有効です。脱水症が発生した場合は、スポーツドリンクに比べナトリウム量が多く水分吸収速度の速い経口補水液が適しています。
より効果的に水分補給するために、意識しておきたい電解質についてご紹介しました。電解質は、生命を維持するためになくてはならない存在です。感染症にかかりやすく脱水症を起こしやすい冬は、電解質を含む経口補水液やイオン飲料を常備してみてはいかがでしょうか。



 春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。
春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。 最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。
最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。
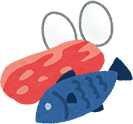 食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。
食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。 ・つけない
・つけない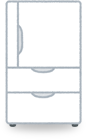 ・増やさない
・増やさない
 夏バテになると、主にだるさ・疲労感・食欲不振などの症状がみられます。これらは夏バテの症状の代表例です。体がだるいと感じる日が続いたり、休んでも疲れが取れにくかったりしたら、夏バテによる不調を疑ってみましょう。また、食欲がわかず食事を摂れないと、栄養不足につながるおそれがあります。消化器の調子もよくご確認ください。
夏バテになると、主にだるさ・疲労感・食欲不振などの症状がみられます。これらは夏バテの症状の代表例です。体がだるいと感じる日が続いたり、休んでも疲れが取れにくかったりしたら、夏バテによる不調を疑ってみましょう。また、食欲がわかず食事を摂れないと、栄養不足につながるおそれがあります。消化器の調子もよくご確認ください。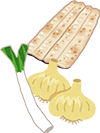 ・疲労回復につながる栄養を摂る
・疲労回復につながる栄養を摂る 暑さで眠れないときや、眠りが浅いときは、意識して普段よりも眠りやすい状態を整えましょう。就寝前30~60分に入浴し、ぬるめの温度の浴槽に浸かります。どうしても暑さが気になるときは、入眠時に氷枕や冷房を活用しても良いでしょう。十分な睡眠で疲労を回復して、疲れを残さない習慣をつくれると理想です。
暑さで眠れないときや、眠りが浅いときは、意識して普段よりも眠りやすい状態を整えましょう。就寝前30~60分に入浴し、ぬるめの温度の浴槽に浸かります。どうしても暑さが気になるときは、入眠時に氷枕や冷房を活用しても良いでしょう。十分な睡眠で疲労を回復して、疲れを残さない習慣をつくれると理想です。
 腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。
腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。 食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。
食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。

 秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
 料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。
料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。 食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
 保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。
保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。 健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
 緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。
緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。 緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。
緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。
 チーズを発酵させるためには青カビや白カビ、鰹節を発酵させるにはカツオブシカビが必要です。また、醤油や味噌を発酵させるために使われる麹菌もカビの一種です。
チーズを発酵させるためには青カビや白カビ、鰹節を発酵させるにはカツオブシカビが必要です。また、醤油や味噌を発酵させるために使われる麹菌もカビの一種です。 乳酸菌には、便秘や肌荒れを引き起こす悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きがあります。免疫力を向上させたい場合におすすめです。ヨーグルト・チーズ・納豆・漬物に含まれています。
乳酸菌には、便秘や肌荒れを引き起こす悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きがあります。免疫力を向上させたい場合におすすめです。ヨーグルト・チーズ・納豆・漬物に含まれています。