
紫外線は、一般的に夏の季節にもっとも強くなります。春から夏にかけて、少しずつ紫外線対策を意識し始めましょう。今回は、紫外線と健康の関係についてお伝えします。つい勘違いしがちな部分もあるからこそ、改めて日焼けの基礎知識を確認してみてください。
◆紫外線の浴びすぎは健康に悪いの?
私たちが目で見ることはできませんが、太陽光には「紫外線」が含まれています。紫外線は、体内でビタミンDを作るために必要な要素です。ビタミンDには、腸でのカルシウムの吸収を2~5倍にする働きがあります。不足するとカルシウム不足に陥るおそれがあり、大切な栄養素といえるでしょう。きのこや一部の魚類にも含まれていますが、食品のみで必要な量を確保するのは難しいと考えられています。ところが、紫外線の浴びすぎは健康への影響が懸念されているため、やや注意が必要です。
◆日焼けの基礎知識
紫外線を浴びると、私たちの体は日焼けをします。日焼けには、紫外線を浴びた数時間後に肌が赤くなる「サンバーン」と、数日後に肌が黒くなる「サンタン」という種類があります。サンバーンが2~3日程度で消えるのに対して、サンタンが消えるまでには数週間から数カ月といった長い期間がかかることも珍しくありません。
このようにサンタンによって肌が黒くなるのは、体が紫外線の被害を防ごうとする防衛反応です。よく「サンタンが紫外線を防ぐ」と誤解されることもあるようですが、実際に紫外線を防ぐ効果はとても小さく、SPF4程度だといわれます。なお、一般的な日常生活レベルで使われる日焼け止めは、SPF10~35です。
日本で紫外線がもっとも強くなるのは6~8月ですが、紫外線の強さや量は地域によって異なります。また、紫外線量は環境によって大きく異なり、日陰の紫外線量は日向の50%、光が反射しやすい新雪の上では紫外線量が100%+80%となります。紫外線をよく反射する雪や砂のある環境では、日焼けをしやすくなることに注意しましょう。
◆紫外線が健康に与える影響
 紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。
紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。
◆紫外線の浴びすぎを避けるポイント
 皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。
皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。
また、屋外の紫外線を避けるのが難しいときは、肌に塗る日焼け止めを活用する方法もあります。市販の日焼け止めは、利用シーンに応じたSPF・PAの数値から選ぶと良いでしょう。特に、レジャーやスポーツのように、長時間にわたり紫外線の強い場所で過ごすときは、数値が高くかつ耐水などの効果も併せて確認してみてください。
紫外線は体内でビタミンDを作るために必要な一方で、浴びすぎは皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。肌のシワやシミといった、美容の観点でのデメリットも少なくありません。紫外線の浴びすぎを避けるために、ご紹介したポイントをぜひ参考にしてみてください。


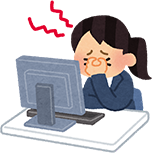
 仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整え
仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整え ・作業中はこまめに休憩を取る
・作業中はこまめに休憩を取る ・画面の明るさや色味を調節する
・画面の明るさや色味を調節する
 温かい湯船に全身が浸かると、体が温まって血管が広がり、血行が良くなります。血液には、私たちの体のすみずみまで酸素や栄養を運び、そして二酸化炭素や老廃物を排出する役割があります。血行が良くなると、筋肉の凝りがほぐれ、疲れが取れやすくなるのがメリットです。ほかにも、体を温めることは内臓や自律神経にも良いといわれます。シャワーを浴びる場合と比べて、全身をしっかりと温められるのが大きな違いです。
温かい湯船に全身が浸かると、体が温まって血管が広がり、血行が良くなります。血液には、私たちの体のすみずみまで酸素や栄養を運び、そして二酸化炭素や老廃物を排出する役割があります。血行が良くなると、筋肉の凝りがほぐれ、疲れが取れやすくなるのがメリットです。ほかにも、体を温めることは内臓や自律神経にも良いといわれます。シャワーを浴びる場合と比べて、全身をしっかりと温められるのが大きな違いです。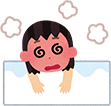 このように多くのメリットが期待できる入浴ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。最後に、湯船に浸かるうえで気をつけておきたいことを解説します。
このように多くのメリットが期待できる入浴ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。最後に、湯船に浸かるうえで気をつけておきたいことを解説します。
 春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。
春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。 最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。
最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。



 ・運動不足
・運動不足 また、仕事とプライベートの切り替えは、意識的に行ってください。自宅のなかで仕事をするスペースを決めて、休憩時間や就業後にはその場を離れる方法もあります。就業時間外には、仕事で使うPCや端末を片付けても良いでしょう。オフィスで勤務する場合と同じように、就業時間や休憩時間を守り、こまめな休憩を取ってください。
また、仕事とプライベートの切り替えは、意識的に行ってください。自宅のなかで仕事をするスペースを決めて、休憩時間や就業後にはその場を離れる方法もあります。就業時間外には、仕事で使うPCや端末を片付けても良いでしょう。オフィスで勤務する場合と同じように、就業時間や休憩時間を守り、こまめな休憩を取ってください。 さらには、社内のコミュニケーションを充実させることも大切です。チャットやビデオ通話は業務連絡での利用に限定せず、雑談も交えながら気軽に交流できる機会を増やします。同僚や部下の様子がおかしいと思われたら、必要に応じて声がけを行ってください。プライベートでも、親しい方とコミュニケーションを取る機会を設けましょう。
さらには、社内のコミュニケーションを充実させることも大切です。チャットやビデオ通話は業務連絡での利用に限定せず、雑談も交えながら気軽に交流できる機会を増やします。同僚や部下の様子がおかしいと思われたら、必要に応じて声がけを行ってください。プライベートでも、親しい方とコミュニケーションを取る機会を設けましょう。




 風邪の原因はウイルスや細菌による感染です。ウイルスや細菌は、私たちの手に付着し、そこから目や鼻などの粘膜を通して感染します。また、咳やくしゃみなどの飛沫に含まれるウイルスや細菌が、のどを通して感染する可能性もあります。手やのどに付いたウイルスや細菌を洗い流すためには、手洗いとうがいが有効です。日常生活では手洗いとうがいを実施し、ウイルスや細菌が体に侵入するのを防ぎましょう。
風邪の原因はウイルスや細菌による感染です。ウイルスや細菌は、私たちの手に付着し、そこから目や鼻などの粘膜を通して感染します。また、咳やくしゃみなどの飛沫に含まれるウイルスや細菌が、のどを通して感染する可能性もあります。手やのどに付いたウイルスや細菌を洗い流すためには、手洗いとうがいが有効です。日常生活では手洗いとうがいを実施し、ウイルスや細菌が体に侵入するのを防ぎましょう。 私たちの体にある粘膜には、体の外からのウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割があります。粘膜のはたらきを保つには、体内に十分な量の水分が必要です。ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、排出しやすくするために、こまめな水分補給を行いましょう。また、空気が感染すると粘膜も乾燥しやすくなります。風邪予防に適した湿度は60~80%といわれます。乾燥しやすい秋~冬は、加湿器を使用してお部屋の湿度を高めに保ちましょう。
私たちの体にある粘膜には、体の外からのウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割があります。粘膜のはたらきを保つには、体内に十分な量の水分が必要です。ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、排出しやすくするために、こまめな水分補給を行いましょう。また、空気が感染すると粘膜も乾燥しやすくなります。風邪予防に適した湿度は60~80%といわれます。乾燥しやすい秋~冬は、加湿器を使用してお部屋の湿度を高めに保ちましょう。 栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動といった規則正しい生活は、風邪予防の基本といえます。特に、疲労がたまると風邪をひきやすくなります。風邪が流行る時期には、普段から体力を保つよう心がけてください。また、風邪予防では体を温めることも大切です。ウイルスや細菌は、低温低湿の環境を好みます。衣服や暖房により保温を行い、体から熱が奪われすぎないよう調整しましょう。
栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動といった規則正しい生活は、風邪予防の基本といえます。特に、疲労がたまると風邪をひきやすくなります。風邪が流行る時期には、普段から体力を保つよう心がけてください。また、風邪予防では体を温めることも大切です。ウイルスや細菌は、低温低湿の環境を好みます。衣服や暖房により保温を行い、体から熱が奪われすぎないよう調整しましょう。
 熱中症が引き起こされる仕組みをお伝えしました。それでは、熱中症を防ぐにはどんなポイントに気をつければよいのでしょうか? まず、大切なのはこまめな水分補給と、適度な塩分補給を行うことです。気温の高い屋外にいるときは、のどが渇いたと感じなくても、水分を摂るよう心がけてください。汗をたくさんかいたら、適量の塩分を摂ります。
熱中症が引き起こされる仕組みをお伝えしました。それでは、熱中症を防ぐにはどんなポイントに気をつければよいのでしょうか? まず、大切なのはこまめな水分補給と、適度な塩分補給を行うことです。気温の高い屋外にいるときは、のどが渇いたと感じなくても、水分を摂るよう心がけてください。汗をたくさんかいたら、適量の塩分を摂ります。
 熱中症を防ぐためには、外出時に日差しを防いだり、体を冷やしたりするグッズを使う方法もあります。日差しを防ぐグッズとして挙げられるのは、帽子や日傘などです。帽子や日傘には、頭や体が直射日光に当たるのを防ぎます。直射日光を避けるだけでも温度に差が出るため、ぜひご活用ください。また、体を冷やすグッズとして、保冷剤や冷却スカーフなどが挙げられます。太い血管が通る首筋を冷やすと、全身を効率よく冷やすことにつながるため、身につけて暑さの対策を行いましょう。
熱中症を防ぐためには、外出時に日差しを防いだり、体を冷やしたりするグッズを使う方法もあります。日差しを防ぐグッズとして挙げられるのは、帽子や日傘などです。帽子や日傘には、頭や体が直射日光に当たるのを防ぎます。直射日光を避けるだけでも温度に差が出るため、ぜひご活用ください。また、体を冷やすグッズとして、保冷剤や冷却スカーフなどが挙げられます。太い血管が通る首筋を冷やすと、全身を効率よく冷やすことにつながるため、身につけて暑さの対策を行いましょう。
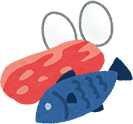 食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。
食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。 ・つけない
・つけない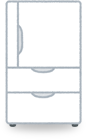 ・増やさない
・増やさない