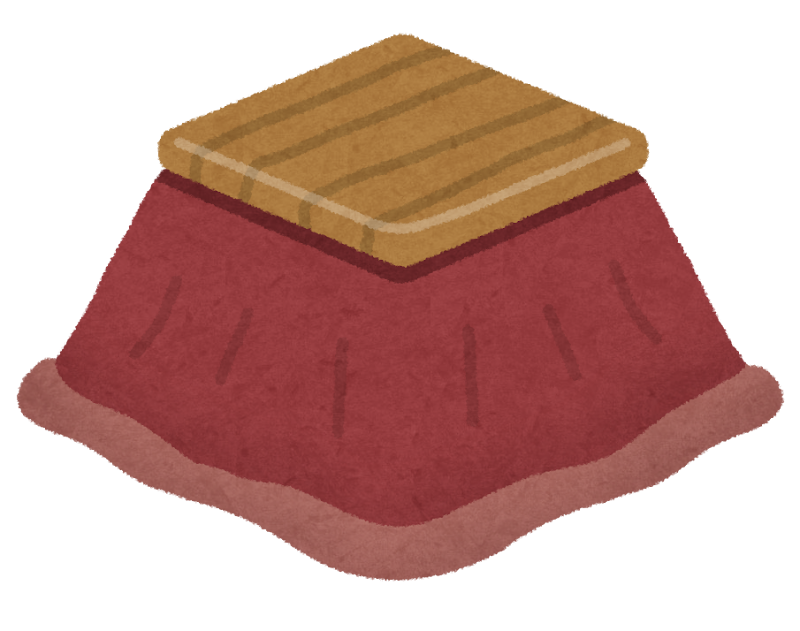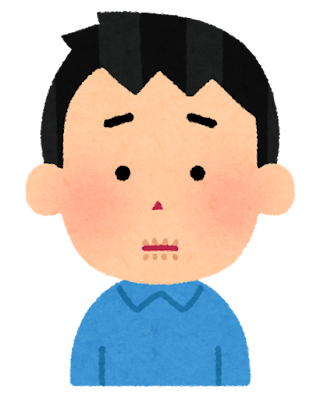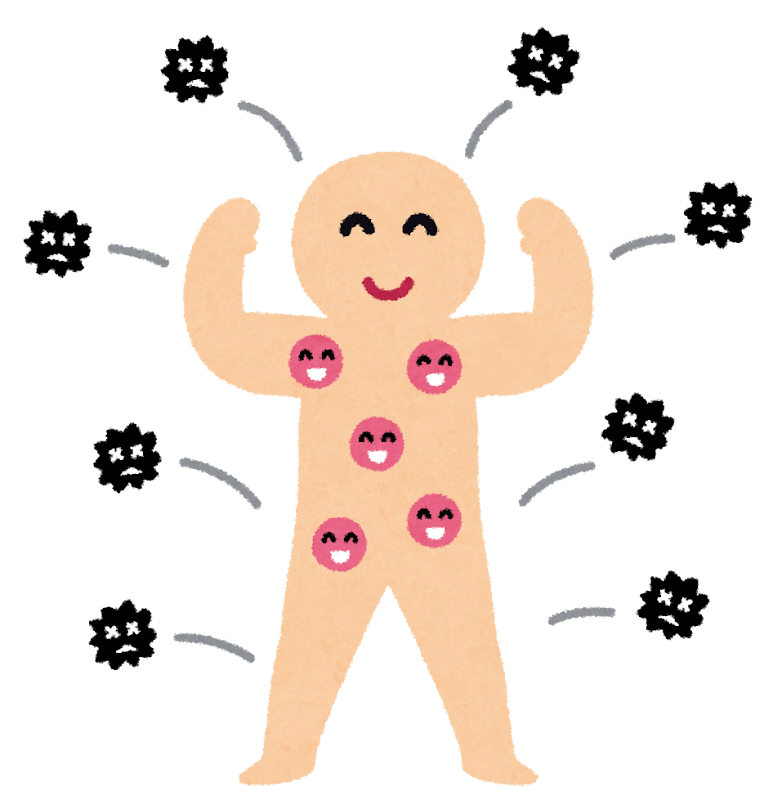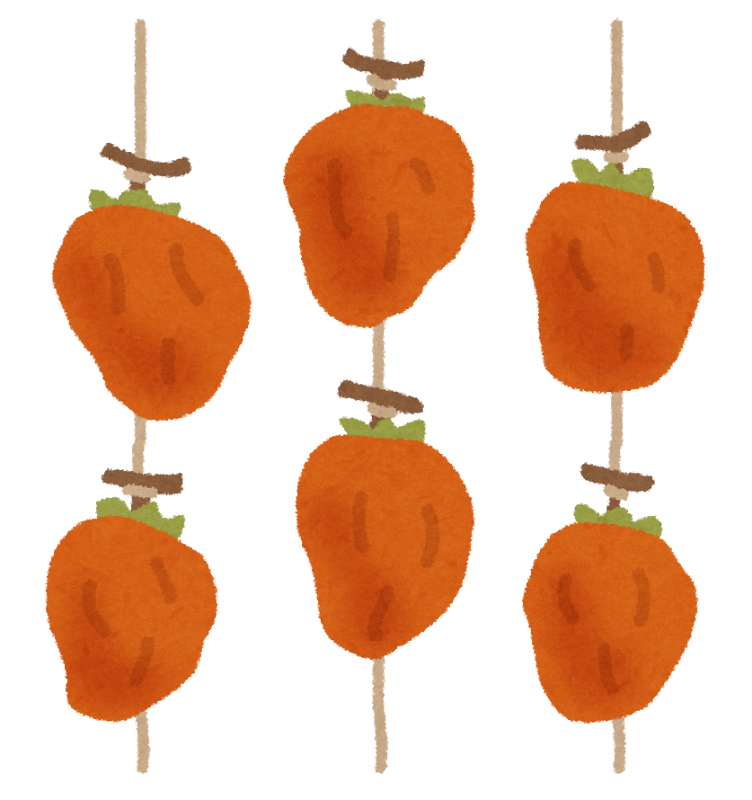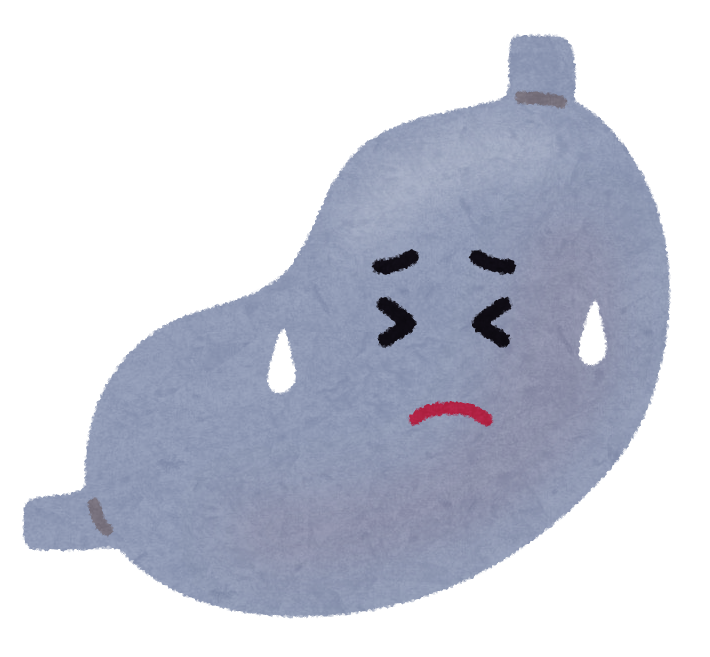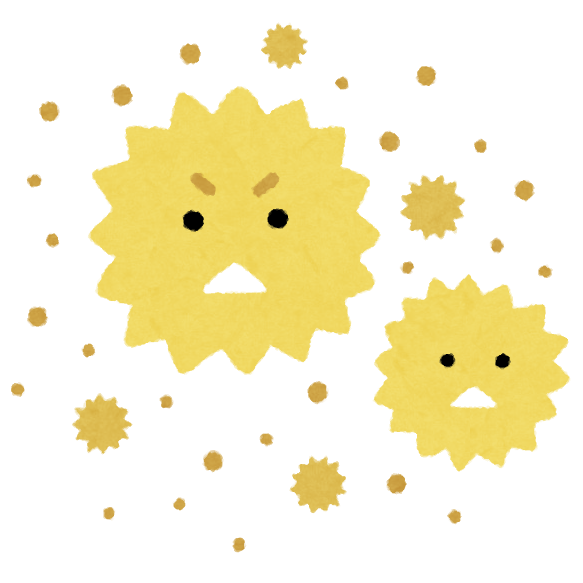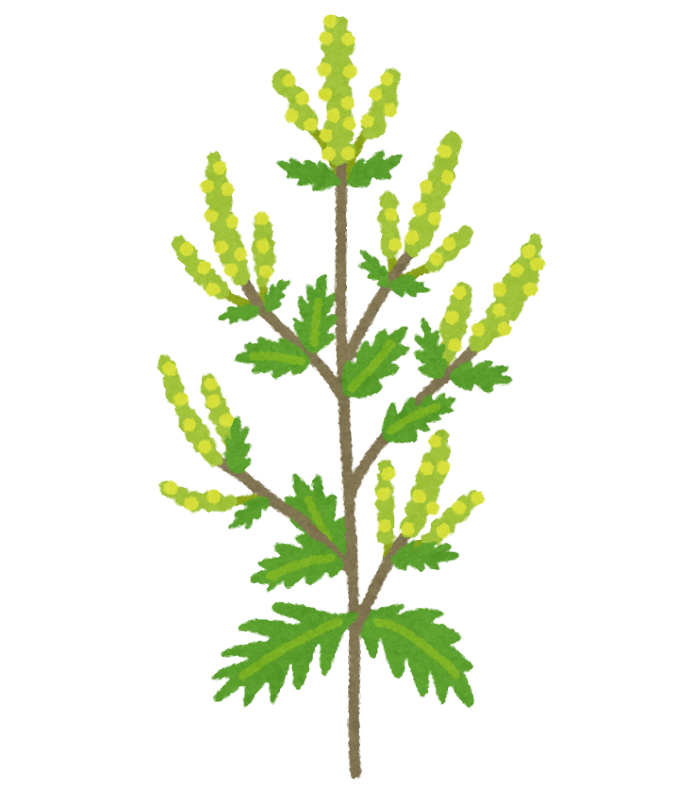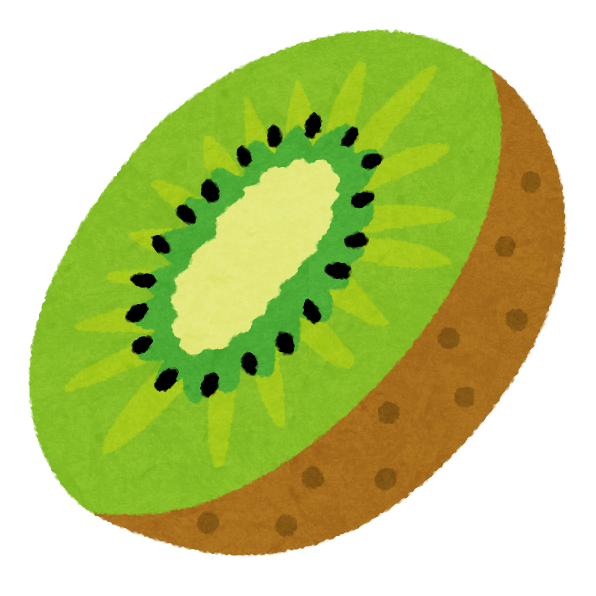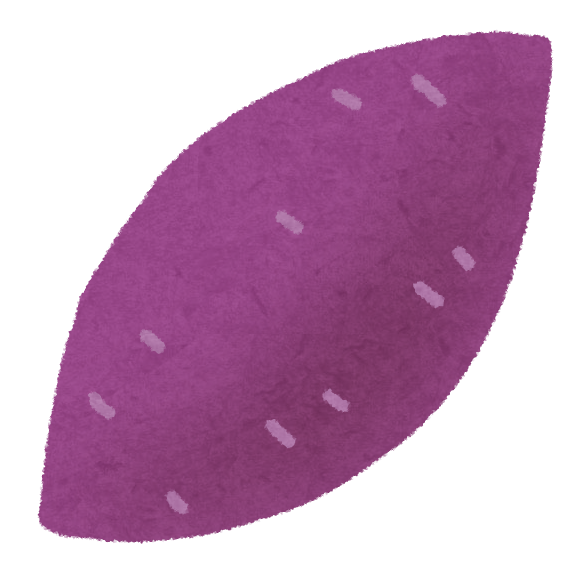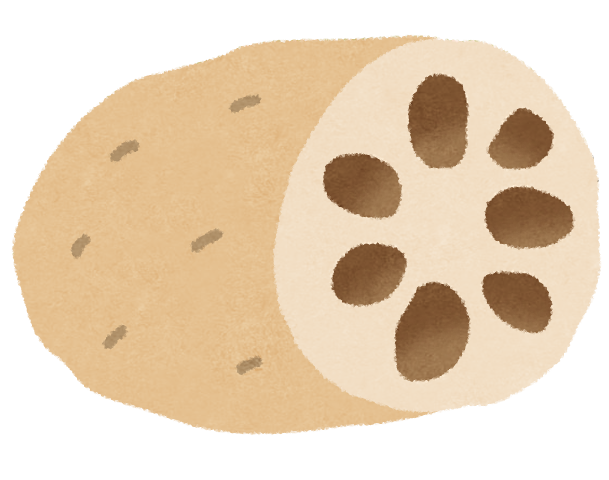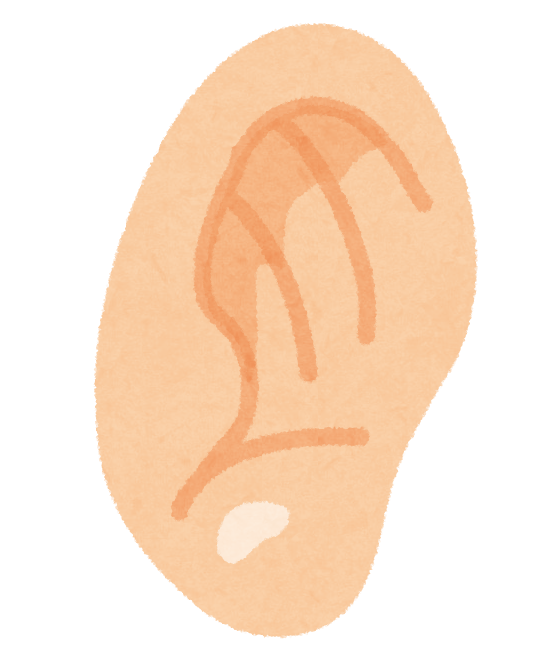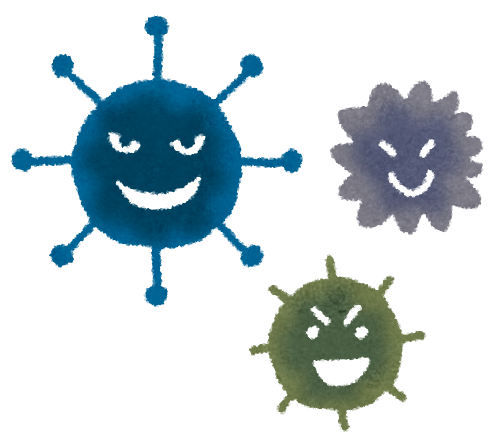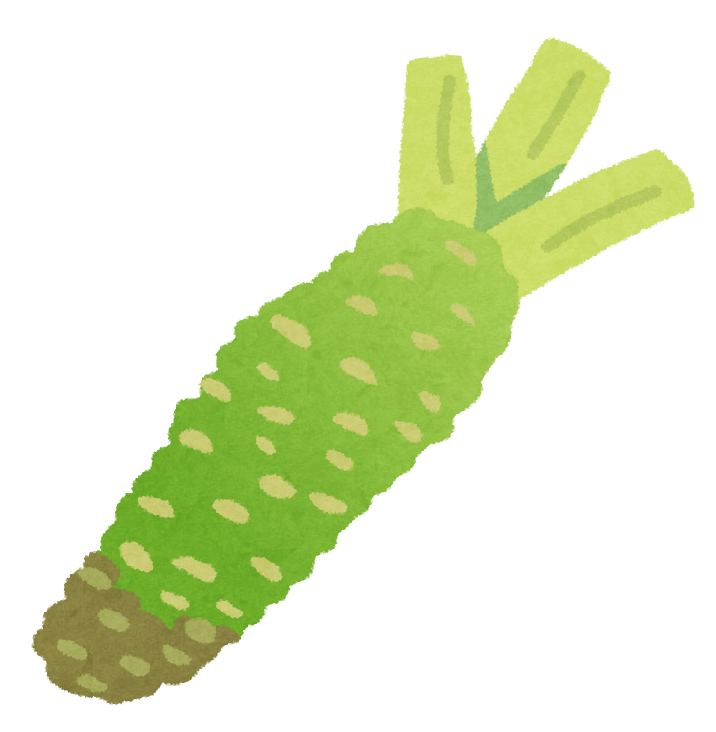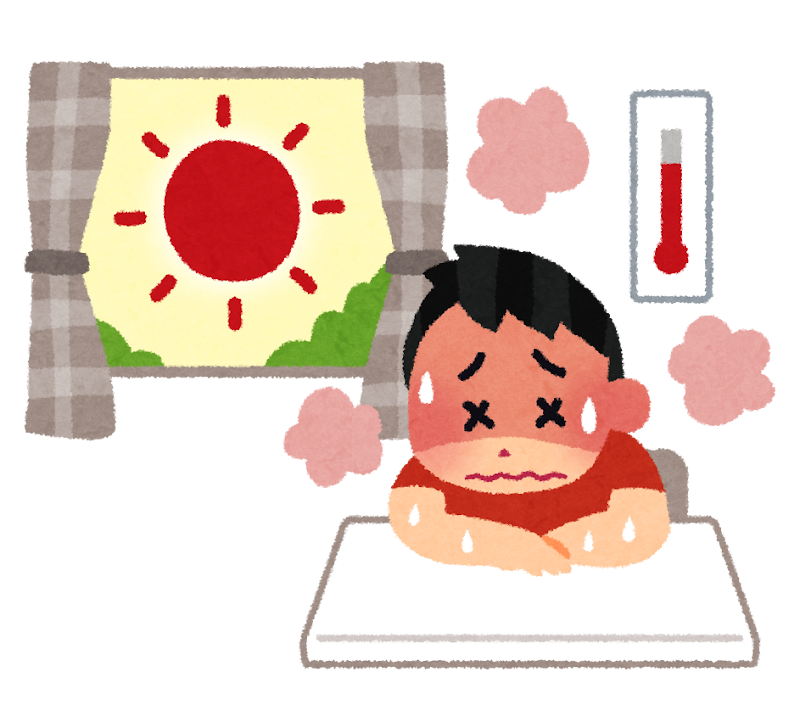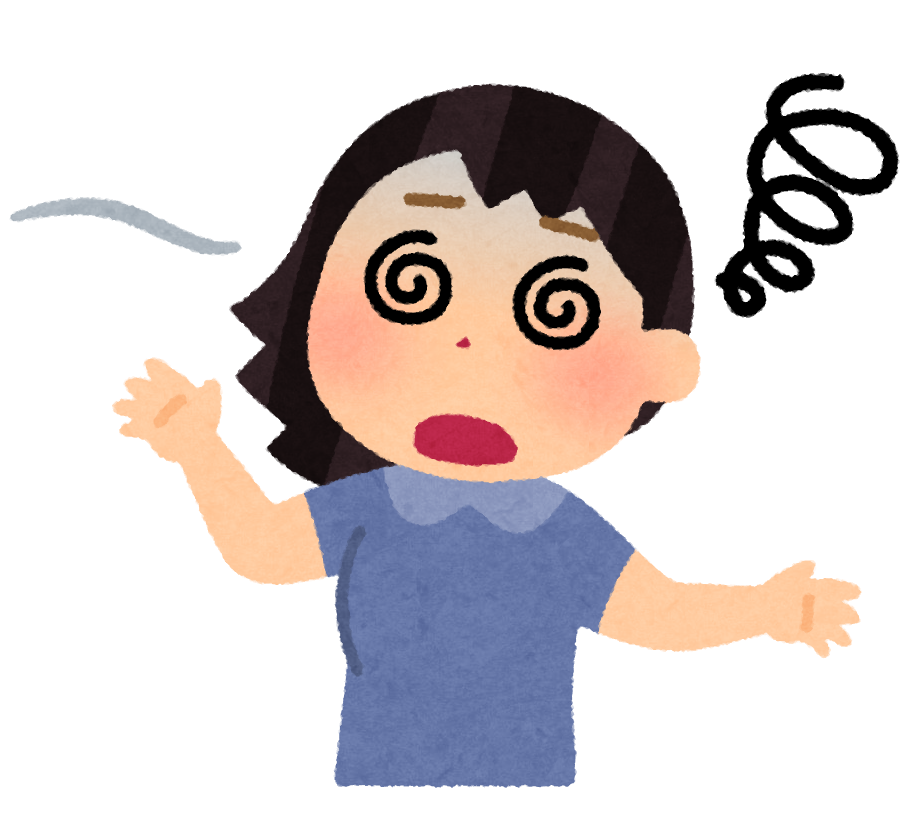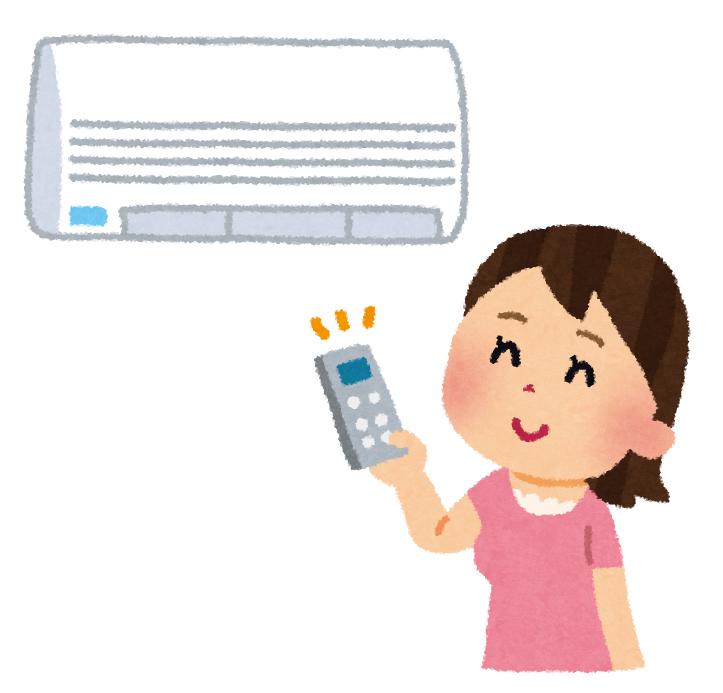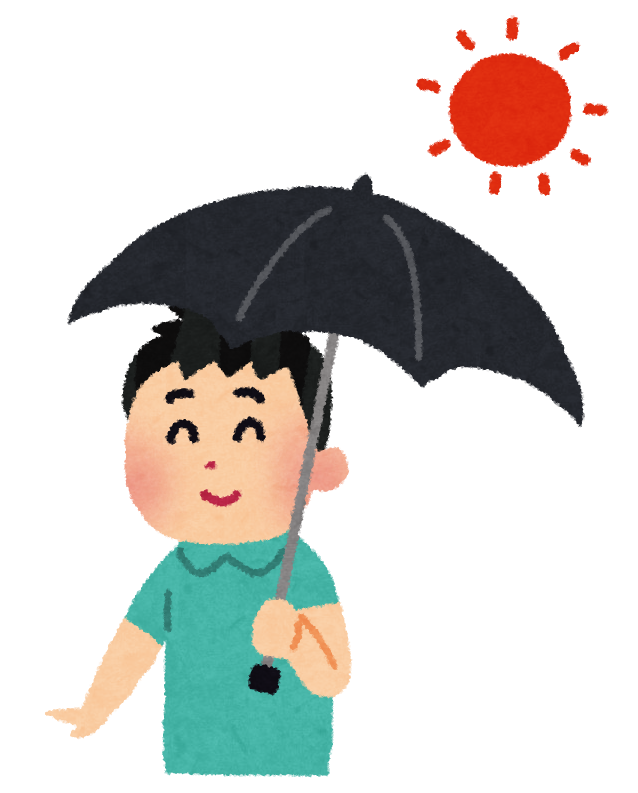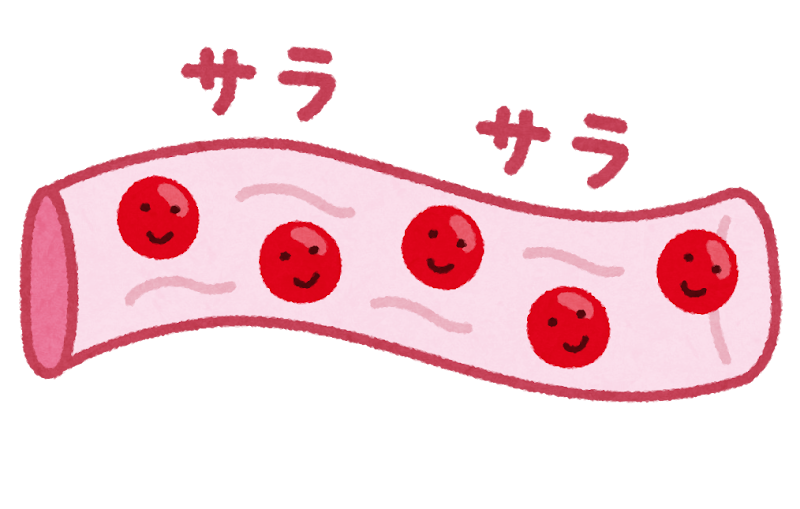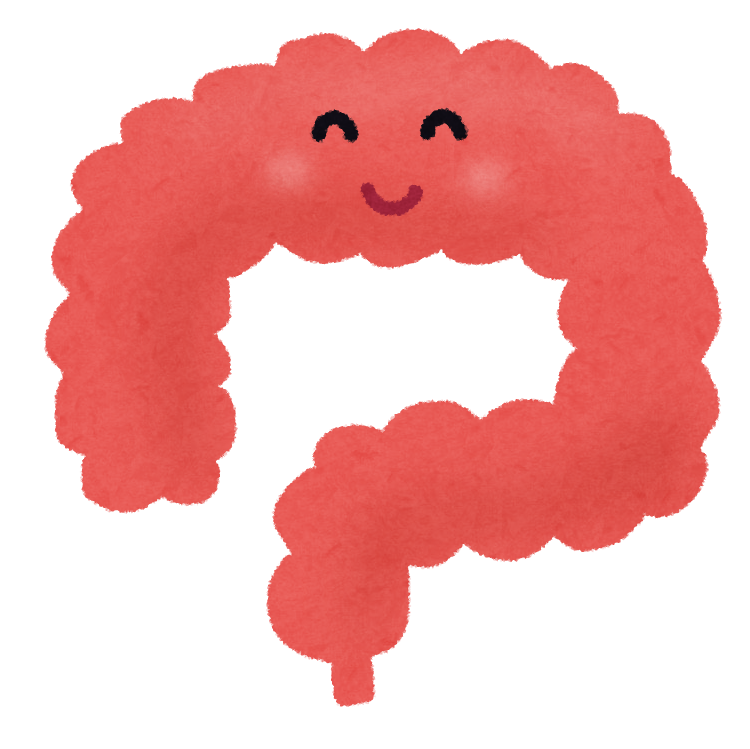冬になると手足の冷えや肩こり、疲れやすさを感じる方が増えてきます。これは気温の低下によって血行が悪くなり、自律神経のバランスが乱れやすくなることが大きな原因です。こうした冷えによる不調を予防・改善するために注目されているのが「温活」です。本記事では、冷えが起こる仕組みとともに、日常生活で無理なく取り入れられる温活のポイントを分かりやすくご紹介します。
◆冷えはなぜ起こる?冬に体が冷えやすくなる理由
冷えは体質だと思われがちですが、その多くは生活環境や習慣の影響を受けています。まずは冷えが起こる仕組みを理解し、自分の生活の中に当てはまるポイントがないか振り返ってみることが大切です。

◎気温低下による血流の変化
冬に体が冷えやすくなるもっとも大きな理由は、気温の低下です。寒さを感じると体は熱を逃がさないように血管を収縮させるため、手足など末端への血流が悪くなります。血流の低下は肩こりやむくみの原因にもなり、さまざまな不調につながりやすくなります。
◎運動不足による発熱量の低下
体温の多くは、筋肉の働きによって作り出されています。しかし冬は寒さの影響で外出や運動の機会が減り、体を動かす量がどうしても少なくなりがちです。運動不足になると筋肉量や代謝が低下し、体が熱を生み出しにくい状態になります。

◎自律神経の乱れも冷えの原因に
冷えは外気の影響だけでなく、自律神経の働きとも深く関係しています。ストレスや不規則な生活、睡眠不足などが続くと自律神経のバランスが崩れ、血管の収縮と拡張がうまく調整できなくなるのです。その結果、血行が悪くなり、体温調節がうまくいかなくなることがあります。
◎日常習慣が冷えを悪化させることも
さらに、普段何気なく行っている習慣が冷えを強めているケースもあります。シャワーだけで入浴を済ませてしまう、冷たい飲み物を多くとる、締め付けの強い衣服を着用しているなどの行動は、血流を妨げ、体を冷やす要因になります。
◆すぐできる!毎日の生活で実践したい温活習慣
特別な道具がなくても、温活習慣を意識するだけで体は少しずつ温まりやすくなります。まずは、無理のない方法から取り入れてみましょう。

◎入浴で体を芯から温める
温活の基本となるのが毎日の入浴です。シャワーだけで済ませてしまうと体の表面しか温まらず、血流の改善にはつながりにくくなります。38~40度くらいのぬるめのお湯にゆっくりつかることで、全身の血行が良くなり、冷えの改善が期待できます。とくに就寝前の入浴はリラックス効果も高く、質の良い睡眠にもつながるためおすすめです。
◎衣服で冷えやすい部位を守る
首・手首・足首は血管が皮膚に近く、冷えを感じやすい場所です。この“3つの首”を冷やさないよう意識するだけでも体感温度は大きく変わります。マフラーや手袋、厚手の靴下などを活用し、体の熱を逃がさない工夫をしましょう。締め付けの強い服装は血流を妨げるため、ゆったりした衣類を選ぶことも大切です。

◎軽い運動で血行を促す
運動は、体を内側から温めるもっとも効果的な方法の一つです。激しい運動でなくても、軽いストレッチやウォーキングを毎日の習慣にするだけで、筋肉が動き、血流が良くなります。長時間同じ姿勢でいる人は、こまめに体を動かすことを心がけると冷えにくい体づくりにつながります。
◎睡眠の質を高めて体温を整える
冷えの改善には十分な睡眠も欠かせません。寝る直前までスマートフォンを使うと交感神経が優位になり、体が温まりにくくなります。就寝前はリラックスできる時間をつくり、規則正しい生活リズムを整えることが、温活の大切なポイントです。
◆体の中からポカポカに!温活におすすめの食材
食事を少し工夫するだけで、体は内側からじんわりと温まりやすくなります。毎日の食卓に温活の視点を取り入れてみましょう。

◎体を温める食材を上手に取り入れる
温活は外側から体を温めるだけでなく、食事による内側からのケアもとても重要です。生姜やねぎ、にんにくといった香味野菜には血行を促す働きがあり、冷えを感じやすい季節にぴったりの食材といえます。また、大根やれんこん、ごぼうなどの根菜類は体を温める性質があるとされ、冬の食事に積極的に取り入れたい食材です。
◎発酵食品で代謝をサポート
味噌や納豆、ヨーグルトといった発酵食品も温活の心強い味方です。腸内環境が整うことで代謝が高まり、体温を保ちやすくなります。毎日の食卓に一品加えるだけでも、体の内側から健康を支えることにつながります。温かい味噌汁や発酵食品を使った料理は、寒い時期の体調管理におすすめです。

◎体を冷やす食べ方には注意
一方で、冷たい飲み物のとり過ぎや生野菜中心の食事などは、体を冷やす原因になることがあります。とくに冬場は、できるだけ温かい料理を選び、飲み物も常温や温かいものを意識すると安心です。食事の内容だけでなく、「冷やさない食べ方」を心がけることも大切なポイントです。
◎取り入れやすいメニューの工夫
忙しい毎日でも、温活は難しいものではありません。生姜を加えたスープや鍋料理、根菜たっぷりの煮物などは手軽に作れて体も温まります。朝食に温かい飲み物を一杯プラスするだけでも、体の冷え方は変わってきます。無理なく続けられる方法を選ぶことが、温活を習慣にするコツです。
***
冷えは単なる体質ではなく、生活習慣の積み重ねによって起こることがほとんどです。だからこそ、日々の過ごし方を少し見直すだけで改善できる可能性があります。お風呂や運動、食事など身近なところから温活を取り入れれば、体調が整い、寒い季節も快適に過ごせるようになります。今年の冬は「体を温めること」を意識して、無理のない温活習慣を始めてみましょう。