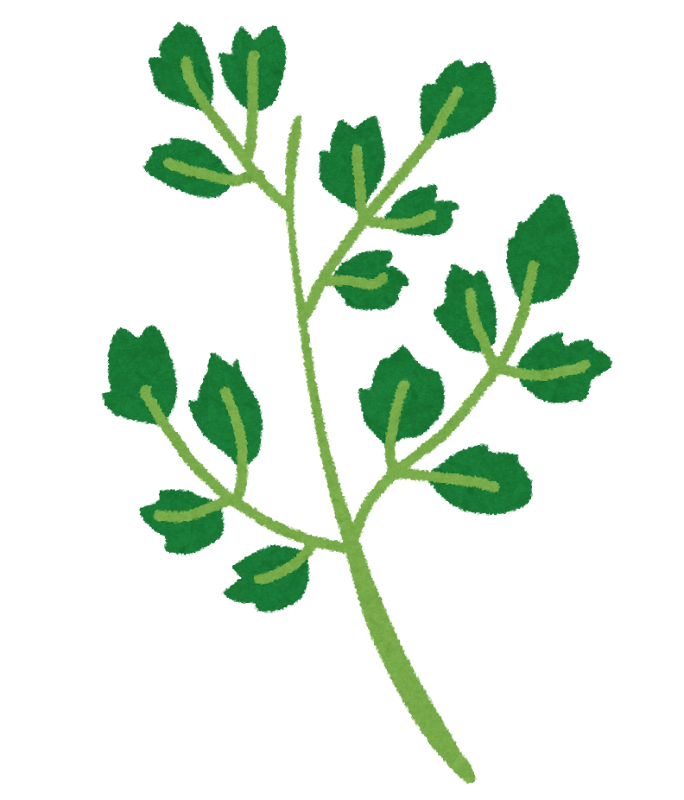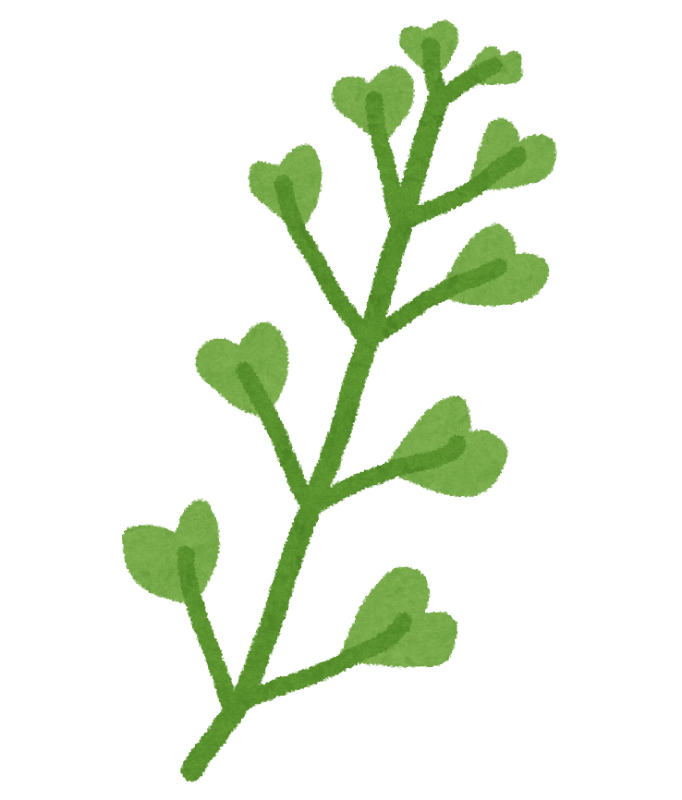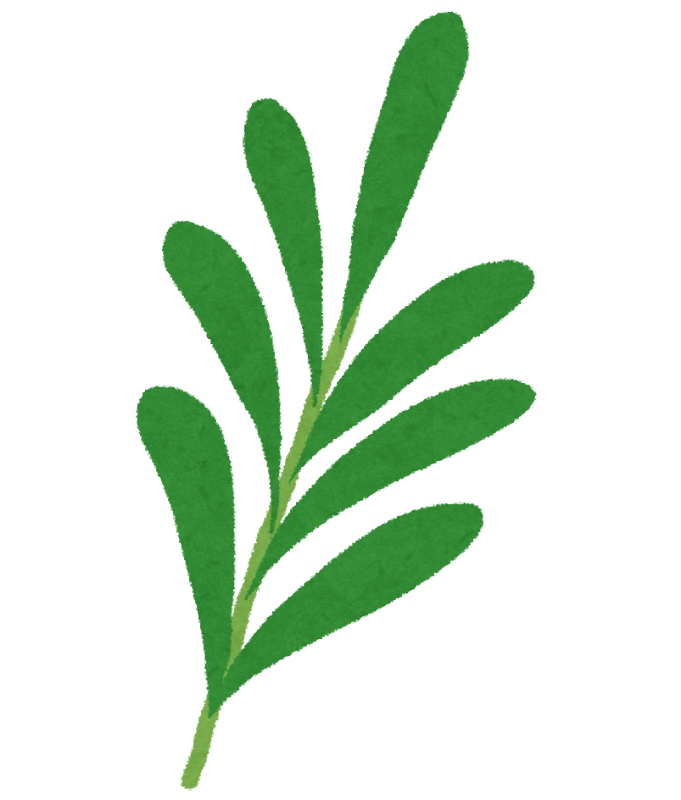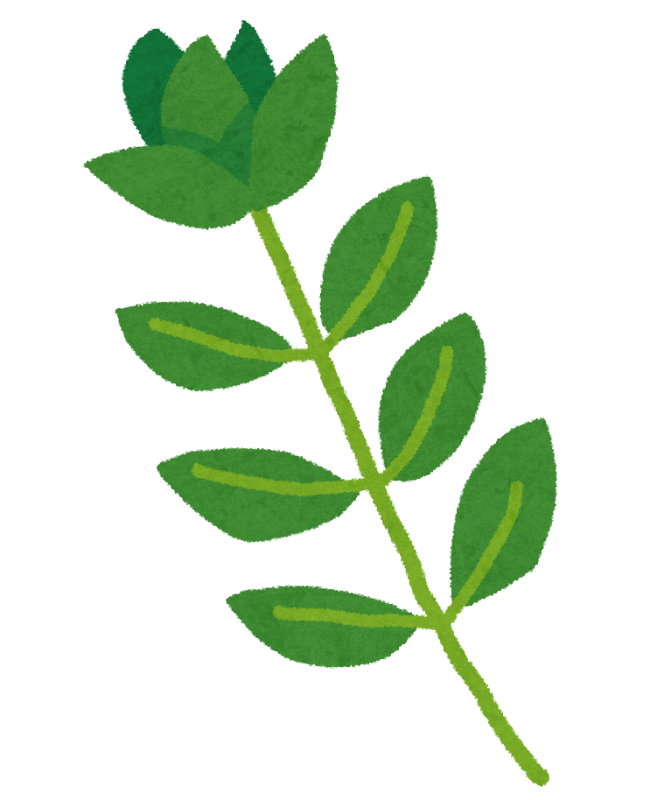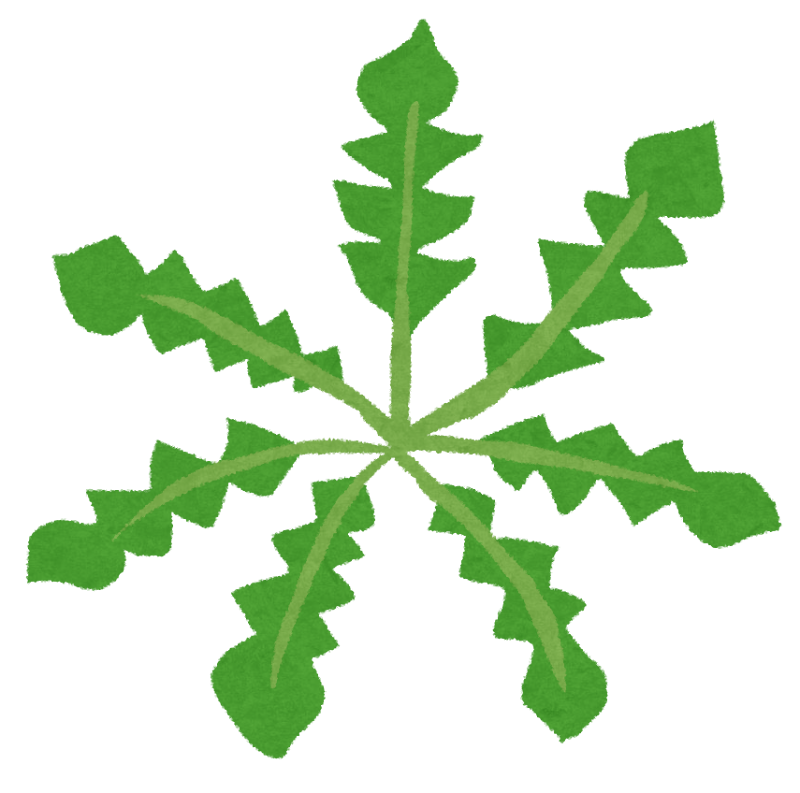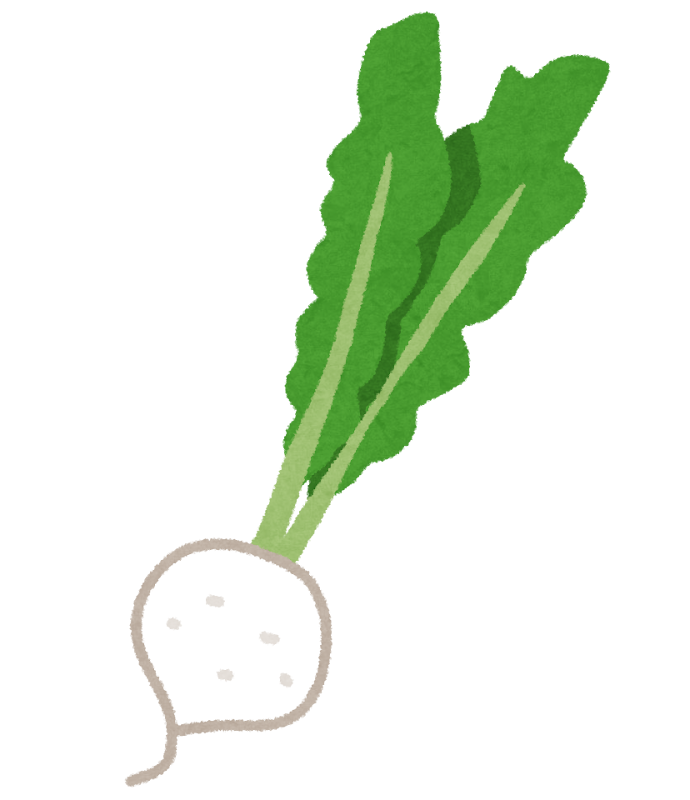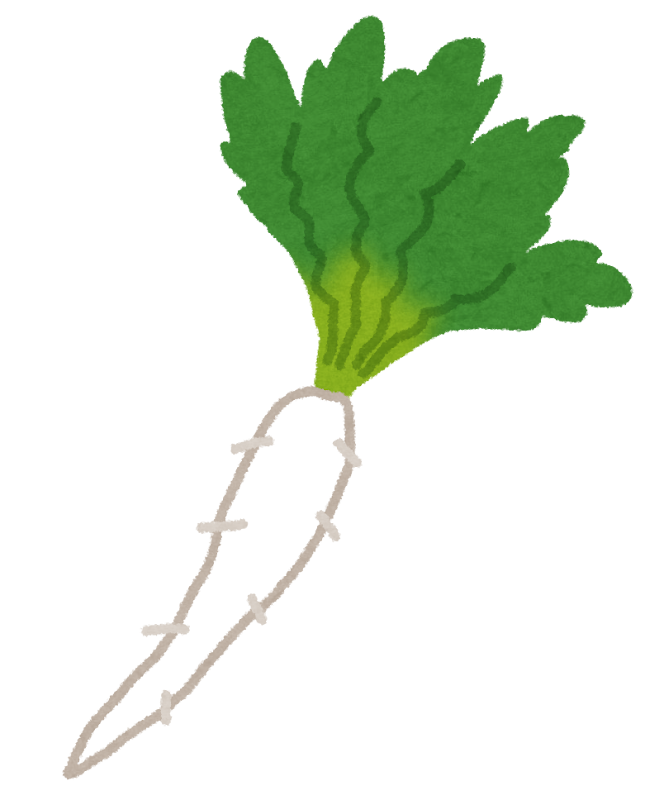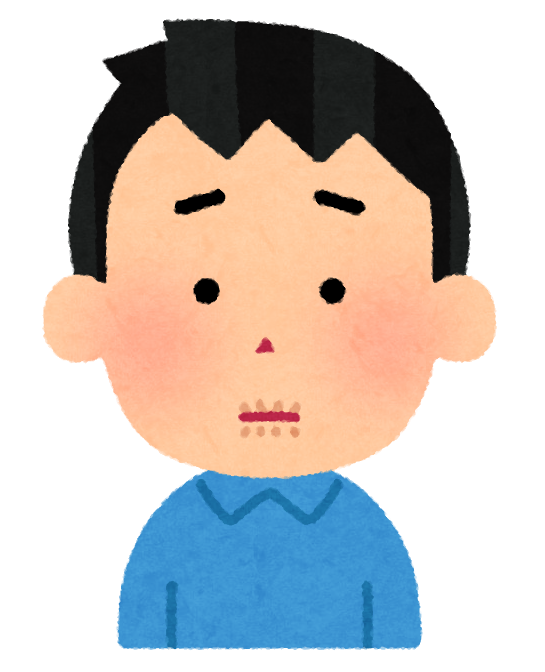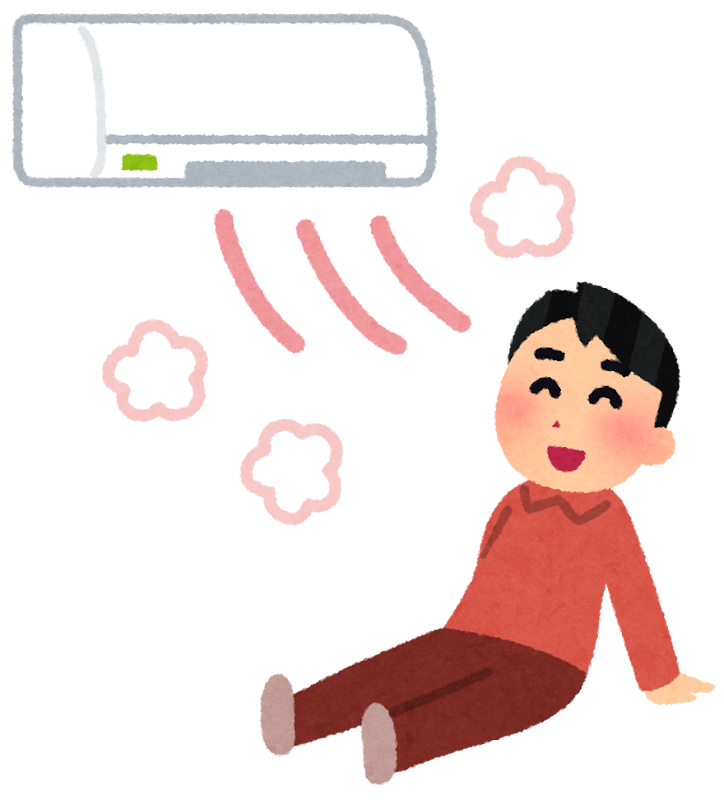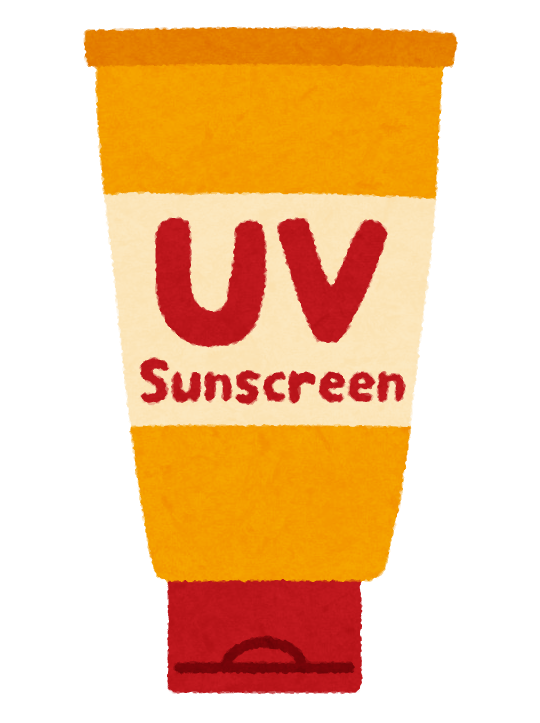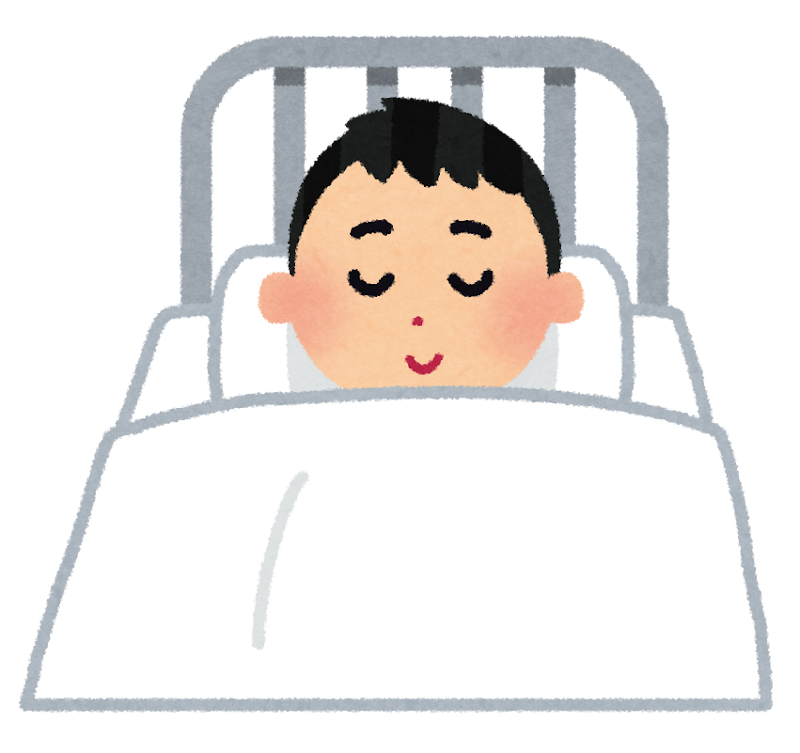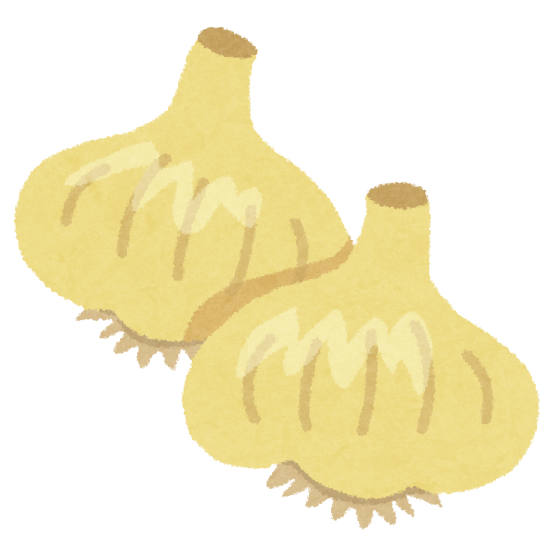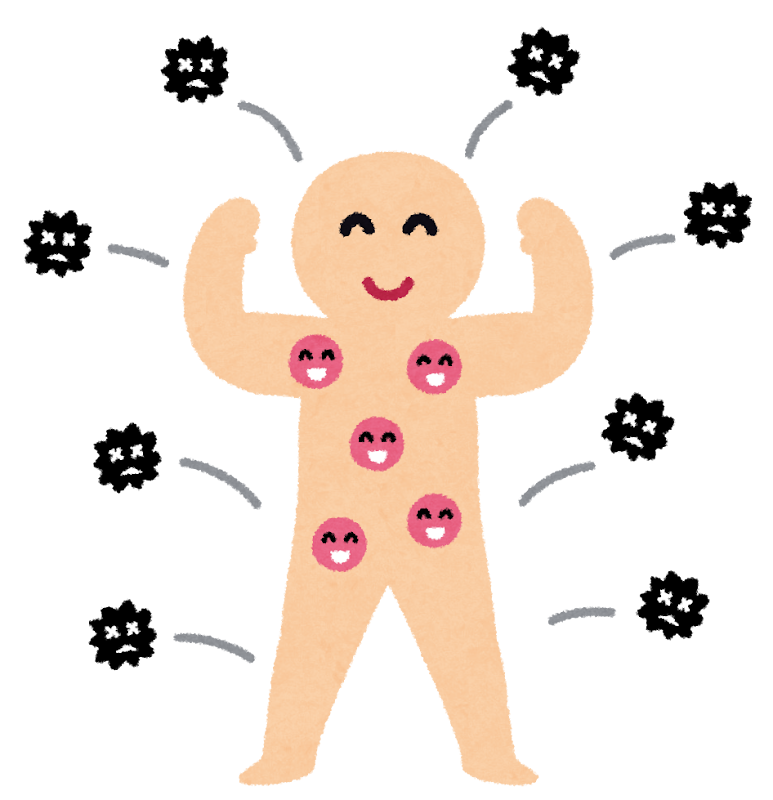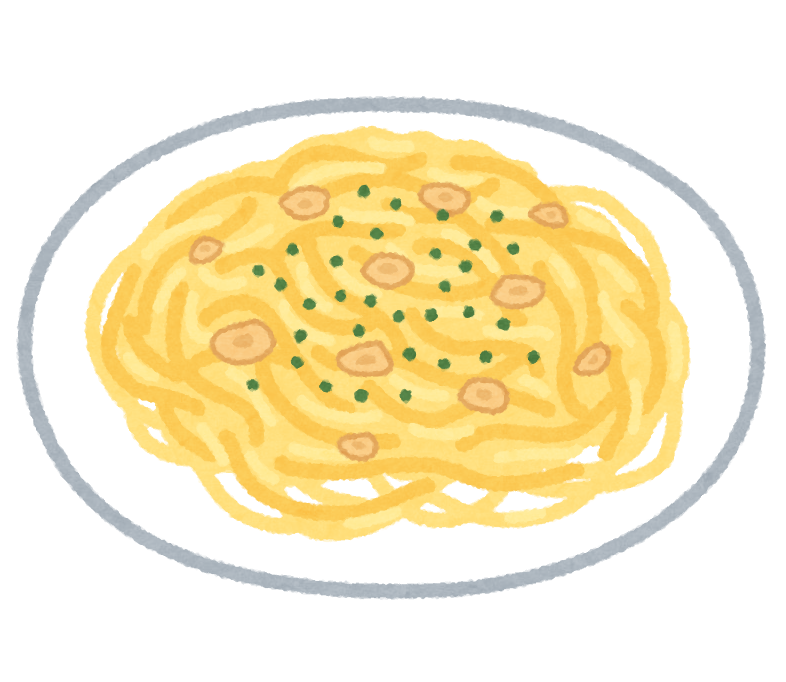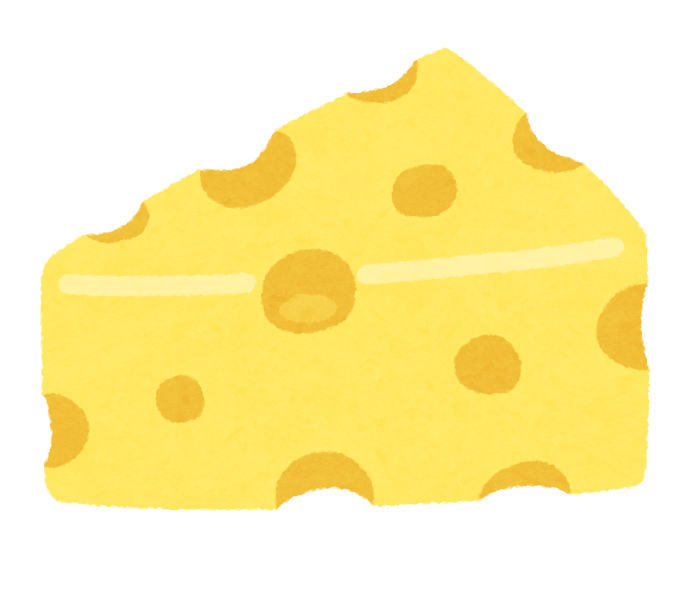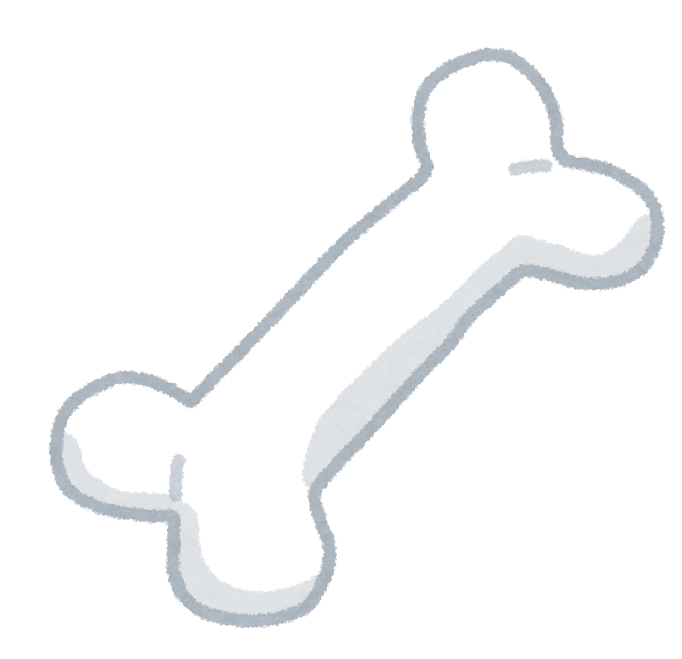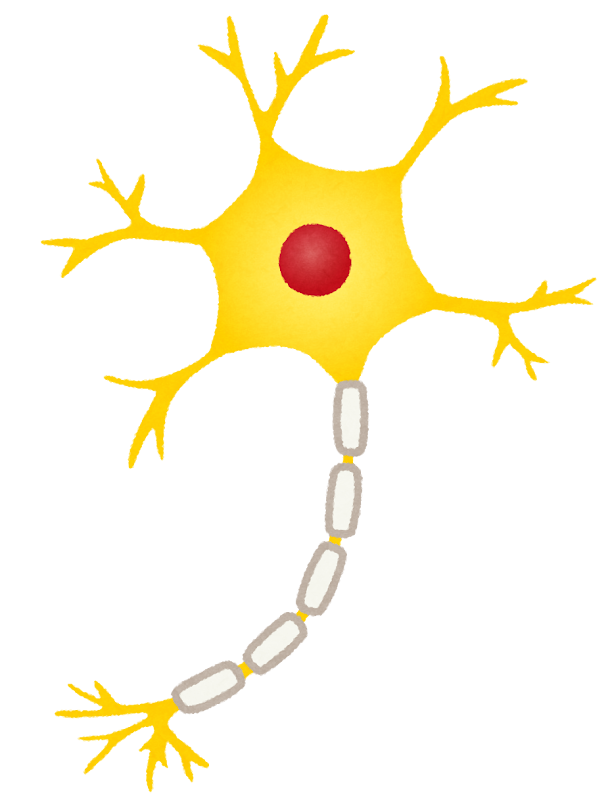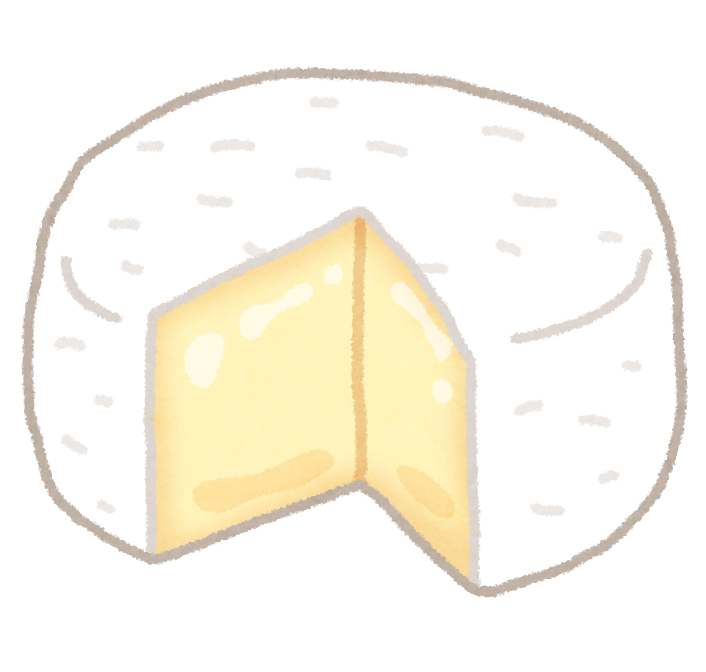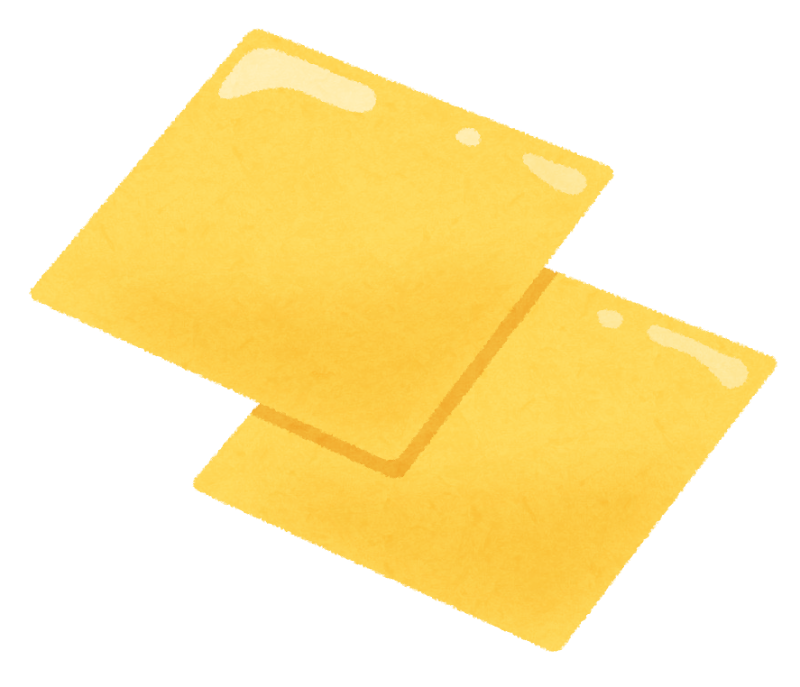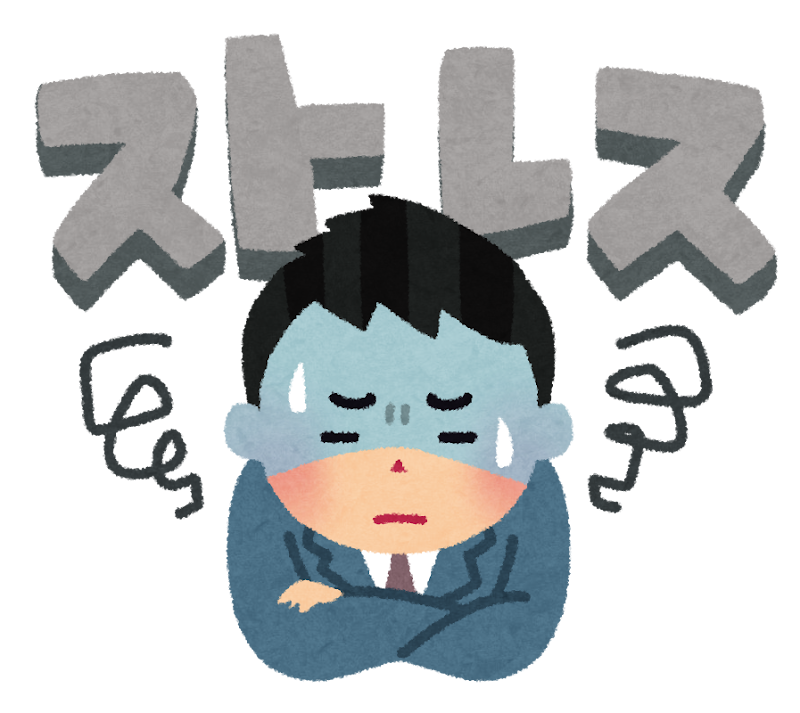
新生活のスタートは期待と不安が入り混じり、ストレスを感じることも多いでしょう。新しい環境や人間関係に適応する過程で、心身のバランスが崩れがちになります。今回は、そんなときに役立つ、日常に取り入れやすいセルフケアの方法を紹介します。無理なく続けられるケア方法を実践して、心地よい新生活を送りましょう。
◆新生活のストレスの原因とその影響
新しい環境に飛び込むとき、期待と同時に不安もつきまとうものです。まずは、新生活における主なストレスの原因と、それが体と心に与える影響について見ていきましょう。
◎新しい環境への適応に伴う不安

新しい職場や学校、引っ越しなどで環境が大きく変わると、自分の居場所や役割が定まらず不安を感じることがあります。これにより自己評価が下がり、「自分にできるだろうか」「周りに受け入れられるだろうか」といった心配が募ります。慣れないルールや新たな生活リズムへの適応に追われ、心が落ち着かない状態になることも少なくありません。
◎人間関係の変化がもたらすプレッシャー
新しい環境では、新たな人間関係が生まれます。上司や同僚、クラスメート、近隣の住民との関係性がまだ確立されていないため、コミュニケーションに緊張感が生まれます。「うまく話せない」「誤解されるかも」という不安が重なると、自己表現が難しくなり、孤立感に襲われることもあるでしょう。これらのプレッシャーは、時に大きなストレス源となります。
◎ストレスが心身に及ぼす影響
新生活のストレスが長期間続くと、心身にさまざまな影響が現れます。疲労感や体のだるさ、頭痛、肩こりといった身体的な症状が出ることもあります。また、ストレスホルモンが増加することで、夜眠れなくなったり、食欲が低下したりする場合もあるかもしれません。さらに、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなったりするなど、心の不調にもつながります。
◆ストレス軽減に効果的なセルフケア方法
新生活のストレスに対処するためには、セルフケアの工夫が大切です。日常生活の中で取り入れやすいリラクゼーション法や、気分転換の方法を活用することで、心身の負担を軽減しましょう。
◎簡単にできるリラクゼーション法

新生活のストレスを感じたときにすぐに取り入れられるリラクゼーション法として、深呼吸や瞑想、ストレッチがあります。
深呼吸は、副交感神経を活性化させ、リラックス効果をもたらします。ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口からゆっくり吐き出すことで、緊張を和らげましょう。瞑想は、静かな場所で目を閉じて数分間心を落ち着けるだけでも効果があります。また、ストレッチは筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、リフレッシュ効果を高めます。リラックス効果が持続するため、朝や寝る前に軽く行うのがおすすめです。
◎リフレッシュのための気分転換
気分転換は、ストレス解消に有効な方法です。
忙しい日常の中でも、外に出て散歩をするだけで気分がリフレッシュされます。自然の中を歩くと、心が穏やかになり、ストレスホルモンの減少にもつながります。
また、自分の趣味に没頭する時間を意識的に作ることも大切です。好きな音楽を聴いたり、絵を描いたり、読書をしたりすることで、日常のプレッシャーから一時的に解放される感覚が得られます。自分だけのリラックスタイムを大切にしましょう。
◎食事や睡眠で体調管理
心身の健康を保つためには、バランスの取れた食事と質の良い睡眠が欠かせません。
食事ではビタミンB群やマグネシウムを含む食品(豚肉、魚、ナッツ類など)を意識して摂取し、神経の安定を図りましょう。また、糖質やカフェインの過剰摂取は避け、体を温めるスープやハーブティーを取り入れるとリラックス効果が期待できます。
睡眠環境を整えるためには、就寝前のスマートフォンの使用を控え、部屋を暗くして静かな状態を作ることが大切です。
◆心の健康を保つためのセルフケア
新生活では、心の健康を保つことが特に重要です。ここでは、心の健康を守るためのセルフケアについて紹介します。
◎感情の整理と発散
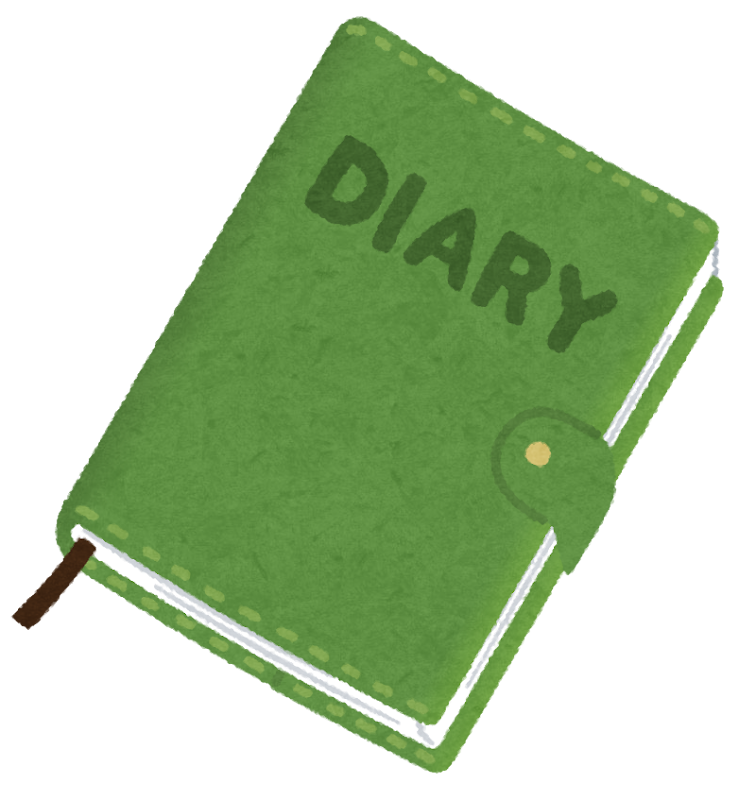
新しい環境に慣れる過程で感じるストレスや不安は、無理に抑え込まずに向き合うことが大切です。感情を整理し、発散する方法として日記を書くことは効果的です。日記にその日の出来事や感情を書き出すことで、自分の気持ちを客観的に見つめ直せます。
また、信頼できる友人や家族に話すことも心の負担を軽減する方法です。話すことで気持ちが整理され、共感や励ましを得られることで安心感が生まれます。
◎自己肯定感を高める習慣
新しい環境では失敗や戸惑いがつきものですが、自分を責めすぎないことが大切です。小さな達成感を意識することで、自己肯定感を高める習慣を持ちましょう。たとえば、「今日は早起きできた」「一つタスクを終えた」といった些細な成功体験を自分で認め、褒めることが大切です。
また、ポジティブな言葉を自分にかけることも効果的です。「自分は頑張っている」「少しずつ慣れていけば大丈夫」といった肯定的な言葉が、心の支えになります。
◎「無理しない」ことを意識する
新生活では、「すべて完璧にこなさなければ」と無意識にプレッシャーを感じることがあります。しかし、無理をしすぎると疲れが蓄積し、ストレスが増大してしまいます。完璧を求めず、マイペースを大切にする意識を持ちましょう。
周囲の期待や評価に左右されず、自分のペースでできる範囲で行動することが、心の健康を守るポイントです。「少しずつ慣れればいい」という気持ちで、自分を許してあげることが大切です。
***
新生活のストレスは誰もが経験するものですが、ちょっとしたセルフケアで心身の負担を軽減できます。自分に合った方法を見つけ、無理せずに取り入れることが大切です。新しい生活に慣れるまでの時間も、自分を大切にするチャンスと捉えて、楽しく前向きに過ごしましょう。