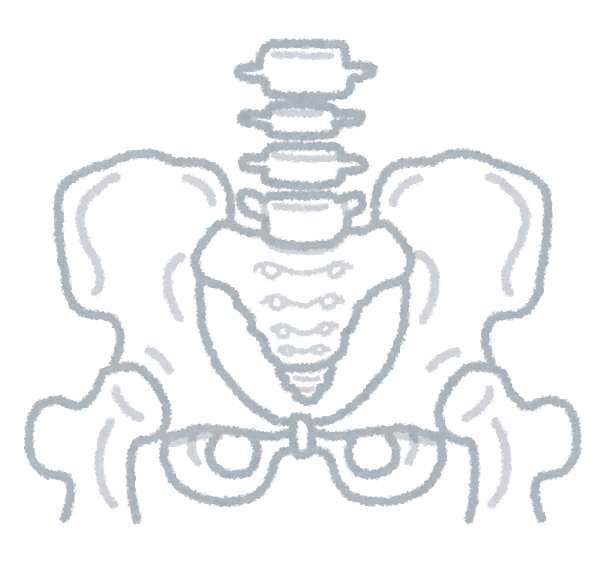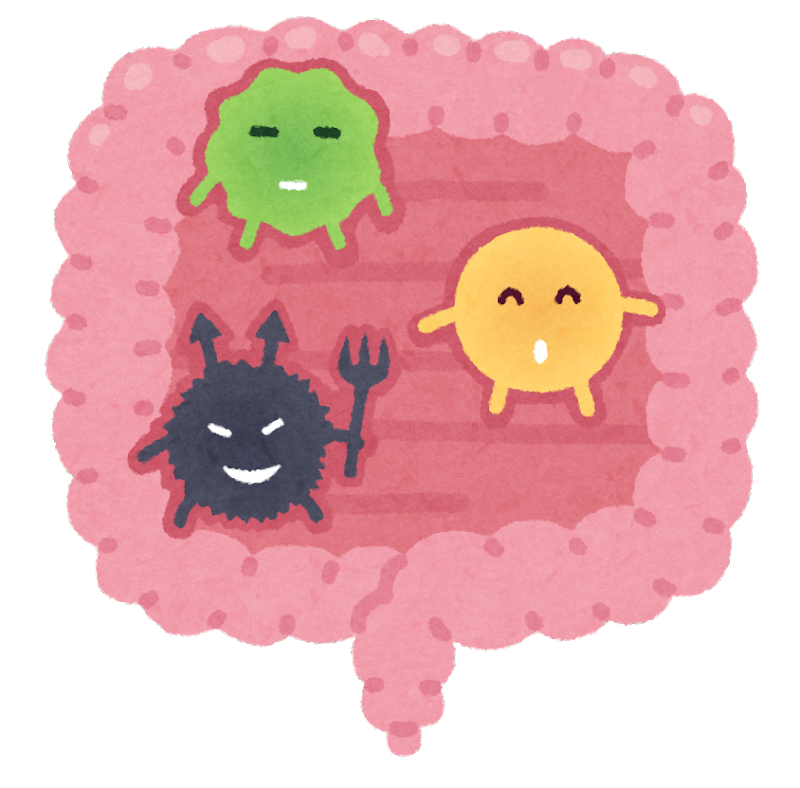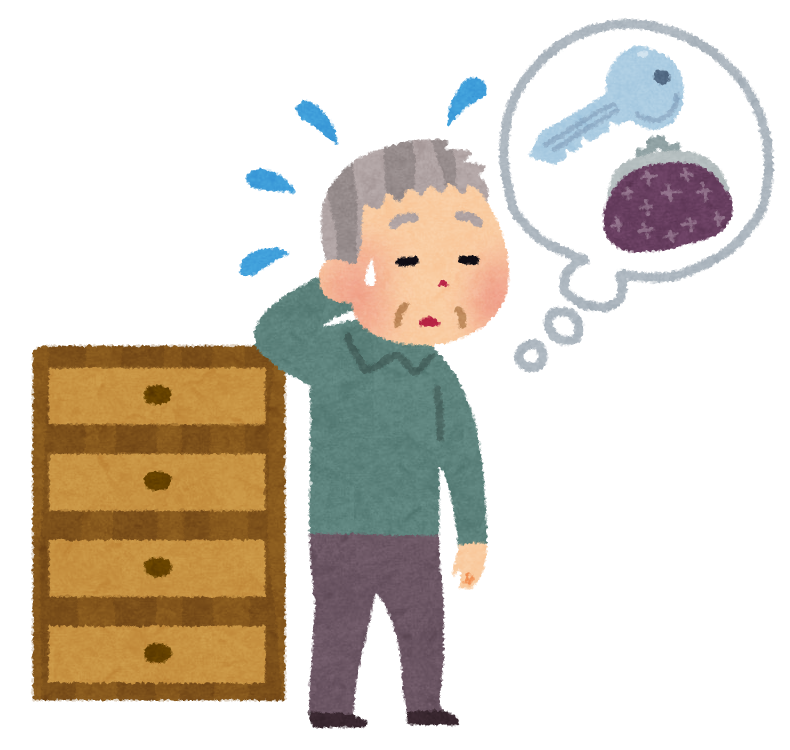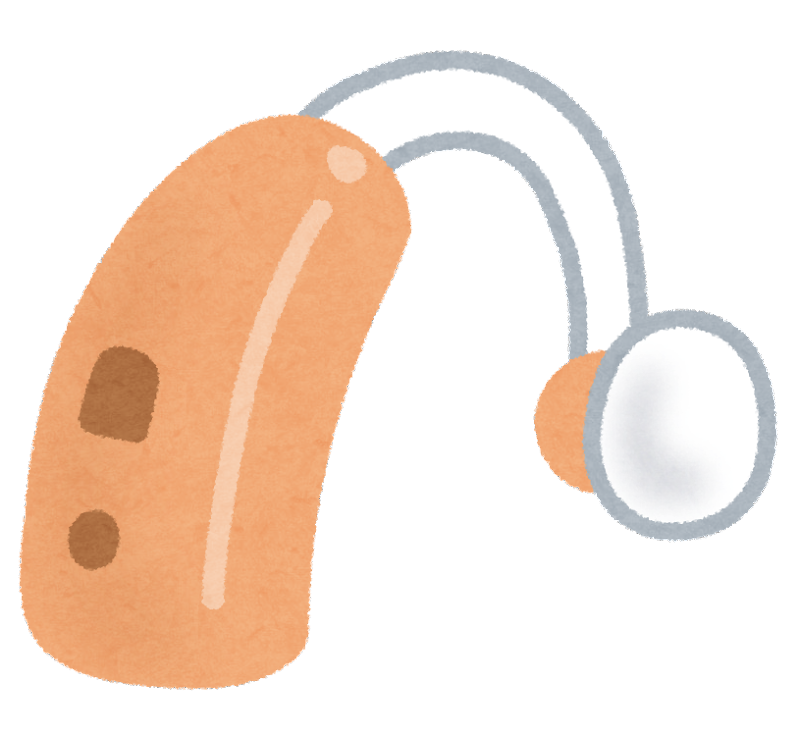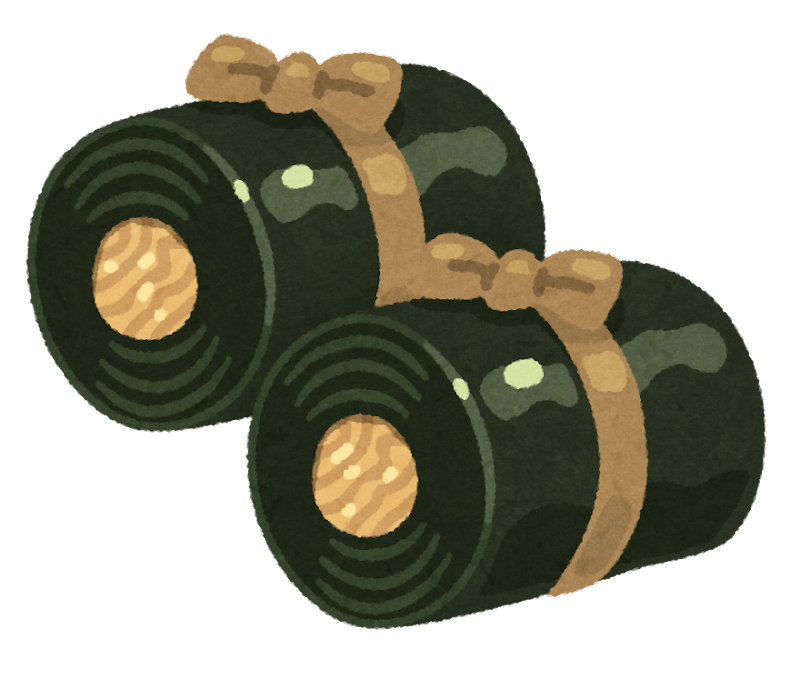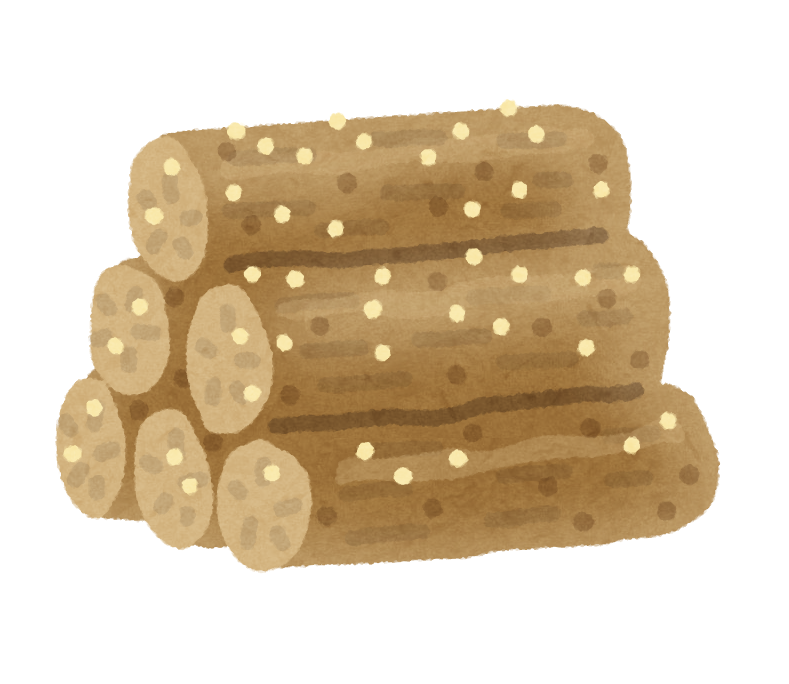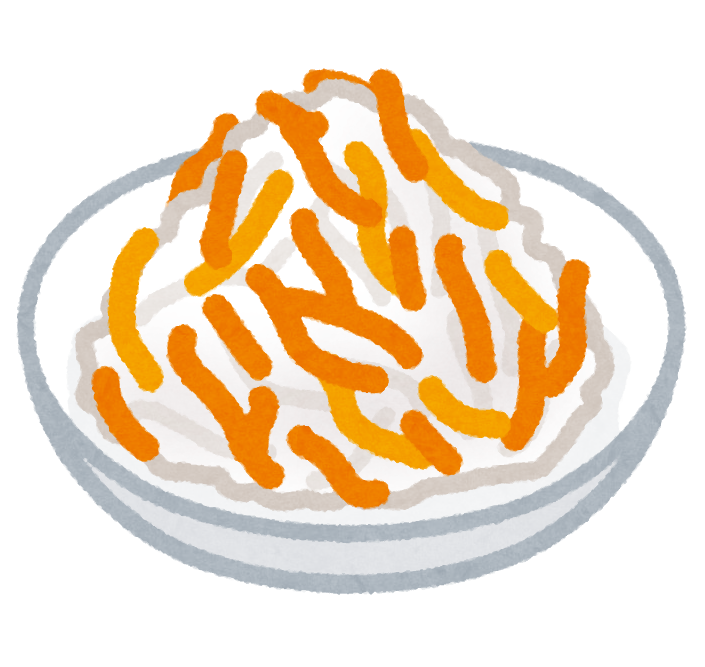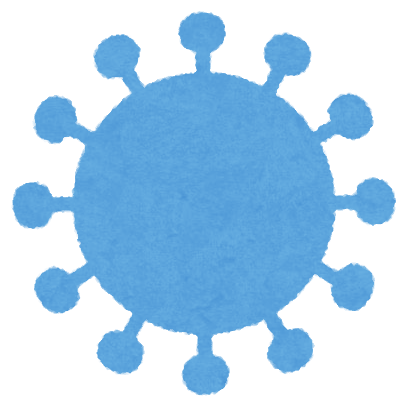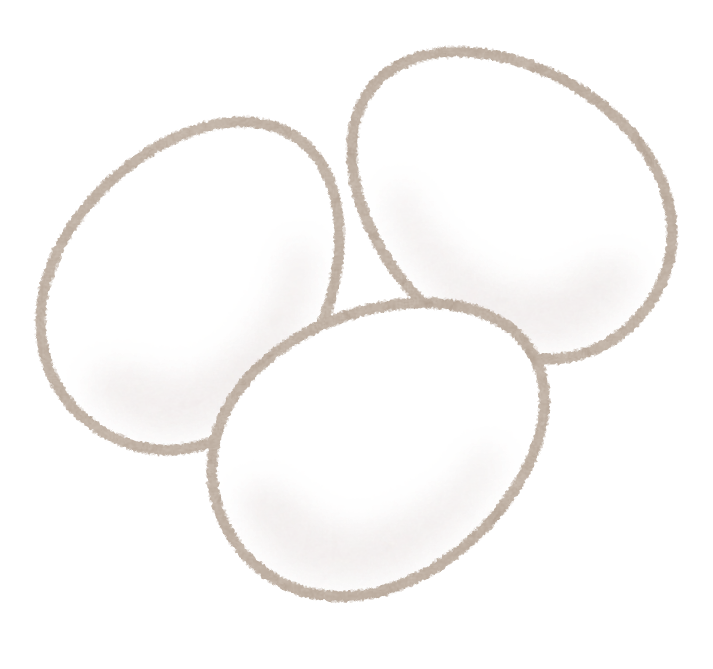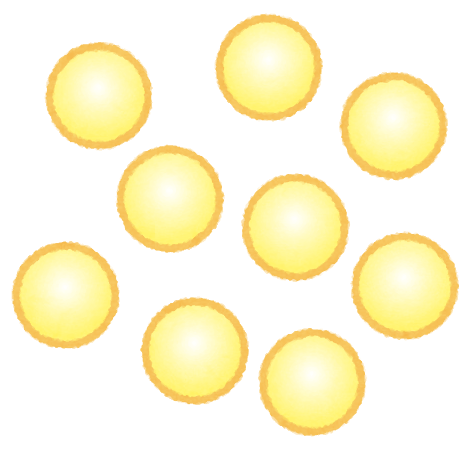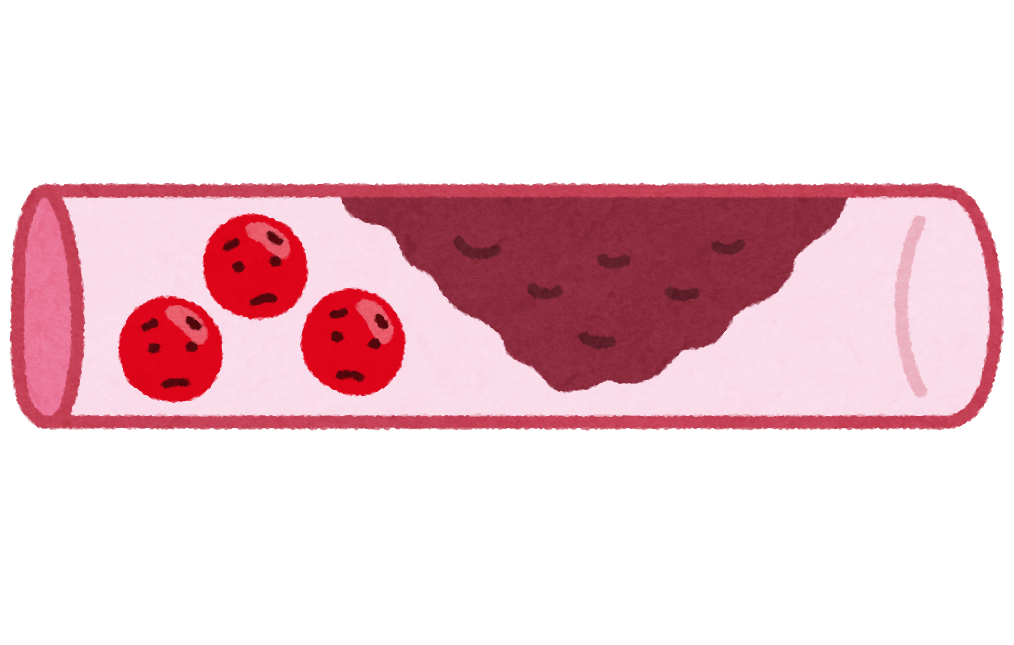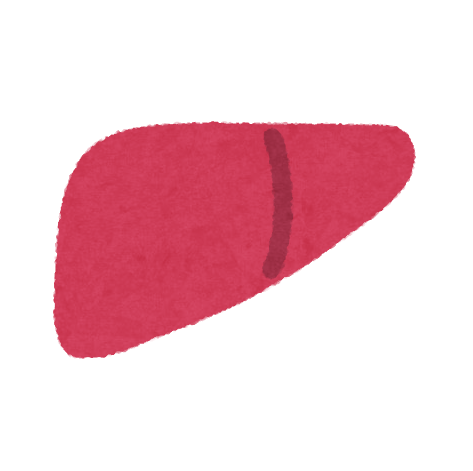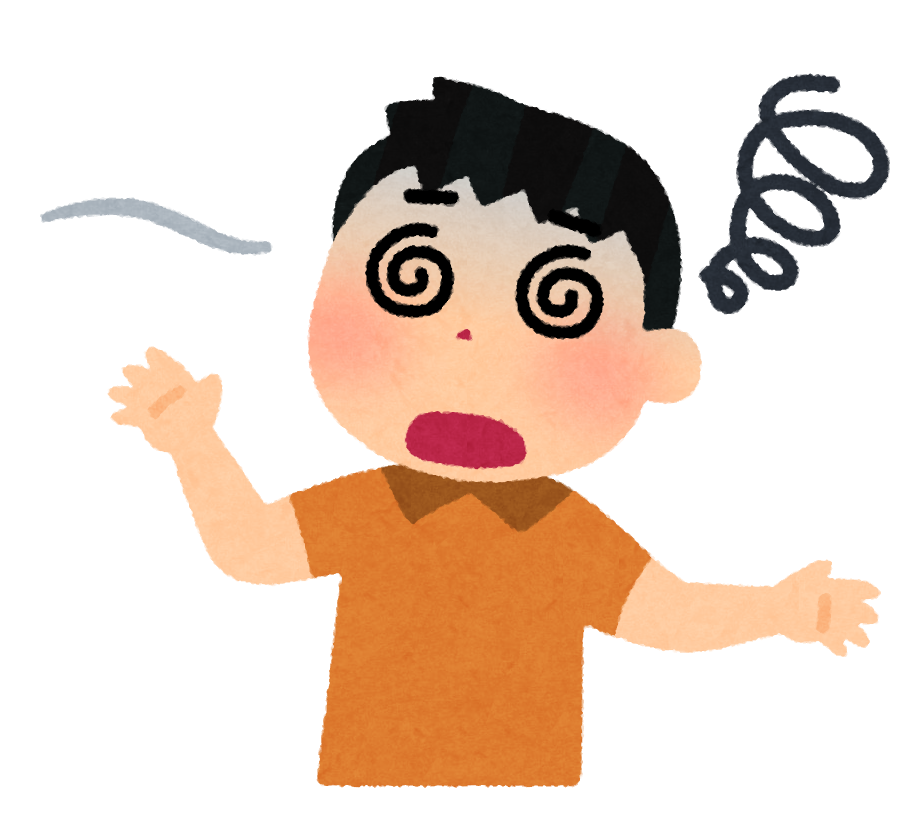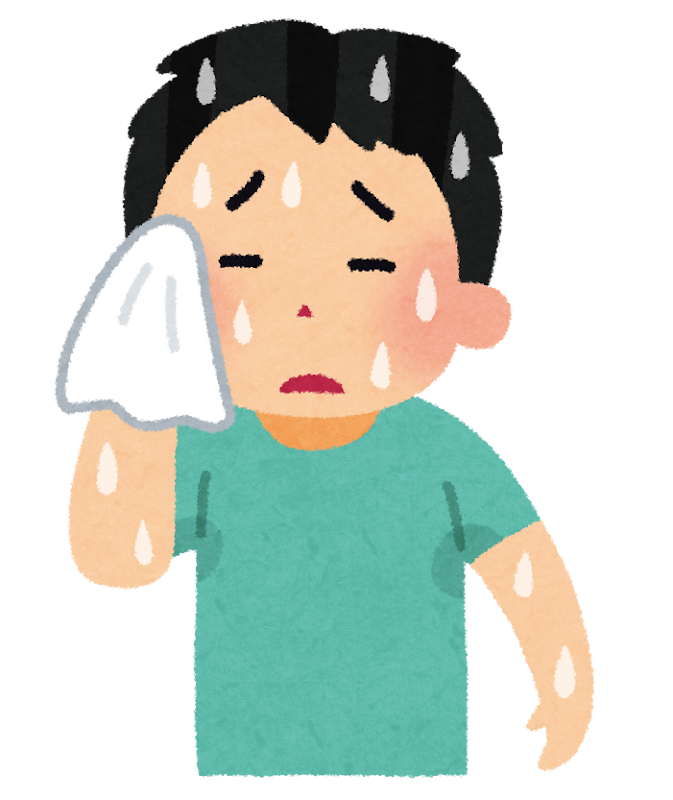
多汗症とは、過剰な発汗により日常生活に大きな影響を与える健康問題です。この症状は、身体の特定の部位から大量の汗が出ることで、個人の生活の質や精神的な健康に悪影響を及ぼします。普段から人より汗が多いと感じ、生活するうえで不便を感じている方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、多汗症の原因や症状について解説し、予防に効果的な対策方法や治療を考えるべき目安などをご紹介します。
◆多汗症とは?

多汗症は、発汗時に通常よりも多くの汗が出る症状で、程度によっては日常生活のさまざまな場面に支障をきたすことがある疾患です。
多汗症には、全身にわたって多量の発汗が見られる「全身性多汗症」と、手のひら、足の裏、脇、顔など特定の部位で多くの発汗が見られる「局所性多汗症」があります。さらに、神経障害、感染症、内分泌代謝異常、精神的緊張などが原因となる「続発性多汗症」と、特定の原因が不明である「原発性多汗症」に分類されます。
◆多汗症の症状
多汗症の症状は、日常生活に支障をきたすほどの過剰な発汗です。人によって程度は異なりますが、重度の場合、汗が手のひらから滴り落ちることもあります。さらに、足や脇の不快な臭い、汗による指先の冷え、手足に水疱(水ぶくれ)ができる、表皮がめくれるといった皮膚のトラブルも引き起こします。多汗症により、患者はさまざまな精神的苦痛を経験し、仕事や勉強に支障をきたすことや、対人関係に影響が及び、生活の質(QOL)が著しく低下することもあるでしょう。
精神的苦痛が大きい場合、うつ病などの精神疾患を併発することもあるため注意が必要です。多汗症の症状は、幼児期から思春期にかけて発症しやすく、10~30代にかけて多く見られる病気です。
◆多汗症のセルフチェック
以下の項目に当てはまる数が多いほど、多汗症の症状レベルが高いといえます。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。治療すべきかの目安は、「汗が原因で生活に支障が出ているかどうか」です。これらの症状に悩まされており、改善したいと考えている場合は皮膚科を受診しましょう。
- 手のひらや足の裏、脇が常に汗で湿っている
- 気温が高い季節でなくてもたくさん汗をかく
- 緊張により多量の汗が出る
- 脇の汗染みが気になり、好きなファッションを選べない
- 汗が原因で1日に何度も着替える
- 手汗で文字がにじむ、スマホが反応しないなど、生活に支障が出る
- 汗をかくことをおそれて仕事や勉強に集中できない
- 日中は大量の汗に悩まされるが、睡眠中は汗をほとんどかかない
- 多汗症の家族歴がある
◆多汗症の原因
多汗症の原因はさまざまにあり、全身性多汗症と局所性多汗症ではそれぞれ原因が異なります。ここでは、多汗症の原因についてご紹介します。
◎全身性多汗症の原因

- 内分泌・代謝性発汗:甲状腺機能亢進症、更年期障害、糖尿病、肥満症など
- 神経障害:パーキンソン病など
- 温熱性発汗:運動、高温の環境、発熱などによる発汗
- 薬剤副作用:向精神薬、睡眠導入薬、非ステロイド抗炎症薬、ステロイド薬などの服用による発汗
- 感染症:結核、敗血症など
- 特発性発汗:原因不明の発汗
◎局所性多汗症の原因

- 精神性発汗:精神的な緊張による発汗(手のひら、足の裏、脇など)
- 神経障害による発汗:胸部交感神経切除後などによる発汗(体幹)
- 味覚性発汗:辛いものなどを食べたとき(顔面)
- その他:皮膚疾患による局所多汗症など
◆多汗症を予防する対策法
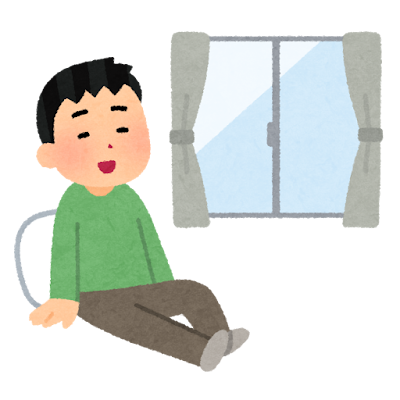
発汗を減らすために、できるだけ強いストレスを避ける生活を心がけることが重要です。ストレスが溜まっていると感じたら、心と体をリラックスさせられる時間を確保して解消しましょう。
辛いものや刺激物、カフェインの摂りすぎも交感神経を優位にするため、できるだけ避けるのが無難です。ほかにも、適度な飲酒用を守ることや喫煙を控えることなど、交感神経を優位にさせないよう心がけることが大切です。睡眠時間を十分とり、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
ただし、これらの対策は神経障害や糖尿病などによる発汗の予防にはなりません。多汗の原因がほかにある場合は、その治療を優先させてください。
***
多汗症は、多くの人々にとって困難な問題ですが、適切な治療と日常生活での対策を講じることで、症状を効果的に管理することができます。自身の体質やライフスタイルに合った方法を見つけることが重要であり、医療専門家のアドバイスを受けることも大切です。多汗症は、治療を受けていない潜在的な患者が多い病気です。ただ人より汗が多いだけと放置せず、多汗症と向き合いながら、快適で充実した生活を送るための一歩を踏み出しましょう。