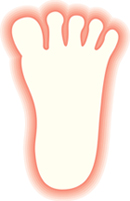|
||||||||
|
|
緊張型頭痛とは | ||||||||||||||||||||||||||
<症状>
<原因>
いずれの場合も、頭のまわりに幾重にもある筋肉が収縮して、頭痛・頭重感を引き起こします。 <特徴>
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
緊張型頭痛を予防するには | ||||||||||||||||||
|
|
|
緊張型頭痛の治療と薬 | ||
|
| 頭痛には、くも膜下出血や脳腫瘍などの病気が原因となり症状として頭痛が起こる「症候性頭痛」と、頭痛それ自体が病気である「慢性頭痛(機能性頭痛)」があります。慢性頭痛には、今回お話した筋肉のこりが原因の「緊張型頭痛」の他、頭の血管の過度の拡張が原因となる「片頭痛」や「群発頭痛」がありますが、どれも医師の治療が必要な“病気”です。「我慢すれば収まる」と無理をせず、早めに診断と治療を受けましょう。 |