
日々の忙しさのなかで、お風呂を沸かして湯船に浸かる時間を確保できず、ついシャワーのみで済ませてしまうことがないでしょうか。実は、湯船に浸かって体を温めると、多くのメリットが期待できます。たまにはゆっくりとお湯に入って、疲れた体と心を休められる時間を作れると理想的です。今回は、お風呂と健康の関係についてお伝えします。
◆湯船に浸かると健康にどんなメリットがある?
毎日の入浴で湯船に浸かると、健康にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まずは、入浴に期待されている効果をご紹介します。
・体が温まり疲れが取れやすくなる
 温かい湯船に全身が浸かると、体が温まって血管が広がり、血行が良くなります。血液には、私たちの体のすみずみまで酸素や栄養を運び、そして二酸化炭素や老廃物を排出する役割があります。血行が良くなると、筋肉の凝りがほぐれ、疲れが取れやすくなるのがメリットです。ほかにも、体を温めることは内臓や自律神経にも良いといわれます。シャワーを浴びる場合と比べて、全身をしっかりと温められるのが大きな違いです。
温かい湯船に全身が浸かると、体が温まって血管が広がり、血行が良くなります。血液には、私たちの体のすみずみまで酸素や栄養を運び、そして二酸化炭素や老廃物を排出する役割があります。血行が良くなると、筋肉の凝りがほぐれ、疲れが取れやすくなるのがメリットです。ほかにも、体を温めることは内臓や自律神経にも良いといわれます。シャワーを浴びる場合と比べて、全身をしっかりと温められるのが大きな違いです。
・水圧によって血行が促される
湯船に浸かると、体が水圧による影響を受けます。こうして全身に圧力がかかると、溜まった血液が押し戻されて流れが促されたり、腹部が縮んで呼吸の回数が増えたりするのがメリットです。適度なしめつけによって、滞りがちな血行が促されます。体へのマッサージ効果が期待できるだけでなく、むくみの解消につながると考えられています。
・全身のリラックスにつながる
水のなかでは「浮力」と呼ばれる作用がはたらき、自然と体が浮いてきます。実はこの浮力は、お風呂で湯船に浸かっているときにもはたらいているのです。浮力があることで、常に体の重みを支えている筋肉や関節をリラックスさせることにつながります。体の重みから解放されて緊張が減るため、体と心をゆったりと休められるのがメリットです。
◆日々の入浴で注意したいポイント
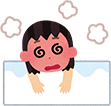 このように多くのメリットが期待できる入浴ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。最後に、湯船に浸かるうえで気をつけておきたいことを解説します。
このように多くのメリットが期待できる入浴ですが、いくつか注意しておきたいポイントもあります。最後に、湯船に浸かるうえで気をつけておきたいことを解説します。
・お湯の温度は40℃程度が目安
体の疲れを取りリラックスするために、お湯の温度は40℃程度を目安にしましょう。お湯の温度が高すぎると、興奮につながる「交感神経」が活発になりやすく、血圧が上がるおそれがあります。42℃以上の熱いお湯での入浴にはリスクがあるためご注意ください。特に冬場は温かいお湯に浸かりたくなりますが、お風呂を沸かすときは適温を守りましょう。
・長風呂をしすぎない
湯船に浸かる時間は、長ければ長いほど良いわけではありません。目安として、入浴時間は40℃程度のお湯の場合で、10~15分に留めましょう。ただし、顔が汗ばんでくるのを感じたら、上記の時間以内であっても湯船から出て休憩を取るようおすすめします。40℃程度のお湯に10~15分浸かると、体温が約1℃上がるといわれます。長風呂には体温が上がりすぎるリスクがあるため注意しましょう。
・アルコールを飲むのは避ける
湯船に浸かると多くの水分が失われます。一般的には、入浴により約800mlの水分が失われるといわれるため、水・イオン飲料・麦茶などで水分補給を行うと良いでしょう。このとき、アルコール飲料を飲むと利尿作用により脱水が起こるおそれがあります。お風呂上がりはお酒を飲むのを避けて、まずはしっかりと水分補給を行ってください。
今回は、お風呂で湯船に浸かるメリットをご紹介しました。入浴時には、可能であればシャワーよりも湯船に浸かって、体を温めるようおすすめします。冷えやすい冬は、ぜひご紹介した入浴のポイントを参考にしてみてください。



 春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。
春夏秋冬、食卓で季節感を楽しめるのが魅力の「旬の食材」。そんな季節の食べ物には、健康や家計にもたくさんのメリットがあるのです。ここでは、3つのポイントでお伝えします。 最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。
最後に、冬に食べ頃を迎える旬の食材をご紹介します。寒い冬を健康に過ごすために、これらの旬の食材を意識して採り入れてみてはいかがでしょうか。



 ・運動不足
・運動不足 また、仕事とプライベートの切り替えは、意識的に行ってください。自宅のなかで仕事をするスペースを決めて、休憩時間や就業後にはその場を離れる方法もあります。就業時間外には、仕事で使うPCや端末を片付けても良いでしょう。オフィスで勤務する場合と同じように、就業時間や休憩時間を守り、こまめな休憩を取ってください。
また、仕事とプライベートの切り替えは、意識的に行ってください。自宅のなかで仕事をするスペースを決めて、休憩時間や就業後にはその場を離れる方法もあります。就業時間外には、仕事で使うPCや端末を片付けても良いでしょう。オフィスで勤務する場合と同じように、就業時間や休憩時間を守り、こまめな休憩を取ってください。 さらには、社内のコミュニケーションを充実させることも大切です。チャットやビデオ通話は業務連絡での利用に限定せず、雑談も交えながら気軽に交流できる機会を増やします。同僚や部下の様子がおかしいと思われたら、必要に応じて声がけを行ってください。プライベートでも、親しい方とコミュニケーションを取る機会を設けましょう。
さらには、社内のコミュニケーションを充実させることも大切です。チャットやビデオ通話は業務連絡での利用に限定せず、雑談も交えながら気軽に交流できる機会を増やします。同僚や部下の様子がおかしいと思われたら、必要に応じて声がけを行ってください。プライベートでも、親しい方とコミュニケーションを取る機会を設けましょう。




 風邪の原因はウイルスや細菌による感染です。ウイルスや細菌は、私たちの手に付着し、そこから目や鼻などの粘膜を通して感染します。また、咳やくしゃみなどの飛沫に含まれるウイルスや細菌が、のどを通して感染する可能性もあります。手やのどに付いたウイルスや細菌を洗い流すためには、手洗いとうがいが有効です。日常生活では手洗いとうがいを実施し、ウイルスや細菌が体に侵入するのを防ぎましょう。
風邪の原因はウイルスや細菌による感染です。ウイルスや細菌は、私たちの手に付着し、そこから目や鼻などの粘膜を通して感染します。また、咳やくしゃみなどの飛沫に含まれるウイルスや細菌が、のどを通して感染する可能性もあります。手やのどに付いたウイルスや細菌を洗い流すためには、手洗いとうがいが有効です。日常生活では手洗いとうがいを実施し、ウイルスや細菌が体に侵入するのを防ぎましょう。 私たちの体にある粘膜には、体の外からのウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割があります。粘膜のはたらきを保つには、体内に十分な量の水分が必要です。ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、排出しやすくするために、こまめな水分補給を行いましょう。また、空気が感染すると粘膜も乾燥しやすくなります。風邪予防に適した湿度は60~80%といわれます。乾燥しやすい秋~冬は、加湿器を使用してお部屋の湿度を高めに保ちましょう。
私たちの体にある粘膜には、体の外からのウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割があります。粘膜のはたらきを保つには、体内に十分な量の水分が必要です。ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、排出しやすくするために、こまめな水分補給を行いましょう。また、空気が感染すると粘膜も乾燥しやすくなります。風邪予防に適した湿度は60~80%といわれます。乾燥しやすい秋~冬は、加湿器を使用してお部屋の湿度を高めに保ちましょう。 栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動といった規則正しい生活は、風邪予防の基本といえます。特に、疲労がたまると風邪をひきやすくなります。風邪が流行る時期には、普段から体力を保つよう心がけてください。また、風邪予防では体を温めることも大切です。ウイルスや細菌は、低温低湿の環境を好みます。衣服や暖房により保温を行い、体から熱が奪われすぎないよう調整しましょう。
栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動といった規則正しい生活は、風邪予防の基本といえます。特に、疲労がたまると風邪をひきやすくなります。風邪が流行る時期には、普段から体力を保つよう心がけてください。また、風邪予防では体を温めることも大切です。ウイルスや細菌は、低温低湿の環境を好みます。衣服や暖房により保温を行い、体から熱が奪われすぎないよう調整しましょう。
 熱中症が引き起こされる仕組みをお伝えしました。それでは、熱中症を防ぐにはどんなポイントに気をつければよいのでしょうか? まず、大切なのはこまめな水分補給と、適度な塩分補給を行うことです。気温の高い屋外にいるときは、のどが渇いたと感じなくても、水分を摂るよう心がけてください。汗をたくさんかいたら、適量の塩分を摂ります。
熱中症が引き起こされる仕組みをお伝えしました。それでは、熱中症を防ぐにはどんなポイントに気をつければよいのでしょうか? まず、大切なのはこまめな水分補給と、適度な塩分補給を行うことです。気温の高い屋外にいるときは、のどが渇いたと感じなくても、水分を摂るよう心がけてください。汗をたくさんかいたら、適量の塩分を摂ります。
 熱中症を防ぐためには、外出時に日差しを防いだり、体を冷やしたりするグッズを使う方法もあります。日差しを防ぐグッズとして挙げられるのは、帽子や日傘などです。帽子や日傘には、頭や体が直射日光に当たるのを防ぎます。直射日光を避けるだけでも温度に差が出るため、ぜひご活用ください。また、体を冷やすグッズとして、保冷剤や冷却スカーフなどが挙げられます。太い血管が通る首筋を冷やすと、全身を効率よく冷やすことにつながるため、身につけて暑さの対策を行いましょう。
熱中症を防ぐためには、外出時に日差しを防いだり、体を冷やしたりするグッズを使う方法もあります。日差しを防ぐグッズとして挙げられるのは、帽子や日傘などです。帽子や日傘には、頭や体が直射日光に当たるのを防ぎます。直射日光を避けるだけでも温度に差が出るため、ぜひご活用ください。また、体を冷やすグッズとして、保冷剤や冷却スカーフなどが挙げられます。太い血管が通る首筋を冷やすと、全身を効率よく冷やすことにつながるため、身につけて暑さの対策を行いましょう。
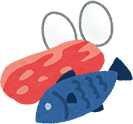 食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。
食中毒のピークは8~9月であり、大半は初夏から初秋にかけて発生しています。この時期によくある食中毒は、上述したO-157、カンピロバクター、サルモネラによる事例です。 ・つけない
・つけない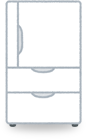 ・増やさない
・増やさない
 家庭向けの体温計には種類があります。一般的によく知られているのは、脇の下で体温を測る「脇式体温計」です。脇式体温計は、細長い棒状をした体温計の先端を脇へ当て、腕と体側で挟むように使います。体温を測り終えるまでにやや時間がかかるのが特徴です。ほかにも、耳の穴のなかで体温を測る「耳式体温計」もあります。耳式体温計は、本体を手で持ち、センサー部分を耳に入れて使います。たった数秒で体温を測れるのが特徴で、子どもの体温を測定するときにも役立ちます。ただし、値段は脇式体温計よりもやや高額です。
家庭向けの体温計には種類があります。一般的によく知られているのは、脇の下で体温を測る「脇式体温計」です。脇式体温計は、細長い棒状をした体温計の先端を脇へ当て、腕と体側で挟むように使います。体温を測り終えるまでにやや時間がかかるのが特徴です。ほかにも、耳の穴のなかで体温を測る「耳式体温計」もあります。耳式体温計は、本体を手で持ち、センサー部分を耳に入れて使います。たった数秒で体温を測れるのが特徴で、子どもの体温を測定するときにも役立ちます。ただし、値段は脇式体温計よりもやや高額です。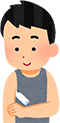 多くの家庭に常備されている脇式体温計を使った場合の、体温の測り方をご紹介します。まずは、体温計の電源を入れましょう。体温計が起動し、検温の準備ができたら、先端にあるセンサー部分を斜め下方向から脇の中心へ当てます。このとき、体温計のディスプレイが体の内側を向くようにしつつ、もっとも温度が高い脇の中心に挟むのが大切です。体温計の角度は30~45度を目安にしましょう。しっかりと腕を締めて、反対の手で軽く押さえた状態で検温が完了するまで待ちます。体温計の先端が脇からはみ出さないようご注意ください。
多くの家庭に常備されている脇式体温計を使った場合の、体温の測り方をご紹介します。まずは、体温計の電源を入れましょう。体温計が起動し、検温の準備ができたら、先端にあるセンサー部分を斜め下方向から脇の中心へ当てます。このとき、体温計のディスプレイが体の内側を向くようにしつつ、もっとも温度が高い脇の中心に挟むのが大切です。体温計の角度は30~45度を目安にしましょう。しっかりと腕を締めて、反対の手で軽く押さえた状態で検温が完了するまで待ちます。体温計の先端が脇からはみ出さないようご注意ください。
 夏バテになると、主にだるさ・疲労感・食欲不振などの症状がみられます。これらは夏バテの症状の代表例です。体がだるいと感じる日が続いたり、休んでも疲れが取れにくかったりしたら、夏バテによる不調を疑ってみましょう。また、食欲がわかず食事を摂れないと、栄養不足につながるおそれがあります。消化器の調子もよくご確認ください。
夏バテになると、主にだるさ・疲労感・食欲不振などの症状がみられます。これらは夏バテの症状の代表例です。体がだるいと感じる日が続いたり、休んでも疲れが取れにくかったりしたら、夏バテによる不調を疑ってみましょう。また、食欲がわかず食事を摂れないと、栄養不足につながるおそれがあります。消化器の調子もよくご確認ください。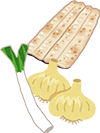 ・疲労回復につながる栄養を摂る
・疲労回復につながる栄養を摂る 暑さで眠れないときや、眠りが浅いときは、意識して普段よりも眠りやすい状態を整えましょう。就寝前30~60分に入浴し、ぬるめの温度の浴槽に浸かります。どうしても暑さが気になるときは、入眠時に氷枕や冷房を活用しても良いでしょう。十分な睡眠で疲労を回復して、疲れを残さない習慣をつくれると理想です。
暑さで眠れないときや、眠りが浅いときは、意識して普段よりも眠りやすい状態を整えましょう。就寝前30~60分に入浴し、ぬるめの温度の浴槽に浸かります。どうしても暑さが気になるときは、入眠時に氷枕や冷房を活用しても良いでしょう。十分な睡眠で疲労を回復して、疲れを残さない習慣をつくれると理想です。