
腸内環境は私たちの健康と深いかかわりがあります。消化や吸収のほかにも、多くの大切な機能がある腸。普段の生活習慣や食習慣によって、腸内環境が乱れないように過ごしましょう。ここでは、腸の役割やお腹を健やかに整えるポイントをお伝えしていきます。毎日の健康維持にお役立てください。
◆腸内環境とは?どうして整える必要があるの?
私たちの体にある腸が、食べ物の消化と吸収にかかわる大切なはたらきをしていることは、多くの方がご存知でしょう。しかし、腸の役割はそれだけではありません。
実は、腸は自律神経と深いかかわりのある器官です。自律神経には、心身の緊張とリラックスを切り替え、コントロールする役割があります。腸は神経細胞が多い器官であり、私たちの感情とも密接に関係するといわれます。また、人間の体内にある免疫細胞のうち、5割以上が腸に存在するともいわれ、体を守るはたらきを担っているのです。
このように、多くの大切な機能を備えている腸。ところが、そんな腸のはたらきは、生活習慣の乱れにより低下してしまうことがあります。腸内環境が悪化すると、便秘や下痢のほか、肥満や肌荒れなどさまざまな不調につながることも。腸内環境を健やかに保つことは、日々の健康維持にも欠かせません。
◆腸内フローラのはたらき
人間の腸内には、1,000兆個を超える細菌が住んでいるといわれます。これらの大量の細菌が住む様子が、まるで花畑のように見えることから、腸内細菌は「腸内フローラ」とも呼ばれます。「フローラ(flora)」とは、英語で花畑を意味する言葉です。
腸内フローラには、体に良いはたらきをする「善玉菌」、悪いはたらきをする「悪玉菌」、どちらでもない「日和見菌(ひよりみきん)」という種類があります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のうち、数が多く優勢なほうの味方となる細菌です。
バランスの良好な腸内フローラは、食べ物を栄養のある物質へと作り変えたり、体を守ったりするはたらきがあります。一方で、悪玉菌が増えて腸内環境が悪化すると、お腹の調子が悪くなり便秘や下痢につながります。
健康のためには、腸内フローラを善玉菌が多い状態に保ち、お腹の調子を整えることが大切です。ここからは、腸内環境を整える生活習慣や食生活についてご紹介します。
◆腸内環境を整える生活習慣
 腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。
腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。
◆腸内環境を整える食生活
 食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。
食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。
今回は、私たちの腸内環境を整える大切さや、腸内フローラのはたらきについてご紹介しました。自律神経が自然と切り替わる生活習慣や、善玉菌および善玉菌のエサを取り入れた食生活で、腸内を健康的に保ちましょう。

脱水といえば夏の健康被害というイメージがないでしょうか? 実は、寒い季節にも脱水は起こります。健康維持や風邪予防につなげるために、こまめな水分補給を心がけましょう。
◆水分補給は寒い冬にも必要です
まだ寒い日が続いています。主に手足や体の冷えが気になるこの時期、つい忘れがちになるのが水分補給です。暑さからたくさんの汗をかく夏には、多くの方が脱水予防に努めているのではないでしょうか。その一方で、冬の脱水は見落とされやすいといえます。
たとえ寒くて汗をかかないとしても、冬場は排泄にともない水分が失われています。特に、暑さが去ってから水を飲む量が極端に少なくなった方は要注意。引き続き積極的に水分補給を行ってください。ここからは、冬の水分補給の重要性についてお伝えしていきます。
◆寒い時期に起こる脱水とは?
 もともと空気が乾燥しやすい冬。さらには、使用している暖房器具の影響でさらに湿度が低くなることがあります。このような環境で生活を続けていると、体の表面にある皮膚や粘膜、そして呼気から水分が失われてしまうのです。
もともと空気が乾燥しやすい冬。さらには、使用している暖房器具の影響でさらに湿度が低くなることがあります。このような環境で生活を続けていると、体の表面にある皮膚や粘膜、そして呼気から水分が失われてしまうのです。
また、夏と比べて自然と水分を摂取しにくいのも、冬に脱水が起こる要因となります。寒いと喉が渇いたのを実感しにくく、水分補給を怠りやすいためです。ほとんど汗をかかないため、あまり水を飲みたくないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
それだけでなく、冬に流行する風邪や感染症で体調を崩して下痢・嘔吐・発熱などの症状が出た場合も、多くの水分が失われます。このように、体から失われる水分が多いにもかかわらず水分補給を行わないと、脱水が起こるおそれがあります。
水分が不足すると、血行が悪くなり冷えにつながったり、血液の粘度が高まり脳卒中や心筋梗塞といった病気のリスクが高くなったりすることも。寒い時期でも体が必要とする水分を積極的に摂り入れて、健康的な生活を続けたいですね。
◆風邪予防にも水分補給が大切
冬場のこまめな水分補給が推奨されるのには、実はほかにも理由があります。それは、風邪予防とかかわりがあるためです。ウイルスが私たちの喉の粘膜に付着すると、風邪を引き起こします。このとき、水を飲むことでウイルスが胃に流れると、風邪予防につながります。
人間の胃袋には、強力な酸性の胃酸があります。胃に流れたウイルスは、その後に胃酸で死滅します。こまめに水分を摂れば、その分ウイルスが喉の粘膜に付着したままになりにくいというわけです。目安としては、30分間に1回の頻度で一口の水を飲みましょう。
また、気道の壁にある「線毛」は、喉から入った異物が肺に侵入するのを防ぐ役割があります。この線毛の弱点は乾燥です。乾燥により線毛が本来の働きをしにくくなると、ウイルスが体内に入り込みやすくなってしまいます。
線毛の乾燥を防ぐためには、マスクをしてのどの乾燥を防ぎ、こまめな水分補給を行うことが大切です。風邪や感染症が流行する冬は、日々の健康維持のために水を飲みましょう。
◆冬におすすめしたい水の飲み方
 寒い冬には、冷たい水を飲みにくいといえます。そのため、水分補給では温めた水である「白湯(さゆ)」を摂るのがおすすめです。お湯を沸かしたり、高温の水が出るウォーターサーバーを利用したり、温かくて飲みやすい温度の水を用意すると良いでしょう。
寒い冬には、冷たい水を飲みにくいといえます。そのため、水分補給では温めた水である「白湯(さゆ)」を摂るのがおすすめです。お湯を沸かしたり、高温の水が出るウォーターサーバーを利用したり、温かくて飲みやすい温度の水を用意すると良いでしょう。
1日に摂取する理想的な水の量は2.5Lといわれます。このうち、飲み水から取り入れる分は2Lが目安です。一度に2L近くの水を摂るのは難しいため、コップ1杯の水をこまめに摂るイメージをしましょう。夏場と同様に、意識して水分補給を行ってください。
冬におろそかになりがちな水分補給。水不足は冷えや病気のリスクにかかわるため、寒い日には温かい水を飲んで健康にお過ごしください。

気温が低く、乾燥しがちな冬場。この時期は、皮膚の健康にも気を配りましょう。特に、手肌に起こりやすいひび・あかぎれは、悪化すると痛みをともない、日常生活にも支障をきたすことがあります。こまめな保湿で予防をして、健やかに保ちましょう。
◆痛みにもつながるひび・あかぎれの症状
湿度が低い冬は、皮膚が乾燥しやすくなります。そこで注意しておきたいのが、手肌によく起こる「ひび」や「あかぎれ」です。ひびとは、肌の表面に亀裂が生じた状態を指します。それに対してあかぎれは、上記のひびの症状がさらに悪化し、患部の亀裂から血が滲んできたり、割れにともない痛みを感じたりする状態を指します。
ひび・あかぎれが起こりやすいのは、主に手の甲・手の指・かかとなどの部位です。特に手に生じた場合には、日常生活での手洗いや入浴、皿洗いや洗濯などの家事を行うとき、支障をきたすおそれがあります。乾燥しやすい冬は、ひびやあかぎれの予防につとめるとともに、できるだけ症状を悪化させないよう対策を行いましょう。
◆冬場のひび・あかぎれの主な原因
手肌に生じるひび・あかぎれの主な原因は、気温の低下や空気の乾燥だと考えられています。冬場に気温が低下すると、皮膚は汗をかきにくく、皮脂の分泌量が少なくなります。そのうえ、乾燥した空気による影響を受け、皮膚の水分が不足しがちになるのです。こうして皮膚が乾燥すると、関節の動きで引っ張られたときや、体重がかかったときなどに耐えられず、表面に亀裂が生じます。ひびやあかぎれはこのようなメカニズムで起こります。
◆ひび・あかぎれを予防するには?
 冬場に起こりやすいひび・あかぎれを予防するためのポイントをご紹介します。
冬場に起こりやすいひび・あかぎれを予防するためのポイントをご紹介します。
・こまめに保湿を行う
クリームを付けてこまめに手肌の保湿を行いましょう。市販のクリームには、セラミド・ワセリン・ヘパリン類似物質などの保湿成分が配合されています。手肌が水で濡れた後にすみやかに保湿できるよう、キッチン・洗面所・浴室にクリームを用意しておくと安心です。
・水仕事はゴム手袋を付けて行う
 皿洗いや洗濯などの家事では、洗浄力の強い洗剤や水が手肌に直接触れないよう、ゴム手袋を付けることをおすすめします。ほかにも、手の油分を奪ったり刺激を与えたりする習慣は乾燥につながりやすいためご注意ください。
皿洗いや洗濯などの家事では、洗浄力の強い洗剤や水が手肌に直接触れないよう、ゴム手袋を付けることをおすすめします。ほかにも、手の油分を奪ったり刺激を与えたりする習慣は乾燥につながりやすいためご注意ください。
・手洗いの方法を見直す
手洗いにお湯を使うと油分が奪われやすいため、水温は高すぎない温度に設定します。タオルを使うときはゴシゴシと手をこするのではなく、優しく押さえて水分を吸い取りましょう。濡れた手から水分が蒸発すると乾燥につながるため、すみやかに拭き取るのが理想です。
◆ひび・あかぎれができたときの対策
もしもひび・あかぎれができてしまったときは、以下の対策を参考にしてみてください。
・幹部を清潔に保ち保湿する
すでにひび・あかぎれができてしまったときも、基本的には手肌の保湿を行います。患部の悪化を防ぐために、常に清潔に保ちましょう。市販されているひび・あかぎれ用の医薬品を使用する方法もあります。患部に痛みが生じているときは、保湿成分が配合され、かつ皮膚への刺激が少ないクリームや軟膏をお選びください。
・医療機関を受診する
ひびやあかぎれの症状が悪化したときや、市販の医薬品を使っても状況が変わらなかったときは、皮膚科の医療機関を受診しましょう。患部が感染したり、別の皮膚炎にかかっていたりする可能性も考えられます。医師の指示にしたがって処方された医薬品を使用するとともに、栄養バランスの良い食事をとり、十分な睡眠時間を確保してください。
冬場の冷えや乾燥が原因で起こりやすいひびやあかぎれ。日常生活に支障をきたすことがあるため、手肌は十分に保湿するとともに、刺激を避けて予防につとめましょう。

気温が下がり肌寒くなると、温かいものを食べたくなりますよね。そんな冬の食卓に欠かせないのが生姜です。スープや鍋料理をはじめとして、美味しく食べられるレシピがたくさんあります。今回は、美味しくてかつたくさんの健康効果が期待されている生姜のパワーについてお伝えしていきます。
◆冬の冷え対策には生姜がおすすめ
幅広い料理に使える生姜は、毎日の食卓に並ぶことの多い、身近な食材のひとつです。ピリッとした独特の辛味があり、食べると体がポカポカと温まる感じがあることから、冬が近づくと生姜を食べたくなる方も多いのではないでしょうか。
そんな生姜には、気温の低い時期に嬉しい健康効果のほかに、ヘルスケアに役立つさまざまな効果が期待されています。食物繊維が豊富に含まれ、低カロリーな食材であるため、肥満が気になる方にもおすすめです。ぜひ冬の食事に取り入れましょう。
◆人類と生姜の歴史
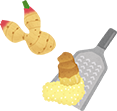
古くから私たちの暮らしとともにあった生姜。人類と生姜の歴史の始まりは、なんと人類が狩猟生活をしていた頃にまで遡ります。生姜は当時から、肉や魚の防腐剤や調味料として用いられていたと考えられているのです。
日本では、中国を経由して生姜が伝わったといわれており、古くから医薬品として暮らしに役立てられてきました。中華料理における生姜といえば、ネギやニンニクと並んで重要な食材のひとつ。また、多くの漢方薬にも生姜が配合されています。
現在は食材として一般家庭の食卓に並ぶイメージのある生姜ですが、かつては医薬品として重宝されていた歴史があります。気軽に購入しやすい食材でありながら、豊富な健康効果が期待されており、日々の健康維持におすすめです。
◆生姜に期待される冬の健康効果
生姜の味わいの特徴でもあるピリッとした辛味は、「ジンゲロール」「ショウガオール」という2つの成分から生じています。
このうちジンゲロールは、特に生の生姜に多く含まれる成分です。強い殺菌力を持つといわれ、風邪予防に役立ちます。ほかの食材の生臭さを消したり、食中毒を予防したりするために生姜が使われるのはこのためです。
ジンゲロールを加熱すると、ショウガオールに変化します。ショウガオールには血行促進作用が期待されています。さらには、血液の流れが良くなることで鎮痛作用も期待されるため、風邪や冷えによる関節の痛みにもおすすめの食材です。
生姜を食べたときにポカポカと体が温まる感じがするのは、これらの成分の働きによるもの。スープや鍋料理など、冬の料理を美味しく引き立ててくれる生姜ですが、冷えや風邪の対策としても役立てられます。
◆冷え対策だけじゃない!生姜のパワー
 冬に嬉しい健康効果が期待できる生姜ですが、食べることでほかにもたくさんのメリットが得られます。古くから人類とともにあった生姜のパワーを、ぜひ理解しておきましょう。
冬に嬉しい健康効果が期待できる生姜ですが、食べることでほかにもたくさんのメリットが得られます。古くから人類とともにあった生姜のパワーを、ぜひ理解しておきましょう。
まず、生姜に含まれるジンゲロールやショウガオールは、消化吸収を助けるといわれています。胃液の分泌を促すことで、胃腸の健康にも役立てられます。食べたあとの胃もたれが気になる方も、生姜のパワーをぜひお役立てください。
また、生姜の成分により血流が促されると、代謝がアップすると考えられています。豊富に含まれる食物繊維には、腸内での糖分や脂肪の吸収を抑える働きが期待されています。肥満でお悩みの方は、ダイエット中のおやつを生姜に置き換えてみてはいかがでしょうか?
血行促進の効果が期待されている生姜は、肌荒れを防ぐともいわれています。血の巡りが良くなると、お肌の新陳代謝も促されるため、美肌を目指す方に嬉しい効果がたくさん。食物繊維によるお通じの改善も含めて、女性におすすめの食材といえるでしょう。
このように、生姜には冷え対策のほかにもさまざまな健康効果が期待されています。寒い季節に美味しく食べられて、さらにヘルスケアにもおすすめの一石二鳥の食材です。生姜を日々の健康維持にお役立てください。

冬場にご自宅の寒暖差が気になることがないでしょうか?
リビングから廊下へ出たとき、浴室から脱衣所へ出たときなどに強い冷えを感じるときは、ヒートショック対策を始めましょう。今回は、寒い季節に気をつけたいヒートショックのリスクと対策をご紹介します。
◆ヒートショックとは?
冬場によく起こる健康被害としてよく話題にのぼる「ヒートショック」。そんなヒートショックとは、急激な温度差が原因で血圧に大きな変動が生じ、さまざまな病気のリスクが高まることを指します。例年、秋頃から被害が増え始め、ピークは1月頃。風呂場やトイレでの事故が多く、特に65歳以上の高齢者や生活習慣病患者の方は注意が必要です。
ヒートショックにより血圧が大きく変動すると、心筋梗塞・脳卒中・不整脈などを引き起こすリスクが高まります。入浴中にヒートショックが起こった場合には、浴槽内で倒れることによる溺死の危険性も無視できません。なお、年間の入浴中の死亡者数は全国で約14,000人といわれていますが、このうち大部分はヒートショックが原因だと考えられています。
このように、ヒートショックは急死につながるケースもあり、決して軽視できない症状です。被害が起こりやすい場面を理解するとともに、秋から冬にかけて対策を始めましょう。
◆ヒートショックが起こりやすい場面
ヒートショックによる事故が起こりやすい場所として、主に浴室・脱衣所・トイレが挙げられます。たとえば、温かい居間から寒い脱衣所へ移動し、寒い脱衣所から浴室へ移動し、熱い湯船に浸かるような場面はその一例です。急激な温度差で血圧が上下し、ヒートショックを起こす危険性があります。気温の低いトイレでも同様のことが起こりえます。
さらに、ヒートショックは浴室やトイレ以外で起こることもあるため、注意しておきましょう。たとえば、温かい居間から寒い廊下に移動したときに血圧が上下してしまうケースも珍しくありません。冬場は、暖房を入れた部屋と入れない部屋とで10度以上の温度差が生じることもあり、身近な場所にヒートショックの危険が潜んでいるといえます。
◆今からできるヒートショックの対策
 ヒートショックによる健康被害や死亡事故を防ぐために、今からできる対策をご紹介します。気温が下がり始めたら意識的に取り入れてみてください。
ヒートショックによる健康被害や死亡事故を防ぐために、今からできる対策をご紹介します。気温が下がり始めたら意識的に取り入れてみてください。
・脱衣所に暖房器具を設置する
浴室と脱衣所に温度差があるときは、脱衣所に暖房器具を設置して、部屋と部屋の温度差をできるだけ少なくすると良いでしょう。あるいは、浴室の扉や浴槽の蓋を開けておくことで、脱衣所との温度差を和らげる方法もあります。脱衣所だけでなく浴室も冷える場合には、シャワーでお湯はりをして、浴室全体を温めるのも効果的です。
・浴槽に入る前に手足を温める
 浴室に入ったとき、いきなり浴槽に入り全身を温めると、心臓に負担をかけやすくなります。まずは心臓から遠い手足にお湯をかけて、部分的に温めてから少しずつ体を慣らしましょう。また、お湯の温度が高すぎるのも好ましくありません。温度は38~40度を目安にして、長時間浴槽に浸かりすぎないようお気をつけください。
浴室に入ったとき、いきなり浴槽に入り全身を温めると、心臓に負担をかけやすくなります。まずは心臓から遠い手足にお湯をかけて、部分的に温めてから少しずつ体を慣らしましょう。また、お湯の温度が高すぎるのも好ましくありません。温度は38~40度を目安にして、長時間浴槽に浸かりすぎないようお気をつけください。
・入浴前の食事や飲酒を控える
食事を摂った直後は消化器官に血液が集まるため、血圧が下がりやすくなります。また、飲酒をすると血管が拡張して血圧が下がりやすく、かつ体の反応が鈍くなります。このような状態での入浴は体への負担が大きく、血圧の変動によるヒートショックのリスクが高まるため注意が必要です。食事や飲酒は入浴後にするよう心がけましょう。
意外と身近にある健康被害であるヒートショック。特に高齢者や生活習慣病患者の方は、入浴前にご家族に声がけを行うなど、万が一の事態に備えておくことが大切です。冬場によくある危険についてよく理解し、日々健康にお過ごしください。

家庭用として販売される商品が増え、身近な存在になった「体組成計」。一般的な体重計と比べて、機能にはどのような違いがあるのでしょうか。また、健康管理においてどのようなメリットがあるのでしょうか。今回は、体組成計についてお伝えしていきます。
◆体組成計とは?
体重を量ることで日々の健康管理に役立てられる体重計。それに対して「体組成計(たいそせいけい)」は、体脂肪や筋肉量といった体の内側の情報がわかるのが特徴です。そもそも「体組成」とは、人間の体を構成する水分・筋肉・脂肪・骨などの組織のことを指します。体組成計では、体に非常に弱い電流を流すことで、体組成の状態を推定しているのです。
◆体組成計の種類
近年では、家庭用に体重計と体組成計の両方の機能を兼ね備えた「体重体組成計」が発売されています。体組成を計測する方法は、主に2種類あります。ひとつは、体重計と同様に機器の上に乗り、両足から計測する方法。もうひとつは、両足で機器の上に乗るとともに両手でグリップを握り、両手両足から計測する方法です。
このうち、より安定して数値を計測しやすいのは、両手両足から計測する方法だといわれます。その理由は、両足から測定する方法の場合は、体内の水分量の変動により数値が影響を受けやすいためです。数値を安定して測るために、毎日同じ時刻に測定する必要があります。また、両手両足から測定すると、体の部位別の細かい数値まで割り出せます。
◆体組成計のメリット
 日頃の体重計を使った健康管理に加えて、体組成計を取り入れると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。まず挙げられるのは、皮下脂肪や内臓脂肪の量を測定できることです。体組成計を使うと、体脂肪率がわかるだけでなく、その脂肪が皮下脂肪なのか内臓脂肪なのかをチェックすることができます。
日頃の体重計を使った健康管理に加えて、体組成計を取り入れると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。まず挙げられるのは、皮下脂肪や内臓脂肪の量を測定できることです。体組成計を使うと、体脂肪率がわかるだけでなく、その脂肪が皮下脂肪なのか内臓脂肪なのかをチェックすることができます。
皮下脂肪と内臓脂肪は、どちらも脂肪ですが、蓄積する場所が異なります。皮下脂肪が皮膚と筋肉の間に蓄積するのに対して、内臓脂肪が蓄積するのは内蔵の周辺です。特に、内臓脂肪は増えすぎると健康リスクが高まりやすいといわれます。このように、体組成計で自分の体のバランスを知ると、生活習慣の改善につなげやすくなるでしょう。
また、一見すると肥満ではないように見えるにもかかわらず、実は体脂肪率が高い「隠れ肥満」と呼ばれる状態もあります。隠れ肥満は、体重や体格から肥満を判断するのが難しいため、肥満の発見が遅れやすく危険視されています。体組成計で体脂肪の状態をチェックし、脂肪と筋肉の量を調整する健康的なダイエットにお役立てください。
◆内臓脂肪型肥満のリスク
肥満が多くの健康リスクをもたらすことは、今や幅広く知られています。特に、内臓脂肪が多い傾向にある肥満は「内臓脂肪型肥満」と呼ばれ、健康リスクが高いため注意が必要です。
 内臓脂肪が増えると、血液中の脂質が増え、血圧が上昇し、インスリンの働きが悪くなります。これらの要因は、脂質異常症・糖尿病・高血圧症などの生活習慣病につながると考えられています。また、複数の症状が組み合わさることで、メタボリックシンドロームをまねくリスクがあるのも知っておきたいポイントです。
内臓脂肪が増えると、血液中の脂質が増え、血圧が上昇し、インスリンの働きが悪くなります。これらの要因は、脂質異常症・糖尿病・高血圧症などの生活習慣病につながると考えられています。また、複数の症状が組み合わさることで、メタボリックシンドロームをまねくリスクがあるのも知っておきたいポイントです。
生活習慣病の中には、重症化すると命にかかわる症状もあります。これらのリスクを予防するためには、日々の生活習慣の改善が欠かせません。食生活や運動習慣を見直すとき、体組成計をはじめとした機器を活用して、適切に健康管理を続けましょう。
体組成計の特徴や活用法についてご紹介しました。健康管理はモチベーションを保つのが難しく、お悩みの方も多いのではないでしょうか。そんなときは体組成計による体のチェックを毎日の習慣にすることで、健康的なダイエットの指針としてみましょう。自分なりに健康管理をするために、ぜひさまざまな工夫を取り入れてみてください。

きのこの中には秋に旬を迎えるものが多くあります。たとえば、しいたけ・しめじ・まいたけ・まつたけなどはその一例です。今回は、きのこに期待されている健康効果や、きのこと組み合わせて食べたい旬の食材についてご紹介します。ヘルシーな食材であるきのこを、日々の健康維持にお役立てください。
◆食欲の秋はきのこの季節
夏の暑さが少しずつ落ち着き、涼しく過ごしやすい気候に変わる秋。そんな秋には、旬の食べ物がたくさんあります。中でも健康のために注目したいのが「きのこ類」です。きのこはミネラルやビタミンといった栄養素のほか、食物繊維がたっぷり含まれ、さらにはカロリーが低い食材として知られています。きのこが食べごろになったら、健康のために意識して毎日の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか?
◆きのこに期待される健康効果

秋の季節に採れる旬の食べ物のきのこには、さまざまな健康効果が期待されています。ここでは、きのこに期待される健康効果の一例をご紹介します。
・免疫力アップ
栄養が豊富に含まれるきのこを食べると、風邪の予防に役立つビタミンを摂取できます。免疫力のアップにかかわる「ビタミンD」のほか、粘膜を強化するといわれる「ビタミンB2」や「ビタミンB6」も含まれているため、風邪をひきやすい季節に摂取すると好ましい食材です。また、きのこには「βグルカン」と呼ばれる食物繊維が含まれています。βグルカンは人間の腸内で働き免疫力を高める働きをするといわれ、寒い時期の体調管理に役立てられます。きのこを食べて風邪予防につなげましょう。
・美容やダイエットに
きのこには、美容にうれしいビタミンが含まれています。皮膚や髪の再生にかかわる「ビタミンB2」や、血行の改善にかかわる「ビタミンB3」などを摂取でき、肌のターンオーバーを整える美容効果が期待されています。また、きのこは食物繊維が豊富で、かつカロリーが低いのも注目したいポイントです。噛みごたえがあるため満腹感を得られやすく、たくさん食べても摂取カロリーが過剰になる心配がありません。それだけでなく、食物繊維がダイエット中の肥満を防ぐ働きをしてくれるのも魅力です。
・冷え対策
寒い季節には手足の末端をはじめとして、体が冷えやすくなります。そんなときは、きのこを食べて冷え対策をしましょう。きのこに含まれる「葉酸」は、血液中の赤血球の生成とかかわりがあるといわれます。また、「ビタミンB3」は血の巡りを良くするといわれ、冷えやすい体を温めることにつながります。これらのビタミンB群は、体温を上げて代謝をアップさせる効果が期待されており、秋から冬にかけて積極的に摂りたい栄養素だといえるでしょう。冷えが気になる方にもきのこがおすすめです。
◆きのこと合わせて食べたい秋の味覚
 秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
また、秋になるとナスが美味しくなるといわれます。ナスは大部分が水分でできている野菜であり、涼しい季節には加熱調理するのがおすすめです。油と一緒に摂ることで、血液中のコレステロールを抑えるといわれています。一方で、ビタミンが少なめであるため、きのこと一緒に調理すると良いでしょう。
きのこはビタミンをはじめとした栄養や食物繊維が豊富に含まれる、低カロリーでヘルシーな食べ物です。秋に旬を迎えるきのこが多くあるため、ぜひさまざまな秋の味覚と組み合わせて、毎日の食事に取り入れてみてください。

健康的な食習慣の一環として、食事の内容だけでなく、食べ方にも気を使ってみましょう。早食いが習慣になっていたり、ごはんやパンなどの炭水化物から食べ始めたり、深夜に量の多い食事を摂っていたりする方は、特にお気をつけください。
今回は、太りにくい食べ方についてご紹介します。さまざまな病気につながるおそれのある肥満を予防するためにも、ご紹介する内容をぜひ参考にしてみてください。
◆食べ方を改善して太りにくい体に
日頃の食生活で食事の内容に気を使っている方も、「食べ方」にはほとんど注意を払っていないかもしれません。実は、食事を摂るときにいくつかのポイントに気をつけるだけで、より健康的な食習慣につなげられる可能性があるのです。
肥満は健康に悪影響を与えると考えられています。たとえば、過度の肥満状態が続くことで、特定の病気のリスクにつながることがあります。糖尿病や高脂血症などはその一例です。ほかにも、肥満による睡眠中の呼吸障害が懸念されるなど、命にかかわるケースも見受けられます。肥満を防ぐためにも、日頃の食習慣を見直してみましょう。
(1)よく噛んでゆっくりと食べよう
太りにくい食べ方の基本は、口に入れた食べ物よく噛んで、ゆっくりと時間をかけて食事をすることです。目安としては、一口あたり30回以上噛むように意識してみてください。このようによく噛むことで、食べ物が細かくなったり消化酵素を含む唾液がよく出たりして、体内で食べ物を消化しやすくなります。
また、食事にゆっくりと時間をかけることで、満腹中枢と呼ばれる脳の一部が刺激を受けて、食べ過ぎを防ぎやすくなると考えられています。早食いが習慣になってしまっている方は、意識して食事に時間をかけるよう心がけてみてください。
(2)食べる順番を工夫しよう
 料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。
料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。
食事をするときは、食物繊維を含む野菜や、たんぱく質を含む食品を、最初のほうに食べるように意識しましょう。たんぱく質を含む食品とは、肉・魚・卵などのことです。ほかにも、温かい味噌汁やスープなどの汁物も、最初のほうに食べると胃腸の働きをサポートしやすくなります。
最後のほうに食べたほうが好ましいのは、炭水化物を含む食品です。ごはん・パン・麺などがこれに該当します。血糖値を上昇させるため、食べ過ぎに注意するとともに、できるだけほかの食品を食べた後に摂取すると好ましいでしょう。
(3)食べる時間帯を意識しよう
 食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
脂質や糖質を摂るときは、朝食や昼食の時間帯を選ぶと良いでしょう。反対に、夕食の時間帯には食事を軽めに抑え、食後の間食などを抑えるよう工夫してみてください。特に、20時以降に炭水化物を含む菓子類などを摂るのは避けることをおすすめします。どうしても食欲が抑えられないときは、寒天や豆腐などの低カロリーなものを選びましょう。
太りにくい食べ方についてお伝えしました。食事の内容に気をつけることも大切ですが、ぜひ食べ方にも意識を向けて、より健康的な食習慣を身に着けていきましょう。

健康的な生活習慣を保つために役立てられる保健機能食品。不足しやすい栄養素を補ったり、健康維持の一環として取り入れたりすることで、すこやかなライフスタイルの維持につながるのが特徴です。今回は、よく耳にする「トクホ」をはじめとした、保健機能食品の基本的な情報についてお伝えします。
◆保健機能食品とは?
市販されている商品のパッケージで、「血圧が高めの方に」といった表示を見かけたことがないでしょうか?このように、摂取することで何らかの機能が期待できる食品は「保健機能食品」と呼ばれます。
保健機能食品には、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3つの種類があります。これらの保健機能食品は、安全性や有効性において国が定めた基準を満たし、国の制度に基づいて表示が行われています。
よく「トクホ」と略して呼ばれているのは、特定保健用食品です。国によって商品の審査が行われ、消費者庁の承認を受けられれば、期待できる効果をパッケージに表示することが認められます。人間のイラストのようなマークがつけられているのが特徴です。
「栄養機能食品」とは、栄養成分が含まれている食品を指します。トクホのように審査や承認はありませんが、基準を満たしている商品であれば、パッケージに指定された通りの表示ができるようになります。
それに対して「機能性表示食品」は、科学的根拠をもとに機能性が表示できる食品のことです。消費者庁に安全性や機能性についての届け出が必要ですが、国による審査は行われません。企業の責任のもとで表示されています。
3つの保健機能食品のなかでも、国の審査を受け、かつ消費者庁からの承認を受けているのは、特定保健用食品(トクホ)のみです。パッケージの機能表示をもとに判断しながら、食品を日頃の健康維持にお役立てください。
◆保健機能食品の注意点
 保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。
保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。
すでに医療機関で治療中の病気がある方や、服用している医薬品がある方は、保健機能食品を摂取する前に医師や薬剤師などの専門家への相談が必要となります。医薬品との飲み合わせに影響をおよぼすおそれもあるため、事前に確認しておきましょう。
そもそも、このような保健機能食品の制度が定められたのは、あたかも健康効果が得られるかのように表示する食品が流通し、消費者を混乱させるのを防ぐためです。これを踏まえて、特定の機能が期待できる食品を賢く健康に役立てることが大切だといえます。
◆保健機能食品の上手な活用方法
 健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
たとえば、病気ではない血圧がやや高めの方が、「特定保健用食品(トクホ)」の商品だけで体質の改善につなげようとするのは、適切ではありません。普段の食事で塩分を控えたり、運動する習慣をつけたりしたうえで、トクホの商品を活用しましょう。病気にかかっている方の場合は、医師の指示に従って医薬品を服用したり、トクホの商品を摂取しても問題がないか確認したりと、初めに医療機関で指導を受けることが大切です。
また、保健機能食品はたくさん摂取するほど高い効果が期待できるというわけではありません。商品には1日に摂取する量の目安が書かれているため、この範囲内で取り入れることをおすすめします。保健機能食品を活用しながら、健康増進に努めましょう。

“緑茶は体に良い”とよく言われていますが、具体的にどのような働きがあるのでしょうか? 緑茶には、歯の健康をサポートしたり、ダイエット効果を高めたり、花粉症のアレルギー症状を穏やかにしたりと、さまざまな働きがあります。より健康を大切にしたいなら、緑茶を飲む習慣を作ってみましょう。こちらでは、緑茶の健康効果についてご紹介します。
◆歯の健康をサポートする
緑茶の健康効果のひとつとして挙げられるのは、歯の健康をサポートできることです。緑茶を毎日飲むと虫歯予防に役立つと考えられています。緑茶には、歯を強くする働きのあるフッ素が含まれており、虫歯に対する抵抗力を上げられます。また、タンニンの持つ殺菌作用で、虫歯菌を減らす効果も期待されています。
緑茶で虫歯予防する場合は、食後に緑茶うがいをしてみましょう。緑茶うがいをすることで、虫歯の原因菌の繁殖を抑えたり、歯の表面に虫歯菌を付きにくくしたり、酸の産生を抑制したりといった働きが期待できます。ぜひ食後に緑茶でうがいをする習慣を作ってみてください。
◆ダイエットをサポートする
緑茶に含まれるカテキンは、ダイエットを手助けしてくれます。カテキンはポリフェノールの一種で、抗菌作用や殺菌作用を持っています。さらに、近年は脂肪燃焼効果が期待できることも分かってきました。脂肪の吸収を抑えて排出を促してくれるため、ダイエットを効率的に進められます。また、緑茶には利尿作用があるため、老廃物を排出してむくみを改善する効果も期待できます。
ダイエットのために緑茶を飲む際は、タイミングに気をつけましょう。おすすめは、運動前・食前・食事中・食後です。運動前に緑茶を飲むと、カフェインが脂肪を分解してくれるため、効率的に脂肪を燃やせます。食前や食中に飲めば、食欲抑制効果が期待でき、食事量のコントロールが可能です。また、食後にお茶を飲むと、食事で摂った糖質や脂質の吸収を抑える働きが期待できます。適切なタイミングで緑茶を飲んで、ダイエット効果を高めましょう。
◆血糖値のコントロールにつながる
緑茶には、血糖値を下げる働きも期待されています。ペンシルヴァニア州立大学農学部の研究チームの調査によると、マウスに緑茶の成分を与えると、糖尿病に関連する検査値が低下することが分かりました。
緑茶の成分を糖尿病のマウスに摂取させると血糖値が下がり、体重やインスリン値も減少したという結果が出ています。一方、緑茶の成分を摂取しなかったり、運動をしなかったりしたマウスは、数値に改善が見られませんでした。この実験から、緑茶の摂取と運動を同時に行うことで、血糖値の改善が期待できると考えられています。
◆花粉症のアレルギー症状を穏やかにする
 緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。
緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。
ただし、花粉症の症状を緩和するほどの高い効果を期待する場合、1日に2リットル近くの緑茶を飲む必要があります。この数値は現実的でなく、緑茶のみで花粉症の症状を抑えるのは難しいため、ほかの花粉症対策と合わせて緑茶を飲むようにしましょう。
◆肝臓の健康を守る
 緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。
緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。
緑茶に含まれるカテキンには抗酸化作用があり、肝臓を攻撃する活性酸素の抑制が期待できます。さらに緑茶の持つテアニンにはリラックス作用があるため、ストレスの緩和にも効果的です。肝臓の健康が気になる方は、ぜひ緑茶を飲むようにしてみてください。

 腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。
腸内環境を整えるために、朝~昼は活動的に過ごし、夕方~夜はリラックスして過ごしましょう。自律神経が自然と切り替わるような生活リズムが理想です。朝、目が覚めたら1杯の水を飲み、朝食を取ってください。腸に刺激を与えて排便を促しましょう。一方で、交感神経と副交感神経が切り替わる夕方以降には、軽い運動と軽い食事を心がけます。睡眠不足やストレスは、自律神経の乱れにつながるため、できるだけ解消につとめてください。 食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。
食生活から腸内環境を整えるうえでは、善玉菌を含む食品と、善玉菌のエサとなる食品をバランス良く摂ることが大切です。善玉菌を含む食品の例には、ヨーグルト・チーズ・納豆をはじめとした発酵食品が挙げられます。また、乳酸菌やビフィズス菌を含む整腸剤を摂る方法もあります。一方で、食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む食品は、善玉菌のエサとなります。野菜類・果物・豆類をはじめとした食品も、併せて取り入れましょう。


 もともと空気が乾燥しやすい冬。さらには、使用している暖房器具の影響でさらに湿度が低くなることがあります。このような環境で生活を続けていると、体の表面にある皮膚や粘膜、そして呼気から水分が失われてしまうのです。
もともと空気が乾燥しやすい冬。さらには、使用している暖房器具の影響でさらに湿度が低くなることがあります。このような環境で生活を続けていると、体の表面にある皮膚や粘膜、そして呼気から水分が失われてしまうのです。 寒い冬には、冷たい水を飲みにくいといえます。そのため、水分補給では温めた水である「白湯(さゆ)」を摂るのがおすすめです。お湯を沸かしたり、高温の水が出るウォーターサーバーを利用したり、温かくて飲みやすい温度の水を用意すると良いでしょう。
寒い冬には、冷たい水を飲みにくいといえます。そのため、水分補給では温めた水である「白湯(さゆ)」を摂るのがおすすめです。お湯を沸かしたり、高温の水が出るウォーターサーバーを利用したり、温かくて飲みやすい温度の水を用意すると良いでしょう。
 冬場に起こりやすいひび・あかぎれを予防するためのポイントをご紹介します。
冬場に起こりやすいひび・あかぎれを予防するためのポイントをご紹介します。 皿洗いや洗濯などの家事では、洗浄力の強い洗剤や水が手肌に直接触れないよう、ゴム手袋を付けることをおすすめします。ほかにも、手の油分を奪ったり刺激を与えたりする習慣は乾燥につながりやすいためご注意ください。
皿洗いや洗濯などの家事では、洗浄力の強い洗剤や水が手肌に直接触れないよう、ゴム手袋を付けることをおすすめします。ほかにも、手の油分を奪ったり刺激を与えたりする習慣は乾燥につながりやすいためご注意ください。
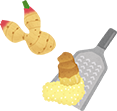
 冬に嬉しい健康効果が期待できる生姜ですが、食べることでほかにもたくさんのメリットが得られます。古くから人類とともにあった生姜のパワーを、ぜひ理解しておきましょう。
冬に嬉しい健康効果が期待できる生姜ですが、食べることでほかにもたくさんのメリットが得られます。古くから人類とともにあった生姜のパワーを、ぜひ理解しておきましょう。
 ヒートショックによる健康被害や死亡事故を防ぐために、今からできる対策をご紹介します。気温が下がり始めたら意識的に取り入れてみてください。
ヒートショックによる健康被害や死亡事故を防ぐために、今からできる対策をご紹介します。気温が下がり始めたら意識的に取り入れてみてください。 浴室に入ったとき、いきなり浴槽に入り全身を温めると、心臓に負担をかけやすくなります。まずは心臓から遠い手足にお湯をかけて、部分的に温めてから少しずつ体を慣らしましょう。また、お湯の温度が高すぎるのも好ましくありません。温度は38~40度を目安にして、長時間浴槽に浸かりすぎないようお気をつけください。
浴室に入ったとき、いきなり浴槽に入り全身を温めると、心臓に負担をかけやすくなります。まずは心臓から遠い手足にお湯をかけて、部分的に温めてから少しずつ体を慣らしましょう。また、お湯の温度が高すぎるのも好ましくありません。温度は38~40度を目安にして、長時間浴槽に浸かりすぎないようお気をつけください。
 日頃の体重計を使った健康管理に加えて、体組成計を取り入れると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。まず挙げられるのは、皮下脂肪や内臓脂肪の量を測定できることです。体組成計を使うと、体脂肪率がわかるだけでなく、その脂肪が皮下脂肪なのか内臓脂肪なのかをチェックすることができます。
日頃の体重計を使った健康管理に加えて、体組成計を取り入れると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。まず挙げられるのは、皮下脂肪や内臓脂肪の量を測定できることです。体組成計を使うと、体脂肪率がわかるだけでなく、その脂肪が皮下脂肪なのか内臓脂肪なのかをチェックすることができます。 内臓脂肪が増えると、血液中の脂質が増え、血圧が上昇し、インスリンの働きが悪くなります。これらの要因は、脂質異常症・糖尿病・高血圧症などの生活習慣病につながると考えられています。また、複数の症状が組み合わさることで、メタボリックシンドロームをまねくリスクがあるのも知っておきたいポイントです。
内臓脂肪が増えると、血液中の脂質が増え、血圧が上昇し、インスリンの働きが悪くなります。これらの要因は、脂質異常症・糖尿病・高血圧症などの生活習慣病につながると考えられています。また、複数の症状が組み合わさることで、メタボリックシンドロームをまねくリスクがあるのも知っておきたいポイントです。

 秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
秋の味覚をきのこと組み合わせて食べることで、日々の健康維持にお役立てください。まずおすすめしたいのはサンマです。サンマに含まれる「DHA」や「EPA」はオメガ3脂肪酸と呼ばれ、コレステロールを押さえて血流を良くする効果が期待されています。サンマにはビタミンCが含まれないため、きのこと一緒に摂取するとバランスが良くなります。
 料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。
料理を食べる順番によって、食事中の血糖値の上昇を抑えられると考えられています。血糖値が上昇すると、体内でインスリンという物質が分泌されることで、血液中の糖分を脂肪として溜め込みやすくなります。また、食欲の増進につながるとも考えられているため、肥満を予防したい場合には注意が必要です。 食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
食事を摂る時間帯も、太りやすさと関係すると考えられています。たとえば、1日の活動に必要なエネルギーは、朝食や昼食で摂取することが大切です。その一方で、就寝後は活動量が少なくなるため、夕食ではそれほど多くのエネルギーが必要とされません。また、内蔵に負担をかけすぎないよう、消化の良い食事を摂るのが好ましいとされています。
 保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。
保健機能食品について注意しておきたいのは、これらが食品であり、医薬品ではないということです。保健機能食品は、病気にかかっていない人が利用することを想定した商品であるため、病気の治癒や予防などの目的で利用されることはありません。 健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
健康に対するさまざまな機能が期待されている「保健機能食品」ですが、あくまでひとつの食品として日頃の食生活に取り入れて活用しましょう。健康を保つためには、基本的にすこやかな食生活や運動習慣を徹底することが必要です。
 緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。
緑茶に含まれるカテキンには抗アレルギー作用があり、ヒスタミンの発生を抑えて皮膚や粘膜を保護してくれます。特におすすめなのは「べにふうき」という品種です。べにふうき緑茶を飲むことで、花粉やハウスダストによるアレルギー症状を和らげる効果が期待できます。 緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。
緑茶は肝臓の健康を守るのにも役立ちます。肝臓は体内の栄養分を蓄積したり、有害物質の解毒を行ったりする重要な臓器です。しかし、活性酸素に弱いという特徴を持っています。ストレスにも弱く、悩み事があると簡単にALTやASTの数値が上がってしまいます。