
冬は、汗をかく機会があまりなく水分を失っている自覚も少ないため、飲料摂取量が少なくなってしまう傾向にあります。空気の乾燥により体の水分も失われやすく、脱水を引き起こす可能性が高い季節といえます。また、ノロウイルスやインフルエンザなど、感染症にかかりやすい季節でもあるため、下痢や嘔吐で脱水症に陥ってしまう人も珍しくありません。今回は、そんな冬場の水分補給をより効果的にする、「電解質」についてご紹介します。
◆電解質とは?
電解質とは、水に溶けると電気を通す性質をもった物質のことです。人間の体の水分(体液)には、もともと電解質が含まれています。水中では電解質は電気を帯びたイオンになり、体内の水分量やpHを一定に保ったり、神経細胞や筋肉細胞の働きにかかわったりしています。
電解質はそれぞれバランスを取りながら、生命の維持に重要な役割を果たしています。そのため、バランスが崩れてしまうと腎機能やホルモンの働きが低下し、命にかかわることもあるのです。
◆おもな電解質とその役割
おもな電解質は、ナトリウム・クロール・カリウム・マグネシウム・カルシウムの5つです。これらは、5大栄養素のうちのミネラルに属します。こちらでは、それぞれの働きや性質をご紹介します。
 ・ナトリウム (Na)
・ナトリウム (Na)
ナトリウムは、体の水分や浸透圧を調節する働きを持っています。神経伝達や筋肉の収縮にも深いかかわりをもつ成分です。
 ・クロール(Cl)
・クロール(Cl)
大部分のクロールはナトリウムとともに存在しており、体の水分量や浸透圧の調節などを行っています。胃酸の分泌や酸塩基平衡の維持にもかかわる成分です。
 ・カリウム(K)
・カリウム(K)
神経伝達や筋肉の収縮、心臓の収縮にかかわります。カリウムが低くなると神経麻痺や摂食障害、高くなると不整脈や腎不全などが起こる可能性が高く、生命維持に大きな役割を果たしている重要な成分です。
 ・マグネシウム(Mg)
・マグネシウム(Mg)
マグネシウムは神経や筋肉を正常に機能させ、骨や歯を作る働きをもちます。また、体内にある酵素も、マグネシウムがなければ正常に機能しません。カルシウムやカリウムの代謝にもかかわる成分です。
 ・カルシウム(Ca)
・カルシウム(Ca)
カルシウムは、骨や歯を作ったり、血液を凝固させたりする働きをしています。体内のカルシウムの99%は、骨や歯などに蓄えられており、血中のカルシウム濃度が低下すると、骨から血液中に移動して濃度を保っています。
◆より効果的に水分補給するためのポイント
 普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。
普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。
電解質を失った状態で水を飲んだ場合は、一時的に体液が増え、体液における電解質の濃度が下がります。すると体は、電解質の濃度を一定に保とうとして、過剰な水分を尿として排出してしまうのです。結果として体液量が回復できず、水分補給ができていない状態を「自発的脱水」と呼びます。このような場合、電解質を含む飲料で水分補給すれば、体液を薄めずに水分補給ができます。水分とともに電解質を失った場合は、経口補水液やイオン飲料で水分補給することが大切です。
脱水症の予防には、塩分濃度が0.1~0.2%のスポーツドリンクなどが有効です。脱水症が発生した場合は、スポーツドリンクに比べナトリウム量が多く水分吸収速度の速い経口補水液が適しています。
より効果的に水分補給するために、意識しておきたい電解質についてご紹介しました。電解質は、生命を維持するためになくてはならない存在です。感染症にかかりやすく脱水症を起こしやすい冬は、電解質を含む経口補水液やイオン飲料を常備してみてはいかがでしょうか。

次第に日が落ちるのが早くなり、秋の深まりや冬の訪れを感じる季節になりました。日照時間は、12月の冬至が1年でもっとも短いとされています。もっとも長い6月の夏至と比べると、日の出から日の入りまで約5時間も差があるのです。
そんな日照時間の短い季節になると、憂鬱な気分になったり気分の落ち込みを感じたりすることはありませんか? 今回は、日照時間の短い季節に気をつけたい、季節性うつ病(季節性情動障害)についてご紹介します。
◆季節性うつ病とは?
 季節性うつ病とは、季節性情動障害(SAD)と呼ばれることもある病気で、毎年決まった時期に症状が現れるという特徴があります。日照時間と深いかかわりがあるといわれており、緯度の高い地域ほど多く見られる病気です。日照時間の短くなる秋口から症状が現れ始め、日の長くなる春先になると自然に回復します。このような特徴から「冬季うつ病」と呼ばれることもありますが、雨で日照時間が短くなる梅雨時に発症する場合もあるようです。おもな症状は、気分の落ち込み・体のだるさ・無気力・過眠・過食などが挙げられます。
季節性うつ病とは、季節性情動障害(SAD)と呼ばれることもある病気で、毎年決まった時期に症状が現れるという特徴があります。日照時間と深いかかわりがあるといわれており、緯度の高い地域ほど多く見られる病気です。日照時間の短くなる秋口から症状が現れ始め、日の長くなる春先になると自然に回復します。このような特徴から「冬季うつ病」と呼ばれることもありますが、雨で日照時間が短くなる梅雨時に発症する場合もあるようです。おもな症状は、気分の落ち込み・体のだるさ・無気力・過眠・過食などが挙げられます。
◆季節性うつ病の原因とは?
季節性うつ病には、日照時間が深く関係していると考えられています。人間は日光に当たると、セロトニンという脳の神経伝達物質が合成されます。セロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれており、集中力が増して気持ちが明るくなるなど、精神面に好影響を与えるホルモンです。一方、セロトニンが不足すると、気分の落ち込みや疲労感、意欲低下など、うつ症状が発現するといわれています。
また、日光浴を浴びると、体内でビタミンDも作られます。ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進したり免疫機能を調整・維持したり、多彩な働きを担う栄養素です。ビタミンDの欠乏もまた、季節性うつ病と関連しているといわれています。
◆季節性うつ病の予防法
 日照時間の少なくなる冬場は、意識的に季節性うつ病の予防に努めましょう。暖かい部屋に閉じこもりがちな冬場だからこそ、気をつけたいポイントをご紹介します。
日照時間の少なくなる冬場は、意識的に季節性うつ病の予防に努めましょう。暖かい部屋に閉じこもりがちな冬場だからこそ、気をつけたいポイントをご紹介します。
・日光を浴びる
季節性うつ病は、日照時間と深いかかわりのある病気です。セロトニン不足、ビタミンD不足を防ぐためにも、意識的に日光を浴びるようにしましょう。屋内で働いている方や外に出る機会の少ない方は、可能な限り窓辺で過ごし、日光に当たるようにするだけでも良い影響が期待できます。
・バランスの良い食事を心がける
 冬場は、年末に向けて仕事が忙しくなったり飲み会が増えたり、食生活が乱れる可能性が高い時期といえます。肉や魚などのたんぱく質やビタミン、ミネラルを意識的に摂り、栄養バランスのいい食事を心がけましょう。バランスのいい食生活は、セロトニンの生成を促します。また、ビタミンDは、食事から摂取することも可能です。魚、卵、キノコ類に多く、しらす、アンコウの肝、干しシイタケに多く含まれています。意識的に食事に取り入れてみてください。
冬場は、年末に向けて仕事が忙しくなったり飲み会が増えたり、食生活が乱れる可能性が高い時期といえます。肉や魚などのたんぱく質やビタミン、ミネラルを意識的に摂り、栄養バランスのいい食事を心がけましょう。バランスのいい食生活は、セロトニンの生成を促します。また、ビタミンDは、食事から摂取することも可能です。魚、卵、キノコ類に多く、しらす、アンコウの肝、干しシイタケに多く含まれています。意識的に食事に取り入れてみてください。
・適度な運動
 適度な運動は、気持ちが前向きになったりストレス解消になったりする効果が期待できます。外に出る機会の少ない方は、できるだけ運動を習慣化してみましょう。特に、太陽の光を浴びながらできる、ウォーキングなどの運動がおすすめです。
適度な運動は、気持ちが前向きになったりストレス解消になったりする効果が期待できます。外に出る機会の少ない方は、できるだけ運動を習慣化してみましょう。特に、太陽の光を浴びながらできる、ウォーキングなどの運動がおすすめです。
日照時間が短くなる冬場こそ気をつけたい、季節性うつ病についてご紹介しました。日光浴は、セロトニンを分泌させ、ビタミンDを生成するなど、季節性うつ病を予防する効果が期待できます。冬場の日照時間を変えることはできませんが、晴れた日は意識的に日光浴を取り入れてみてください。冬になると気分の落ち込みや集中力の低下を感じるという方は、無理はせず、心療内科や精神科に相談しましょう。

気温がぐんと下がり、どんどん寒くなるこれからの時期は、冷え性に悩まされる方も多いでしょう。冷え性は、「全身型」「内臓型」「四肢末端型」「下半身型」と、大きく4つのタイプに分けられます。今回は、冷え性のタイプ別に、より効率的な対策・改善法をご紹介します。さまざまな対策法を試しても冷え性が改善しないと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
◆全身型
全身型の特徴は、常に体温が低く、気温の変化に関わらず一年を通して寒さを感じるタイプです。ストレスや生活習慣が乱れている若者や高齢者など、基礎代謝が低下している方に多く見られます。冷えが慢性化しているため、自覚症状がない人が多いのも特徴的です。倦怠感や疲労感を感じやすく、食欲や気力の低下などの症状が出るケースもあります。甲状腺機能の低下によって引き起こされる可能性もあるため、あまりにも症状が改善されない場合は病院に受診しましょう。
・全身型の対策・改善法

全身型冷え性の主な原因は、基礎代謝の低下にあります。適度な運動を取り入れたり、規則正しい生活を心がけたりして、基礎代謝を上げるよう努めましょう。靴下や腹巻などを活用し、できるだけ体を冷やさないようにすることも大切です。冷たい飲食物を避け、ショウガやネギなど、体を温める性質をもつ食品を積極的にとりましょう。
◆内臓型
内臓型は、手足や体の外側などは温かいのに内臓だけが冷えてしまうタイプで、別名「隠れ冷え性」とも呼ばれています。胃腸が弱く、筋肉の少ない方に多く見られるタイプです。冷たい飲食物を好んで摂取する方や、全身に汗をかきやすい方も内臓型冷え性の可能性が高いといえます。冷えを自覚しづらいため、知らず知らずのうちに内臓に負担をかけてしまっているかもしれません。

・内臓型の対策・改善法
内臓型冷え性は、ストレスなどで自律神経が乱れると引き起こされやすくなります。ストレスをため込まないよう適度に発散したり、規則正しい生活で睡眠不足を解消したりして、自律神経を整えましょう。薄着は避け、腹巻やカイロで積極的にお腹を温めるのも効果的です。冷たい飲み物や生野菜の摂取を控え、温かいものをとりましょう。
◆四肢末端型
 四肢末端型は、手先や足先が冷える典型的な冷え性タイプです。食事量が少ないダイエット中の方や、運動不足によって筋力が低下してしまっている方に多く見られます。体を温めるためのエネルギーが不足しているため末端まで血液が巡らず、手先足先から冷えてしまうのです。しもやけや肌荒れ、月経トラブルを引き起こすことがあります。
四肢末端型は、手先や足先が冷える典型的な冷え性タイプです。食事量が少ないダイエット中の方や、運動不足によって筋力が低下してしまっている方に多く見られます。体を温めるためのエネルギーが不足しているため末端まで血液が巡らず、手先足先から冷えてしまうのです。しもやけや肌荒れ、月経トラブルを引き起こすことがあります。
・四肢末端型の対策・改善法
四肢末端型冷え性の主な原因は、運動不足による筋力の低下です。体の中でもっとも多くの熱を生み出す筋肉をつけるために、毎日の生活に運動やストレッチを取り入れましょう。また、しっかり食事をとることも大切です。特にたんぱく質は、食事誘発性熱産生の高い栄養素のため、積極的に摂取することをおすすめします。お風呂はシャワーだけで済まさず、湯船にしっかり浸かるようにしましょう。
◆下半身型
上半身は温かいのに、お尻や太もも、足など、下半身が冷えてしまうタイプです。加齢によって血管が細くなったり筋力が衰えたりすることで、下半身の血行が悪くなると起こりやすくなります。また、むくみやすい方、デスクワークなどで長時間同じ体勢でいる方なども起こりやすいタイプです。下半身は冷えているのに上半身は血が巡るため温かく、「冷えのぼせ」の症状が出ることがあります。

・下半身型の対策・改善法
下半身型冷え性は、下半身の血行不良が原因となって起こります。スクワットやかかとの上げ下げ運動、階段の上り下りなどを積極的に行いましょう。また、マッサージやストレッチも効果的です。デスクワークなどで長時間同じ体勢をとる方は、定期的に立ち上がったり下半身のストレッチをしたりして、血液を循環させるように心がけましょう。
冷え性を4つのタイプに分け、タイプごとの対策と改善法をご紹介しました。自分の冷え性タイプと原因をしっかり把握し、より効果的な対策をとりましょう。冷えは、さまざまな体の不調を引き起こす原因にもなります。より健康的に冬を過ごせるように、冷え性を改善しながら寒さに備えましょう。

新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、自宅でのテレワークを導入する企業が増えました。会社に通勤する手間が省けるため楽になったという人がいる一方で、新しい勤務形態に疲労を感じている人も多くいるといいます。今回は、コロナ禍におけるテレワーク疲れの原因や、予防法についてご紹介します。
◆テレワーク疲れの原因とは?
テレワーク疲れの主な原因として、以下が考えられます。疲れている自覚がなくても、疲れをため込んでしまっている可能性もあるため注意しましょう。
・同居人のストレス
 家に同居人がいて仕事専用のスペースなどがない場合、同居人の存在がストレスになってしまうことがあります。仕事に集中できなくなったり、電話やオンライン会議中に移動を余儀なくされたり、お互いの生活に支障が出てしまうためです。
家に同居人がいて仕事専用のスペースなどがない場合、同居人の存在がストレスになってしまうことがあります。仕事に集中できなくなったり、電話やオンライン会議中に移動を余儀なくされたり、お互いの生活に支障が出てしまうためです。
・自己管理の難しさ
自宅で仕事をするためオンとオフの切り替えが難しく、生活習慣が乱れてしまうことがあります。また、外に出る機会が大きく減ってしまうため、運動不足による肩こりや腰痛など体の不調が出ることも多いようです。
・リフレッシュできない
通勤途中にお気に入りのコーヒーショップに寄ったり、仕事帰りにジムに通ったりしていた人の場合、通勤がなくなることでリフレッシュできず、かえってストレスになってしまうことがあります。
・業務内容の変化
テレワークに合わせて業務を簡素化したりテンプレート化したりすると、個々のクリエイティビティが発揮されにくくなってしまいます。仕事にやりがいを感じられず、疲れを感じてしまう人も多いようです。また、褒められたり認められたりする承認の不足も大きな原因の1つといえるでしょう。
◆テレワーク疲れに注意したいシーン
仕事へ真面目に取り組むのは大切ですが、頑張りすぎてしまうとテレワークによる疲れを感じてしまうことも。集中しにくい環境に焦りをおぼえて、仕事を抱え込みすぎてしまったり、就業時間外にも仕事をしてしまったりすることがないでしょうか。なかには上司や同僚とのコミュニケーション不足から、不安や孤独を感じてしまう人もいるようです。
また、普段から友人との外食やショッピングなどでストレスを発散していた人は、外出の機会が大きく減ってしまうと、テレワークによる疲れを感じる場合があります。意識してテレワーク疲れの対策に取り組みましょう。
◆テレワーク疲れの予防法
テレワーク疲れを放置すると、身体的にも精神的にも悪影響を及ぼすと考えられます。リモート疲れを蓄積させないために、意識的に予防しておきましょう。
・生活習慣の見直し
生活習慣の乱れは自律神経の乱れにつながります。通勤がなくても、夜更かししたり朝ギリギリまで眠ったりせず、いつもと同じ時間に起きて身だしなみを整えるようにしましょう。仕事のオン・オフの切り替えにもなり、メリハリがつきやすくなります。

・適度な休息と運動を取り入れる
長時間作業を行うときは、1時間に1回は席を立ち、適度な休憩を取りましょう。トイレに行ったり、飲み物を取りに行ったりするだけでもいい気分転換になります。簡単な体操やストレッチを行えば、肩こり予防やストレスの解消にも効果的です。
・積極的にコミュニケーションを取る
 業務的なやり取り以外にも、気軽にコミュニケーションが取る環境を作りましょう。コミュニケーションツールを利用し、相談用や雑談用の部屋などを作るのもおすすめです。業務以外の話ができる機会を設けることで、ストレス緩和や孤独感からの解放などの効果が期待できます。
業務的なやり取り以外にも、気軽にコミュニケーションが取る環境を作りましょう。コミュニケーションツールを利用し、相談用や雑談用の部屋などを作るのもおすすめです。業務以外の話ができる機会を設けることで、ストレス緩和や孤独感からの解放などの効果が期待できます。
テレワーク疲れを予防するためには、バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動も必要不可欠です。通勤がないからとだらけるのではなく、意識的に仕事のオン・オフを切り替えられるようにしましょう。また、コミュニケーションの重要性も見直されてきています。職場のコミュニケーション不足を感じている人は、話し合いの場を整える提案をしてみてください。

夏は食欲不振や体のだるさなど、暑さが原因で引き起こされる体調不良、いわゆる「夏バテ」に悩まされる方も多いのではないでしょうか。冷房で涼しい屋内と猛暑の屋外、気温差の激しい場所を何度も行き来して自律神経が乱れたり、冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎて胃腸を冷やしたりすると夏バテの原因になってしまう可能性があります。そこで今回は、夏バテの予防にぴったりな食材、「スパイス」についてご紹介します。
◆スパイスの効用
 スパイスが夏バテ予防に効果的なのは、以下のような効用があるためです。日ごろから食事にうまく取り入れ、体の内側から夏バテ予防に努めましょう。
スパイスが夏バテ予防に効果的なのは、以下のような効用があるためです。日ごろから食事にうまく取り入れ、体の内側から夏バテ予防に努めましょう。
・発汗作用
気温の高い夏は体に熱がこもりやすいため、汗でうまく熱を発散して体温を調整する必要があります。しかし、加齢や運動不足などによって発汗機能が低下していると、発散できずに熱がこもったままの状態になってしまいます。発汗作用のあるスパイスを摂取することで発汗を促し、上手に体温調節しましょう。
・食欲増進
スパイスの辛味成分は、消化器の粘膜を刺激し、唾液や消化液の分泌を促す作用があります。さらに腸の蠕動運動を促進させるため、食欲を増進するのに効果的です。暑くなるとカレーが食べたくなるという人が多いのも、スパイスにこのような効用があるためと考えられます。
・防腐・抗菌作用
スパイスには防腐・抗菌作用があるため、料理が傷みやすい夏にはぴったりの食材といえます。また、腸菌の増殖を防ぐ作用もあるといわれています。食中毒予防のためにも、日々の食事にうまくスパイスを取り入れましょう。
◆夏バテ予防におすすめのスパイス3選
現代では調味料や香辛料としてさまざまな料理に使われているスパイス。実は、古くから薬として重宝されていました。中国やインドでは漢方として処方したり、体調に応じて料理に使うスパイスを変えたりして活用しているといいます。夏バテ予防に効果が期待できる、おすすめのスパイスを3種類ご紹介します。
・カルダモン
 カルダモンは、さわやかな清涼感のある香りが特徴のスパイスです。カレーのなかでも大切なスパイスといわれており、チャイなどにも使用されます。唾液や胃酸の分泌を促し、消化の手助けをしてくれる働きがあるため、夏バテ予防にぴったりです。また、消臭効果もあるため、口臭や汗の臭いが気になりがちな夏におすすめできます。
カルダモンは、さわやかな清涼感のある香りが特徴のスパイスです。カレーのなかでも大切なスパイスといわれており、チャイなどにも使用されます。唾液や胃酸の分泌を促し、消化の手助けをしてくれる働きがあるため、夏バテ予防にぴったりです。また、消臭効果もあるため、口臭や汗の臭いが気になりがちな夏におすすめできます。
・ターメリック
 ターメリックは、ウコンという名前でもおなじみのスパイスです。明るくて濃い黄色が特徴で、ウコンドリンクやカレーに使われます。弱った肝臓の働きを助けたり、胃を活発にしたりする働きがあるため、食欲減退を抑える効果が期待できます。
ターメリックは、ウコンという名前でもおなじみのスパイスです。明るくて濃い黄色が特徴で、ウコンドリンクやカレーに使われます。弱った肝臓の働きを助けたり、胃を活発にしたりする働きがあるため、食欲減退を抑える効果が期待できます。
・クローブ
 クローブは、刺激的な味と香りが特徴のスパイスです。肉の臭み消しや風味付けとして、煮込み料理にも使用されます。胃腸を温める効果があるため、冷えからくる体の不調を解消したり消化を助けたりする効果が期待できます。相性のいいシナモンと組み合わせてホットワインやチャイなどのドリンクにすると、さらに温め効果がアップするためおすすめです。
クローブは、刺激的な味と香りが特徴のスパイスです。肉の臭み消しや風味付けとして、煮込み料理にも使用されます。胃腸を温める効果があるため、冷えからくる体の不調を解消したり消化を助けたりする効果が期待できます。相性のいいシナモンと組み合わせてホットワインやチャイなどのドリンクにすると、さらに温め効果がアップするためおすすめです。
◆スパイスの注意点
スパイスの中には、例えばナツメグのように大量に摂取すると中毒症状を起こしてしまうものがあります。どんなスパイスでも、原則として少量ずつ使うことを心がけましょう。また、スパイスには、薬の飲み合わせが悪いものや、体調によって避けた方がいいとされるものがあるので注意が必要です。持病のある方や妊娠・授乳中の方、アレルギー疾患のある方は、摂取を控えるか、主治医に相談してから摂取するようにしてください。
夏バテ予防に効果が期待できる、おすすめのスパイスをご紹介しました。夏バテ以外にも、消臭や美容、ダイエットなどにも効果的なスパイスを、日々の食事や生活にぜひ取り入れてみてください。おいしく食べて、体の中から元気に夏を乗り切りましょう。

リラックスしたいときや、リフレッシュしたいときは、自分の好きな香りをじっくりと味わってみてはいかがでしょうか。今回は、植物の香りの力を借りて心身を健やかに保つ「アロマテラピー」についてご紹介します。市販のアロマオイルを用意するだけで、ご自宅で簡単にヘルスケアの習慣を取り入れられるため、お気軽にお試しください。
◆ヘルスケアでも注目されるアロマテラピー
アロマテラピーとは、植物の香りを利用した自然療法のことです。「アロマオイル」と呼ばれる植物から抽出した精油を用いて、心身を健やかに保ちます。アロマオイルによってもたらされる匂いの情報は、嗅覚を通じて大脳辺縁系へと伝わり、刺激を与えます。そんなアロマテラピーは、市販のグッズを使えば、ご自宅でも簡単に行えるのが魅力です。
 お家でアロマテラピーを行うには、お好みのアロマオイルと、香りを広げるためのディフューザーやティッシュなどを用意しましょう。ディフューザーやティッシュに数滴のアロマオイルを垂らして香らせるのが、基本の楽しみ方です。
お家でアロマテラピーを行うには、お好みのアロマオイルと、香りを広げるためのディフューザーやティッシュなどを用意しましょう。ディフューザーやティッシュに数滴のアロマオイルを垂らして香らせるのが、基本の楽しみ方です。
なお、アロマテラピーは医療機関の治療とは異なるものです。病気を治療中の方や、妊娠中の方など、体調に留意すべき点があれば医師へ相談のうえで楽しみましょう。
◆アロマに期待できる効果とは?
日常生活にアロマオイルを取り入れると、それぞれの香りの特徴を楽しめます。さらには、原料となる植物の種類によって、心身の健康にうれしい効果が期待できることも。たとえば、花のように甘いフローラル系の香りや、濃厚な樹脂系の香りは、心身をリラックスさせるといわれます。同様に、爽やかな柑橘系の香りや、清涼感のあるハーブ系の香りは、心身をリフレッシュさせるといわれます。
◆リラックス&リフレッシュにおすすめの香り
心身を健やかに保ちたいとき、シーンに合わせて以下のおすすめの香りを試してみてはいかがでしょうか。
・リラックスにおすすめのアロマ

気分を落ち着けたいリラックスのシーンには、「ラベンダー」「カモミール」「イランイラン」などのアロマオイルがおすすめです。ラベンダーは初心者にも使いやすい定番の精油で、優しい香りによって緊張がほぐれるといわれます。フルーティーなカモミールの香りは心に安らぎを与え、甘いイランイランの香りは気持ちを安定させるのが特徴です。これらのアロマは、眠りに入るタイミングにもよく使われます。
・リフレッシュにおすすめのアロマ
 すっきりと気分転換したいリフレッシュのシーンには、「レモン」「ペパーミント」「ユーカリ」などのアロマオイルがおすすめです。爽やかなレモンの香りは柑橘系のなかでも知名度が高く、気持ちを前向きにしてくれます。ペパーミントの香りにはすっとした清涼感があり、鼻の通りを良くするのが特徴です。ユーカリはウッディーな香りで、集中したいときにも適しています。上手に活用して気分を切り替えましょう。
すっきりと気分転換したいリフレッシュのシーンには、「レモン」「ペパーミント」「ユーカリ」などのアロマオイルがおすすめです。爽やかなレモンの香りは柑橘系のなかでも知名度が高く、気持ちを前向きにしてくれます。ペパーミントの香りにはすっとした清涼感があり、鼻の通りを良くするのが特徴です。ユーカリはウッディーな香りで、集中したいときにも適しています。上手に活用して気分を切り替えましょう。
◆アロマオイルを使うときの注意点
最後に、日常生活でアロマオイルを使うとき、注意しておきたいことをご紹介します。
まず、アロマオイルは直接に肌へ付けないようお気をつけください。精油の原液は皮膚への刺激が強いため、付着すると異常が生じるおそれがあります。同じように、精油が目や口に入らないよう注意して使いましょう。
また、柑橘系の精油のなかには「光毒性」を持つものもあります。光毒性とは、紫外線に当たると皮膚に刺激を与える作用のことです。肌の露出部分にアロマオイルが付いた状態で日中の屋外へ外出するのは避けておきましょう。
ほかに、子どもやペットによる誤飲といった事故のリスクもあります。アロマオイルの入った容器は安全な場所へ保管してください。
ここまでご紹介したポイントを参考にしながら、アロマオイルをリラックス&リフレッシュに活用してみましょう。

2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、マスクの着用が推奨されるようになりました。それに伴い、長時間マスクを着用し続けることで引き起こされる「マスク肌荒れ」に悩む人が急増しています。こちらでは、マスク肌荒れを防ぐ方法や対策をご紹介します。肌トラブルを回避して、マスク生活と上手に付き合いましょう。
◆マスク肌荒れはなぜ起こるの?
マスク生活が始まってから、マスクによる肌荒れを実感している方も多いようです。まずは、なぜマスク着用によって肌荒れが起こるのか、その原因から見ていきましょう。
・蒸れ
 マスク内は湿度が高いため、一見肌に良さそうに見えます。しかし、過度な湿度は肌にとって好ましいわけではありません。汗や皮脂の分泌が増えたり、雑菌が繁殖しやすくなったりするため、ニキビができやすい環境になっているといえます。汗や皮脂が出やすくなる夏場は、さらなる注意が必要です。
マスク内は湿度が高いため、一見肌に良さそうに見えます。しかし、過度な湿度は肌にとって好ましいわけではありません。汗や皮脂の分泌が増えたり、雑菌が繁殖しやすくなったりするため、ニキビができやすい環境になっているといえます。汗や皮脂が出やすくなる夏場は、さらなる注意が必要です。
・摩擦
マスク着用時に喋ったり、こまめにつけ外ししたりすると、肌は摩擦ダメージを受けてしまいます。蒸れによる影響があるうえ、さらに摩擦ダメージが加わるため、肌トラブルが起きやすくなってしまうのです。
・乾燥
マスクをつけていると、自分の呼気によって内部の温度や湿度が高くなります。その反対に、マスクを外すとこうした湿気が蒸発するとともに、肌の水分も一緒に奪われてしまいます。乾燥は肌トラブルの大きな要因になるため、特に注意が必要です。
◆マスク肌荒れを予防しよう
マスク肌荒れを予防するには、マスク着用による肌ストレスをできるだけ軽くしておくことが大切です。ここでは、ご家庭でできる簡単な予防法をご紹介します。
・丁寧なスキンケア(保湿)
 肌荒れ予防の基本は、肌を清潔に保つことです。マスク内は、ニキビの原因であるアクネ菌が繁殖しやすい環境といえます。毎日朝晩、たっぷりの泡を使って丁寧に洗顔しましょう。肌の保湿は、肌を外的刺激から守ることにつながるため、季節を問わず重要です。特に、洗顔後は肌の水分が失われやすい状態になっているため、すぐに化粧水・乳液・クリームなどで保湿しましょう
肌荒れ予防の基本は、肌を清潔に保つことです。マスク内は、ニキビの原因であるアクネ菌が繁殖しやすい環境といえます。毎日朝晩、たっぷりの泡を使って丁寧に洗顔しましょう。肌の保湿は、肌を外的刺激から守ることにつながるため、季節を問わず重要です。特に、洗顔後は肌の水分が失われやすい状態になっているため、すぐに化粧水・乳液・クリームなどで保湿しましょう
・こまめに汗を吸い取る
マスクの内部は温度や湿度が高くなり、汗をかきやすい状態になっています。そのままにしておくと雑菌が繁殖してしまい、ニキビやかゆみなどの肌トラブルの原因につながってしまいます。汗をかいたら清潔なガーゼやタオル、またはウェットティッシュなどを押し当て、こまめに汗を吸い取りましょう。皮脂も一緒に吸い取ってしまうので、可能であれば再度マスクをつける前に保湿することをおすすめします。
・自分に合ったマスクの着用
マスクが肌に合わないと感じたら、マスクの素材を変えてみると肌への刺激が軽減することがあります。一般的に綿やシルクなど天然素材のマスクのほうが肌への負担は少ないといわれていますが、感染拡大を予防するうえでは不織布マスクが推奨されています。肌触りが気になるときは、不織布マスクと肌の間にガーゼなどを一枚はさむと、刺激が和らぐのでおすすめです。
・保湿クリームなどを塗っておく
マスク着用前に、保湿効果の高いクリームやワセリンなどを塗っておきましょう。特に、マスクが触れやすいほほ・鼻・あごなどに塗っておくと、マスクによる摩擦ダメージを軽減させる効果が期待できます。マスクのゴムが擦れやすく、ダメージを受けがちな耳の後ろも、忘れずにケアしてください。
マスク着用によって引き起こされる、「マスク肌荒れ」の原因と予防法をご紹介しました。コロナ禍の今、マスクは感染拡大防止のためになくてはならないものとなっています。マスク生活と上手に付き合うために予防と対策をしっかり行い、美肌と健康を守りましょう。

巣ごもり生活で体を動かす機会が減り、心身に不調を感じていないでしょうか。ここでは、運動不足による健康リスクや、日常生活で運動量を増やすコツについてお伝えします。無理なく体を動かす習慣をつけて、健康のために適度な運動量を確保しましょう。
◆「巣ごもり生活」でライフスタイルに起こった変化
2020年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、国内ではテレワークや外出自粛といったさまざまな対策が採られることとなりました。こうした「巣ごもり生活」によってライフスタイルが大きく変わり、1日のうち多くの時間を自宅で過ごしている人も少なくありません。そこで問題となっているのが、自宅から出ないことによる運動不足です。これまでは通勤や通学のほか、休日のアクティビティなどで体を動かす機会が多かった方も、ライフスタイルの変化にともない運動不足となっている可能性も。運動量が減って心身の不調を感じるときは、生活習慣を見直してみましょう。
◆運動不足による健康リスクとは?
一見すると、それほど深刻には見えない運動不足。しかし、運動不足が長期間にわたり続くと、心身に影響を与えるだけでなく、生活習慣病のリスクを高めると考えられているのです。日常生活における運動量が不足していると、体力や筋力が低下してしまいます。立ったり歩いたりする能力が衰えれば、やがて活動の幅が制限され、生活の質(QOL)が下がるおそれがあるでしょう。適度に体を動かして気分転換ができない場合、ストレスが溜まりやすいため注意が必要です。また、運動不足が続くと食事での摂取エネルギーに対して消費エネルギーが少なくなる傾向にあります。こうした状況から、肥満・高脂血症・高血圧といった生活習慣病を引き起こしかねません。
◆日常生活で体を動かす習慣をつけましょう
巣ごもり生活で運動不足を感じているものの、いきなりスポーツを始めるのはハードルが高い……そんなときは、身近なところから少しずつ体を動かす習慣をつけていきましょう。最後に、日常生活で運動量を増やすコツをご紹介します。

・日常の動作を少しずつ増やす
日常生活のなかには、体を動かすチャンスが意外と多くあります。まずは、いつもより多く動くことを目標にしてみましょう。エレベーターやエスカレーターを使わずに階段で移動したり、拭き掃除のように全身を使った家事に取り組んだりするだけでも構いません。少しずつ運動量を増やして、運動に慣れていくことが大切です。

・ウォーキングを取り入れる
特別な準備が不要で、どこでも気軽に始められるウォーキング。初めのうちは短い距離から、軽い散歩のつもりで取り組んでみてはいかがでしょうか。日用品の買い物のためにお店まで歩いたり、近所の公園へ出かけたりすると良いでしょう。余裕ができたら、歩いた距離を記録したり、週や月ごとの目標を立てたり、自分なりの楽しみ方ができると理想的です。
・トレーニング動画などを活用する
 昨今の巣ごもり需要を受けて、自治体の公式サイトや動画共有サイトなどで、無料のトレーニング動画が提供されています。動画では目的に応じたトレーニングメニューが用意されており、自宅で効果的に体を動かすために役立ちます。スポーツジムに通うのが難しい方は、動画でプロのトレーナーによる解説を聞くのもひとつの手です。
昨今の巣ごもり需要を受けて、自治体の公式サイトや動画共有サイトなどで、無料のトレーニング動画が提供されています。動画では目的に応じたトレーニングメニューが用意されており、自宅で効果的に体を動かすために役立ちます。スポーツジムに通うのが難しい方は、動画でプロのトレーナーによる解説を聞くのもひとつの手です。
巣ごもり生活で運動不足を感じたら、自分が無理なくできる運動に、少しずつ取り組むようおすすめします。慣れてきたら、徐々に運動量を増やしてみてください。体を動かすことで健康リスクを避けて、心身を健やかに保ちましょう。

紫外線は、一般的に夏の季節にもっとも強くなります。春から夏にかけて、少しずつ紫外線対策を意識し始めましょう。今回は、紫外線と健康の関係についてお伝えします。つい勘違いしがちな部分もあるからこそ、改めて日焼けの基礎知識を確認してみてください。
◆紫外線の浴びすぎは健康に悪いの?
私たちが目で見ることはできませんが、太陽光には「紫外線」が含まれています。紫外線は、体内でビタミンDを作るために必要な要素です。ビタミンDには、腸でのカルシウムの吸収を2~5倍にする働きがあります。不足するとカルシウム不足に陥るおそれがあり、大切な栄養素といえるでしょう。きのこや一部の魚類にも含まれていますが、食品のみで必要な量を確保するのは難しいと考えられています。ところが、紫外線の浴びすぎは健康への影響が懸念されているため、やや注意が必要です。
◆日焼けの基礎知識
紫外線を浴びると、私たちの体は日焼けをします。日焼けには、紫外線を浴びた数時間後に肌が赤くなる「サンバーン」と、数日後に肌が黒くなる「サンタン」という種類があります。サンバーンが2~3日程度で消えるのに対して、サンタンが消えるまでには数週間から数カ月といった長い期間がかかることも珍しくありません。
このようにサンタンによって肌が黒くなるのは、体が紫外線の被害を防ごうとする防衛反応です。よく「サンタンが紫外線を防ぐ」と誤解されることもあるようですが、実際に紫外線を防ぐ効果はとても小さく、SPF4程度だといわれます。なお、一般的な日常生活レベルで使われる日焼け止めは、SPF10~35です。
日本で紫外線がもっとも強くなるのは6~8月ですが、紫外線の強さや量は地域によって異なります。また、紫外線量は環境によって大きく異なり、日陰の紫外線量は日向の50%、光が反射しやすい新雪の上では紫外線量が100%+80%となります。紫外線をよく反射する雪や砂のある環境では、日焼けをしやすくなることに注意しましょう。
◆紫外線が健康に与える影響
 紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。
紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。
◆紫外線の浴びすぎを避けるポイント
 皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。
皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。
また、屋外の紫外線を避けるのが難しいときは、肌に塗る日焼け止めを活用する方法もあります。市販の日焼け止めは、利用シーンに応じたSPF・PAの数値から選ぶと良いでしょう。特に、レジャーやスポーツのように、長時間にわたり紫外線の強い場所で過ごすときは、数値が高くかつ耐水などの効果も併せて確認してみてください。
紫外線は体内でビタミンDを作るために必要な一方で、浴びすぎは皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。肌のシワやシミといった、美容の観点でのデメリットも少なくありません。紫外線の浴びすぎを避けるために、ご紹介したポイントをぜひ参考にしてみてください。
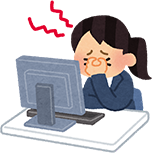
職場でテレワークが導入されたり、学校がオンライン授業に切り替わったりと、2020年以降ライフスタイルに大きな変化があった方もいらっしゃるでしょう。今回は、そんなオンライン化で注意したい目の疲れと、対策についてお伝えします。PCやスマートフォンの活用が必須のオンライン時代、大切な目の健康を守りましょう。
◆オンライン化で実感する目の疲れ
多くの企業でテレワーク(リモートワーク)が導入され、会議やミーティングなどもオンラインで行われるようになりました。また、プライベートでもオンライン上での交流が増えて、PCやスマートフォンの画面を見る時間が増えたと感じる方も多いでしょう。一方で、社会のオンライン化にともない注意したいのが目の疲れです。ライフスタイルが変わって以降、これまで以上に目の疲れを実感することがないでしょうか。特に、デスクワークで長時間にわたり画面を見続けている方は、改めて目の健康に注目してみてください。
◆気をつけたい「VDT症候群」とは?
日常的にPCやスマートフォンのディスプレイを見続けることが多い現代。そんな画面の見すぎによって起こる目の症状は、「VDT症候群(Visual Display Terminal)」と呼ばれています。VDT症候群は、目を酷使することで起こり、慢性化すると全身に症状が見られるのが特徴です。目の疲れや肩こりから始まり、しだいにだるさや背中の痛みが生じ、さらには精神的な症状をまねくと懸念されています。お仕事で画面を見る時間が長い方は、今日から取り組める簡単な対策で、少しでも目の疲れを防ぐ工夫をしてみましょう。
◆目の疲れを防ぐ3つの対策
画面の見すぎで目の疲れを感じるときは、以下の3つの対策をお試しください。今日から自分で取り組める、簡単な対策をご紹介します。
・正しい姿勢を保って作業する
 仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整えましょう。このとき、視線が上向きのまま画面を見続けると目の緊張や乾燥につながるためご注意ください。
仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整えましょう。このとき、視線が上向きのまま画面を見続けると目の緊張や乾燥につながるためご注意ください。
 ・作業中はこまめに休憩を取る
・作業中はこまめに休憩を取る
PCを使って作業をするときは、定期的に休憩を取るよう推奨されています。1時間の作業につき10~15分間の休憩を取るのが目安です。休憩時間には、簡単なストレッチや体操で体を動かしたり、目の周りをやさしくマッサージしたりすると良いでしょう。また、目薬をさしたり、ホットアイマスクで目を温めたりする方法もあります。作業に集中していると、つい休憩がおろそかになるため、意識して目を休める時間を作りましょう。
 ・画面の明るさや色味を調節する
・画面の明るさや色味を調節する
PCのディスプレイは、設定によって自分で明るさや色味を調節することができます。目の負担を抑えたいときは、画面の明るさを下げるとともに、「ブルーライト」と呼ばれる青色の光を下げて対策します。昨今では、多くの端末に「夜間モード」が搭載されており、簡単な操作でブルーライトを調整できるようになりました。ほかにも、画面にブルーライト対策フィルムを貼る方法や、ブルーライトカットのメガネを使う方法があります。
VDT症候群や目の疲れを防ぐ対策についてお伝えしました。オンライン化にともない、ライフスタイルに大きな変化があった方は、改めて目の健康を見直してみましょう。機器の設定を見直したり、市販のアイテムを活用したり、できることから対策を始めてみてください。

 ・ナトリウム (Na)
・ナトリウム (Na) ・クロール(Cl)
・クロール(Cl) ・カリウム(K)
・カリウム(K) ・マグネシウム(Mg)
・マグネシウム(Mg) ・カルシウム(Ca)
・カルシウム(Ca) 普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。
普段の生活をするうえでは、定期的に適量の水分を摂るように心がけていれば何も問題はありません。しかし、大量に汗をかいたときや、風邪や胃腸炎などにかかって嘔吐や下痢の症状があるときなどは注意が必要です。水分とともに電解質も失っていることになるため、水やお茶だけでは適切な水分補給ができているとはいえません。


 季節性うつ病とは、季節性情動障害(SAD)と呼ばれることもある病気で、毎年決まった時期に症状が現れるという特徴があります。日照時間と深いかかわりがあるといわれており、緯度の高い地域ほど多く見られる病気です。日照時間の短くなる秋口から症状が現れ始め、日の長くなる春先になると自然に回復します。このような特徴から「冬季うつ病」と呼ばれることもありますが、雨で日照時間が短くなる梅雨時に発症する場合もあるようです。おもな症状は、気分の落ち込み・体のだるさ・無気力・過眠・過食などが挙げられます。
季節性うつ病とは、季節性情動障害(SAD)と呼ばれることもある病気で、毎年決まった時期に症状が現れるという特徴があります。日照時間と深いかかわりがあるといわれており、緯度の高い地域ほど多く見られる病気です。日照時間の短くなる秋口から症状が現れ始め、日の長くなる春先になると自然に回復します。このような特徴から「冬季うつ病」と呼ばれることもありますが、雨で日照時間が短くなる梅雨時に発症する場合もあるようです。おもな症状は、気分の落ち込み・体のだるさ・無気力・過眠・過食などが挙げられます。 日照時間の少なくなる冬場は、意識的に季節性うつ病の予防に努めましょう。暖かい部屋に閉じこもりがちな冬場だからこそ、気をつけたいポイントをご紹介します。
日照時間の少なくなる冬場は、意識的に季節性うつ病の予防に努めましょう。暖かい部屋に閉じこもりがちな冬場だからこそ、気をつけたいポイントをご紹介します。 冬場は、年末に向けて仕事が忙しくなったり飲み会が増えたり、食生活が乱れる可能性が高い時期といえます。肉や魚などのたんぱく質やビタミン、ミネラルを意識的に摂り、栄養バランスのいい食事を心がけましょう。バランスのいい食生活は、セロトニンの生成を促します。また、ビタミンDは、食事から摂取することも可能です。魚、卵、キノコ類に多く、しらす、アンコウの肝、干しシイタケに多く含まれています。意識的に食事に取り入れてみてください。
冬場は、年末に向けて仕事が忙しくなったり飲み会が増えたり、食生活が乱れる可能性が高い時期といえます。肉や魚などのたんぱく質やビタミン、ミネラルを意識的に摂り、栄養バランスのいい食事を心がけましょう。バランスのいい食生活は、セロトニンの生成を促します。また、ビタミンDは、食事から摂取することも可能です。魚、卵、キノコ類に多く、しらす、アンコウの肝、干しシイタケに多く含まれています。意識的に食事に取り入れてみてください。 適度な運動は、気持ちが前向きになったりストレス解消になったりする効果が期待できます。外に出る機会の少ない方は、できるだけ運動を習慣化してみましょう。特に、太陽の光を浴びながらできる、ウォーキングなどの運動がおすすめです。
適度な運動は、気持ちが前向きになったりストレス解消になったりする効果が期待できます。外に出る機会の少ない方は、できるだけ運動を習慣化してみましょう。特に、太陽の光を浴びながらできる、ウォーキングなどの運動がおすすめです。


 四肢末端型は、手先や足先が冷える典型的な冷え性タイプです。食事量が少ないダイエット中の方や、運動不足によって筋力が低下してしまっている方に多く見られます。体を温めるためのエネルギーが不足しているため末端まで血液が巡らず、手先足先から冷えてしまうのです。しもやけや肌荒れ、月経トラブルを引き起こすことがあります。
四肢末端型は、手先や足先が冷える典型的な冷え性タイプです。食事量が少ないダイエット中の方や、運動不足によって筋力が低下してしまっている方に多く見られます。体を温めるためのエネルギーが不足しているため末端まで血液が巡らず、手先足先から冷えてしまうのです。しもやけや肌荒れ、月経トラブルを引き起こすことがあります。

 家に同居人がいて仕事専用のスペースなどがない場合、同居人の存在がストレスになってしまうことがあります。仕事に集中できなくなったり、電話やオンライン会議中に移動を余儀なくされたり、お互いの生活に支障が出てしまうためです。
家に同居人がいて仕事専用のスペースなどがない場合、同居人の存在がストレスになってしまうことがあります。仕事に集中できなくなったり、電話やオンライン会議中に移動を余儀なくされたり、お互いの生活に支障が出てしまうためです。
 業務的なやり取り以外にも、気軽にコミュニケーションが取る環境を作りましょう。コミュニケーションツールを利用し、相談用や雑談用の部屋などを作るのもおすすめです。業務以外の話ができる機会を設けることで、ストレス緩和や孤独感からの解放などの効果が期待できます。
業務的なやり取り以外にも、気軽にコミュニケーションが取る環境を作りましょう。コミュニケーションツールを利用し、相談用や雑談用の部屋などを作るのもおすすめです。業務以外の話ができる機会を設けることで、ストレス緩和や孤独感からの解放などの効果が期待できます。
 カルダモンは、さわやかな清涼感のある香りが特徴のスパイスです。カレーのなかでも大切なスパイスといわれており、チャイなどにも使用されます。唾液や胃酸の分泌を促し、消化の手助けをしてくれる働きがあるため、夏バテ予防にぴったりです。また、消臭効果もあるため、口臭や汗の臭いが気になりがちな夏におすすめできます。
カルダモンは、さわやかな清涼感のある香りが特徴のスパイスです。カレーのなかでも大切なスパイスといわれており、チャイなどにも使用されます。唾液や胃酸の分泌を促し、消化の手助けをしてくれる働きがあるため、夏バテ予防にぴったりです。また、消臭効果もあるため、口臭や汗の臭いが気になりがちな夏におすすめできます。 クローブは、刺激的な味と香りが特徴のスパイスです。肉の臭み消しや風味付けとして、煮込み料理にも使用されます。胃腸を温める効果があるため、冷えからくる体の不調を解消したり消化を助けたりする効果が期待できます。相性のいいシナモンと組み合わせてホットワインやチャイなどのドリンクにすると、さらに温め効果がアップするためおすすめです。
クローブは、刺激的な味と香りが特徴のスパイスです。肉の臭み消しや風味付けとして、煮込み料理にも使用されます。胃腸を温める効果があるため、冷えからくる体の不調を解消したり消化を助けたりする効果が期待できます。相性のいいシナモンと組み合わせてホットワインやチャイなどのドリンクにすると、さらに温め効果がアップするためおすすめです。
 お家でアロマテラピーを行うには、お好みのアロマオイルと、香りを広げるためのディフューザーやティッシュなどを用意しましょう。ディフューザーやティッシュに数滴のアロマオイルを垂らして香らせるのが、基本の楽しみ方です。
お家でアロマテラピーを行うには、お好みのアロマオイルと、香りを広げるためのディフューザーやティッシュなどを用意しましょう。ディフューザーやティッシュに数滴のアロマオイルを垂らして香らせるのが、基本の楽しみ方です。
 すっきりと気分転換したいリフレッシュのシーンには、「レモン」「ペパーミント」「ユーカリ」などのアロマオイルがおすすめです。爽やかなレモンの香りは柑橘系のなかでも知名度が高く、気持ちを前向きにしてくれます。ペパーミントの香りにはすっとした清涼感があり、鼻の通りを良くするのが特徴です。ユーカリはウッディーな香りで、集中したいときにも適しています。上手に活用して気分を切り替えましょう。
すっきりと気分転換したいリフレッシュのシーンには、「レモン」「ペパーミント」「ユーカリ」などのアロマオイルがおすすめです。爽やかなレモンの香りは柑橘系のなかでも知名度が高く、気持ちを前向きにしてくれます。ペパーミントの香りにはすっとした清涼感があり、鼻の通りを良くするのが特徴です。ユーカリはウッディーな香りで、集中したいときにも適しています。上手に活用して気分を切り替えましょう。
 マスク内は湿度が高いため、一見肌に良さそうに見えます。しかし、過度な湿度は肌にとって好ましいわけではありません。汗や皮脂の分泌が増えたり、雑菌が繁殖しやすくなったりするため、ニキビができやすい環境になっているといえます。汗や皮脂が出やすくなる夏場は、さらなる注意が必要です。
マスク内は湿度が高いため、一見肌に良さそうに見えます。しかし、過度な湿度は肌にとって好ましいわけではありません。汗や皮脂の分泌が増えたり、雑菌が繁殖しやすくなったりするため、ニキビができやすい環境になっているといえます。汗や皮脂が出やすくなる夏場は、さらなる注意が必要です。 肌荒れ予防の基本は、肌を清潔に保つことです。マスク内は、ニキビの原因であるアクネ菌が繁殖しやすい環境といえます。毎日朝晩、たっぷりの泡を使って丁寧に洗顔しましょう。肌の保湿は、肌を外的刺激から守ることにつながるため、季節を問わず重要です。特に、洗顔後は肌の水分が失われやすい状態になっているため、すぐに化粧水・乳液・クリームなどで保湿しましょう
肌荒れ予防の基本は、肌を清潔に保つことです。マスク内は、ニキビの原因であるアクネ菌が繁殖しやすい環境といえます。毎日朝晩、たっぷりの泡を使って丁寧に洗顔しましょう。肌の保湿は、肌を外的刺激から守ることにつながるため、季節を問わず重要です。特に、洗顔後は肌の水分が失われやすい状態になっているため、すぐに化粧水・乳液・クリームなどで保湿しましょう


 昨今の巣ごもり需要を受けて、自治体の公式サイトや動画共有サイトなどで、無料のトレーニング動画が提供されています。動画では目的に応じたトレーニングメニューが用意されており、自宅で効果的に体を動かすために役立ちます。スポーツジムに通うのが難しい方は、動画でプロのトレーナーによる解説を聞くのもひとつの手です。
昨今の巣ごもり需要を受けて、自治体の公式サイトや動画共有サイトなどで、無料のトレーニング動画が提供されています。動画では目的に応じたトレーニングメニューが用意されており、自宅で効果的に体を動かすために役立ちます。スポーツジムに通うのが難しい方は、動画でプロのトレーナーによる解説を聞くのもひとつの手です。
 紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。
紫外線を浴びすぎると、皮膚や目の健康に影響を与えると考えられています。たとえば、紫外線を浴びた数時間後に起こるサンバーンでは、皮膚に炎症が起こって赤みや痛みといった急性傷害が生じることも。また、日焼けのダメージが長年にわたり続くと、肌にシワやシミなどの慢性傷害が現れます。ほかにも皮膚に良性や悪性の腫瘍ができるおそれがあり、目には白内障や翼状片といった病気のリスクがもたらされます。 皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。
皮膚や目の健康を守るためにも、日頃から紫外線の浴びすぎを避けるよう心がけましょう。ここで押さえておきたいのは、すでに日焼けをした後に対策をするより、日焼けをする前に対策をするほうが効果的である点です。外出をするときは、紫外線の強い10~14時の時間帯や、紫外線量の多い環境をできるだけ避けましょう。その際は、できるだけ日陰に入ったり、衣服・帽子・日傘で肌を覆ったりする対策が有効です。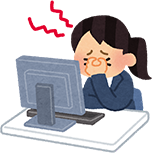
 仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整え
仕事などで長時間にわたり画面を見続けるときは、正しい姿勢を保って作業しましょう。まず、イスに座った状態でディスプレイとは40~50cm程度の距離をとります。背筋を伸ばして画面を見たら、視線の向きをやや下方向にするのが疲れを防ぐポイントです。机とイスの高さを調節して、適切な姿勢でいられるよう作業環境を整え ・作業中はこまめに休憩を取る
・作業中はこまめに休憩を取る ・画面の明るさや色味を調節する
・画面の明るさや色味を調節する