
基礎代謝を上げると、痩せやすくなったり、肌状態が良くなったりといったように、さまざまなメリットがあります。ダイエットをしてもなかなか痩せられない方や、肌の調子が悪い方は、基礎代謝アップに取り組んでみてはいかがでしょうか。こちらでは、基礎代謝を上げるメリットや基礎代謝の上げ方についてお伝えします。
◆基礎代謝とは
基礎代謝とは、心拍や呼吸、体温の安定化といった生命維持のために最低限必要なエネルギーのことです。基礎代謝が高ければ何もしなくてもエネルギーが消費されるため、基礎代謝の向上はダイエットに役立ちます。
体内でもっとも多くエネルギーを消費するのは筋肉です。そのため、基礎代謝を高めるには運動をして筋肉を増やすことが有効だと考えられています。筋肉は年齢とともに落ちていきますが、トレーニングをすれば何歳からでも増やせます。そのため、基礎代謝のアップも何歳からでも可能です。
◆基礎代謝を上げるメリット
基礎代謝を上げるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
メリットのひとつは、前述の通り痩せやすくなることです。運動をしなくても体内の糖質や脂質の分解が行われ、余分なものが溜まりにくくなります。無理な食事制限をしなくても、痩せた状態を維持できます。
肌の調子が良くなるのもメリットです。基礎代謝が上がると、新陳代謝が活発になります。すると、皮膚細胞の置き換わりが早くなり肌状態が整います。新しい皮膚は水分を多く含むため、常に潤った肌状態のキープが可能です。
基礎代謝が上がって血の巡りが良くなると、冷え性や肩こりの改善効果も期待できます。体の末端にある手足は冷えやすくなりますが、血液が行き渡ると温度が上昇します。結果、冷えが改善されるのです。また、血行が促進されると筋肉が柔らかくなるため、肩もこりにくくなります。
体調を崩しやすい方にも基礎代謝の向上はおすすめです。風邪を引きやすかったり、体調を崩しやすかったりする方は、自律神経の調子が良くないと考えられています。基礎代謝が活発になれば、自律神経の不調が改善されて、体調を崩しにくくなります。
◆基礎代謝の上げ方
 基礎代謝を上げるには、次のような方法がおすすめです。
基礎代謝を上げるには、次のような方法がおすすめです。
・継続して運動をする
基礎代謝を上げるには筋肉が重要であるため、適度に運動をしましょう。筋肉は20代を過ぎると徐々に減っていくため、意識して運動して筋肉を増やす必要があります。
ジムに行ったりランニングをしたりする時間を取れない場合は、日常生活に小さな運動を取り入れるだけでも構いません。最寄り駅のひとつ手前で降りたり、エスカレーターよりも階段を使ったりといった工夫をして、運動量を増やしましょう。
・毎日湯船に浸かる
 暑い日は湯船に入らずにシャワーで済ませるという方もいらっしゃいます。しかし、基礎代謝を上げるには湯船に入るのがおすすめです。湯船に浸かって体の奥から温まると、血流が良くなり、老廃物が流れやすくなって新陳代謝が高まります。
暑い日は湯船に入らずにシャワーで済ませるという方もいらっしゃいます。しかし、基礎代謝を上げるには湯船に入るのがおすすめです。湯船に浸かって体の奥から温まると、血流が良くなり、老廃物が流れやすくなって新陳代謝が高まります。
体温が1度上がるごとに基礎代謝は約12%アップします。ぜひ、毎日湯船に浸かって体を温めましょう。
・朝起きてすぐにストレッチをする
朝起きてすぐにストレッチをすると、体に酸素を取り込みやすくなり、代謝が上がりやすくなります。血の巡りも良くなり、すっきり目を覚ませます。
ストレッチは、ベッドに寝たままの状態で行いましょう。仰向けのまま頭の上で両手を組み、両手両足を上下に伸ばします。それから膝を立て、おへそを覗き込むように状態を浮かせてください。
さらに両手を左右に広げ、右足を左側に伸ばしてキープします。終わったら、反対側も行いましょう。最後に四つん這いになってお尻を踵の上に乗せます。その状態で両手を伸ばし、背中をストレッチしてください。
続けると基礎代謝を上げられます。ぜひ毎日行ってみましょう。



 二日酔いしてしまったら、まずは水分を多く取りましょう。お酒には利尿作用がある上に、おつまみには水分を失わせる塩分が多く含まれています。そのため、お酒を飲んだ次の日の体は水分不足になりやすく、頭痛やめまいといったさまざまな不調が起こります。朝起きたら始めに水分をとるようにしてください。
二日酔いしてしまったら、まずは水分を多く取りましょう。お酒には利尿作用がある上に、おつまみには水分を失わせる塩分が多く含まれています。そのため、お酒を飲んだ次の日の体は水分不足になりやすく、頭痛やめまいといったさまざまな不調が起こります。朝起きたら始めに水分をとるようにしてください。 アミノ酸は魚・肉・ご飯、ビタミンB1は豚肉・うなぎ・たらこといった食材に多く含まれます。二日酔いした日はこれらの食材を意識して食べるようにしましょう。
アミノ酸は魚・肉・ご飯、ビタミンB1は豚肉・うなぎ・たらこといった食材に多く含まれます。二日酔いした日はこれらの食材を意識して食べるようにしましょう。
 漢方を使うと効果を感じられる可能性があるのは、次のような症状です。
漢方を使うと効果を感じられる可能性があるのは、次のような症状です。 病気というほどひどくなくても、頭痛や動悸に悩まされる方は少なくありません。漢方薬を使うとホルモン分泌や自律神経のバランスを整える効果ができ、不快な症状を和らげられる可能性があります。
病気というほどひどくなくても、頭痛や動悸に悩まされる方は少なくありません。漢方薬を使うとホルモン分泌や自律神経のバランスを整える効果ができ、不快な症状を和らげられる可能性があります。
 チーズを発酵させるためには青カビや白カビ、鰹節を発酵させるにはカツオブシカビが必要です。また、醤油や味噌を発酵させるために使われる麹菌もカビの一種です。
チーズを発酵させるためには青カビや白カビ、鰹節を発酵させるにはカツオブシカビが必要です。また、醤油や味噌を発酵させるために使われる麹菌もカビの一種です。 乳酸菌には、便秘や肌荒れを引き起こす悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きがあります。免疫力を向上させたい場合におすすめです。ヨーグルト・チーズ・納豆・漬物に含まれています。
乳酸菌には、便秘や肌荒れを引き起こす悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きがあります。免疫力を向上させたい場合におすすめです。ヨーグルト・チーズ・納豆・漬物に含まれています。
 マイタケには、キノコキトサンが多く含まれています。キノコキトサンとは、脂肪の吸収率を抑え、中性脂肪を減らす働きのある成分です。生活習慣病や動脈硬化の予防に役立ちます。また、ビタミンD・ビオチン・ナイアシン・食物繊維も豊富です。
マイタケには、キノコキトサンが多く含まれています。キノコキトサンとは、脂肪の吸収率を抑え、中性脂肪を減らす働きのある成分です。生活習慣病や動脈硬化の予防に役立ちます。また、ビタミンD・ビオチン・ナイアシン・食物繊維も豊富です。 シイタケには、食物繊維・ビタミンD・レンチナン・エリタデニンといった栄養成分が含まれています。シイタケの約40%は食物繊維です。食物繊維の整腸作用で便通が良くなり、肌荒れ防止やダイエットへの効果が期待できます。
シイタケには、食物繊維・ビタミンD・レンチナン・エリタデニンといった栄養成分が含まれています。シイタケの約40%は食物繊維です。食物繊維の整腸作用で便通が良くなり、肌荒れ防止やダイエットへの効果が期待できます。 エノキダケに含まれる主な栄養素は、ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・ビタミンDといったものです。ビタミンDの働きによって骨粗鬆症を予防でき、カルシウムの吸収率が高まります。さらに抗酸化作用があるため、免疫力が強化され、細胞の老化を抑えられます。
エノキダケに含まれる主な栄養素は、ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・ビタミンDといったものです。ビタミンDの働きによって骨粗鬆症を予防でき、カルシウムの吸収率が高まります。さらに抗酸化作用があるため、免疫力が強化され、細胞の老化を抑えられます。
 ラベンダーは「ハーブの女王」とも呼ばれる、もっとも有名なハーブのひとつです。花だけではなく、茎や葉っぱにも高い芳香成分が含まれています。
ラベンダーは「ハーブの女王」とも呼ばれる、もっとも有名なハーブのひとつです。花だけではなく、茎や葉っぱにも高い芳香成分が含まれています。 カモミールは、イギリスではもっとも古くから知られている薬用植物です。主に熱病や婦人病の治療薬として使われてきました。香りはりんごに似ています。
カモミールは、イギリスではもっとも古くから知られている薬用植物です。主に熱病や婦人病の治療薬として使われてきました。香りはりんごに似ています。 ペパーミントは、食品や歯磨き粉によく使われる、もっとも親しまれているハーブのひとつです。世界の幅広い地域で栽培されています。精油の産出量が一番多いのはアメリカですが、イギリス産の精油がもっとも品質的に優れていると考えられています。
ペパーミントは、食品や歯磨き粉によく使われる、もっとも親しまれているハーブのひとつです。世界の幅広い地域で栽培されています。精油の産出量が一番多いのはアメリカですが、イギリス産の精油がもっとも品質的に優れていると考えられています。
 頭が凝ると、健康にさまざまな影響が出ます。そのひとつが睡眠です。人間は十分な睡眠を取ることによって疲労を回復させ、脳を休ませています。しかし、頭が凝っていると、脳が緊張して質の良い睡眠が取れなくなってしまいます。
頭が凝ると、健康にさまざまな影響が出ます。そのひとつが睡眠です。人間は十分な睡眠を取ることによって疲労を回復させ、脳を休ませています。しかし、頭が凝っていると、脳が緊張して質の良い睡眠が取れなくなってしまいます。 頭の凝りを改善するには、マッサージやストレッチ、ツボ押しがおすすめです。頭のケアをして、健康な体を目指しましょう。
頭の凝りを改善するには、マッサージやストレッチ、ツボ押しがおすすめです。頭のケアをして、健康な体を目指しましょう。
 カルシウムが不足すると、骨や歯が弱くなります。高齢者であれば骨粗鬆を招いたり、幼児の場合は骨の発達に影響が出たりするおそれがあります。また、カルシウムは血管の細胞の活動にも影響を与えるため、血圧上昇や血管の老化にも注意が必要です。
カルシウムが不足すると、骨や歯が弱くなります。高齢者であれば骨粗鬆を招いたり、幼児の場合は骨の発達に影響が出たりするおそれがあります。また、カルシウムは血管の細胞の活動にも影響を与えるため、血圧上昇や血管の老化にも注意が必要です。 カルシウムのほかにも不足しがちなのがタンパク質です。タンパク質は、体重1kgあたり1.2~1.4g必要だとされています。体重60kgの方であれば、必要なタンパク質量は72~84gです。しかし、多くの方は必要な分のタンパク質を摂取できていません。
カルシウムのほかにも不足しがちなのがタンパク質です。タンパク質は、体重1kgあたり1.2~1.4g必要だとされています。体重60kgの方であれば、必要なタンパク質量は72~84gです。しかし、多くの方は必要な分のタンパク質を摂取できていません。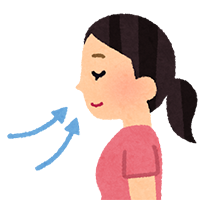
 たとえば、虫歯や歯周病のリスクが上がることです。唾液には、口内の細菌を殺したり、汚れを洗い流したりする働きがあります。しかし、口呼吸をすると口の中が乾燥してしまい、虫歯や歯周病の原因となる菌を取り除きにくくなります。歯の健康を守るためにも、口での呼吸は避けましょう。
たとえば、虫歯や歯周病のリスクが上がることです。唾液には、口内の細菌を殺したり、汚れを洗い流したりする働きがあります。しかし、口呼吸をすると口の中が乾燥してしまい、虫歯や歯周病の原因となる菌を取り除きにくくなります。歯の健康を守るためにも、口での呼吸は避けましょう。 自分が口呼吸をしているかどうか判断できないという方もいらっしゃるかもしれません。口呼吸しているか分からないという方は、以下の点を確認してみましょう。
自分が口呼吸をしているかどうか判断できないという方もいらっしゃるかもしれません。口呼吸しているか分からないという方は、以下の点を確認してみましょう。
 熱中症の方を見つけたら、最初に行うのは意識があるかどうかの確認です。話しかけても返事がなかったり、朦朧として受け答えがおかしかったりする場合は、速やかに病院で診てもらわなければなりません。この処置を誤ると後遺症が残る可能性があり、最悪の場合は死に至ることもあり得ます。病人に意識がないようなら、すぐに救急車を呼びましょう。
熱中症の方を見つけたら、最初に行うのは意識があるかどうかの確認です。話しかけても返事がなかったり、朦朧として受け答えがおかしかったりする場合は、速やかに病院で診てもらわなければなりません。この処置を誤ると後遺症が残る可能性があり、最悪の場合は死に至ることもあり得ます。病人に意識がないようなら、すぐに救急車を呼びましょう。 ただし、お茶やコーヒーのようなカフェインを含む飲み物を飲むと、利尿作用によって反対に水分が失われてしまう可能性があります。熱中症対策には、カフェインの含まれていないものを飲むようにしましょう。
ただし、お茶やコーヒーのようなカフェインを含む飲み物を飲むと、利尿作用によって反対に水分が失われてしまう可能性があります。熱中症対策には、カフェインの含まれていないものを飲むようにしましょう。