|
||||||||
|
|
PTSD(外傷後ストレス障害)とは? | |
|
||
| PTSDにかかるケース | ||
| PTSDは、心的な外傷を受けた後、上記のような症状が数週間から数ヶ月の間に起こり、数年に渡って続く精神障害です。通常ならば衝撃的な出来事を体験した場合でも、時が経つにつれてそのショックや記憶は薄れていくものですが、受けたショックがあまりにも大きすぎる場合などに発症するとみられています。ただし個人差も大きく、同じような体験をした場合でも発症する人としない人がいるように、個人の性格やストレスへの過敏性など、様々な要因が発症に影響していると研究が進められています。また、幼児期など自我の未発達な段階で受けた大きな心的外傷は特に危険性が大きいと考えられ、早期の対応が必要とされています。
PTSDの重症度には大きな幅があり、比較的軽症のものから重症のものまで、患者によって様々です。大災害や大事故でなくても、家庭や学校、会社内など日常生活をとりまく環境のなかで受けた心的外傷が発端となることもあり、昨年も大きく取り上げられていた「いじめ」問題も重要な要因のひとつと言われています。 |
||
| 治療について | ||
| 現在のところ、主な治療は薬物療法と心理療法です。睡眠障害や過敏症状などには抗不安薬、抑うつ症状には抗うつ薬などが用いられ、心理療法ではカウンセリングを中心に体験を言葉にする行動療法などが行われています。しかし、多くの患者は、原因となった体験を思い出したくないがために、それについて語るのを避ける傾向があり、周囲からの協力や理解を得にくいという問題点があります。誰かに話して相談できる態勢づくり、また、周囲がその人を心理的に支えていくことが治療の第一歩です。
医療機関では、精神科・心療内科が本症の診療に当たっています。 |
||
|
||


 PTSDとはPost-traumatic Stress Disorderの略称で、戦争や自然災害、事故、家庭内暴力や性的虐待など、自分自身や身近な人の生命や身体に脅威となる外傷的な出来事を経験した後に長く続く心身の病的反応を指します。日本では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件に関連して大きく取り上げられ、注目されるようになりました。
PTSDとはPost-traumatic Stress Disorderの略称で、戦争や自然災害、事故、家庭内暴力や性的虐待など、自分自身や身近な人の生命や身体に脅威となる外傷的な出来事を経験した後に長く続く心身の病的反応を指します。日本では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件に関連して大きく取り上げられ、注目されるようになりました。 「骨粗しょう症」とは、骨を構成するカルシウム不足が原因で骨の密度が減り、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。現在日本では約5,000万人もの患者がいると言われ、高齢の女性に特に多い病気でもあります。
「骨粗しょう症」とは、骨を構成するカルシウム不足が原因で骨の密度が減り、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。現在日本では約5,000万人もの患者がいると言われ、高齢の女性に特に多い病気でもあります。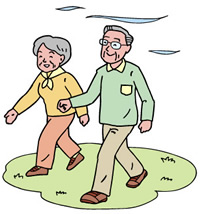 ○生活編
○生活編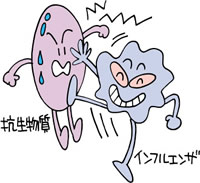 インフルエンザと風邪は、そもそも原因となるウィルスの種類が違います。インフルエンザは高熱が出るだけでなく、筋肉や関節の痛みなど全身に出る症状が強く、気管支炎や肺炎を併発しやすいなどの特徴があり、抵抗力のない乳幼児や高齢者にとっては生命にかかわる危険も。また、突然大流行することもある、恐ろしい病気です。
インフルエンザと風邪は、そもそも原因となるウィルスの種類が違います。インフルエンザは高熱が出るだけでなく、筋肉や関節の痛みなど全身に出る症状が強く、気管支炎や肺炎を併発しやすいなどの特徴があり、抵抗力のない乳幼児や高齢者にとっては生命にかかわる危険も。また、突然大流行することもある、恐ろしい病気です。 「風が吹いただけで痛い」ほど足の関節が痛む病気、として知られる痛風。ある日突然足の親指の付け根が腫れ、立ち上がれないほどの痛みが発作的に起こります。この発作はたいていの場合1週間ほどで治まりますが、半年から1年の期間を経てまた同じような痛みが起こり、繰り返すうちに足首や膝の関節まで広がってくるように。怖いのは、この痛みと併行して内臓が侵されていくこと。間接の強烈な痛みだけでなく、腎臓などの内臓にも障害が起こってしまう病気と覚えておきましょう。
「風が吹いただけで痛い」ほど足の関節が痛む病気、として知られる痛風。ある日突然足の親指の付け根が腫れ、立ち上がれないほどの痛みが発作的に起こります。この発作はたいていの場合1週間ほどで治まりますが、半年から1年の期間を経てまた同じような痛みが起こり、繰り返すうちに足首や膝の関節まで広がってくるように。怖いのは、この痛みと併行して内臓が侵されていくこと。間接の強烈な痛みだけでなく、腎臓などの内臓にも障害が起こってしまう病気と覚えておきましょう。 痛風を防ぐには、尿酸値を下げることが大切。それには尿酸のもとになるプリン体という物質を減らすのが第一です。
痛風を防ぐには、尿酸値を下げることが大切。それには尿酸のもとになるプリン体という物質を減らすのが第一です。
 私たちの体の中には無数の細菌が棲息しています。細菌と聞くと、なんだか体に悪いもののように感じますが、常在菌と呼ばれるこの細菌たちは、病原菌など身体へ有害な菌の進入や増殖を防ぐ大切なもの。その中で、腸内に棲息する細菌を腸内細菌と呼びます。
私たちの体の中には無数の細菌が棲息しています。細菌と聞くと、なんだか体に悪いもののように感じますが、常在菌と呼ばれるこの細菌たちは、病原菌など身体へ有害な菌の進入や増殖を防ぐ大切なもの。その中で、腸内に棲息する細菌を腸内細菌と呼びます。 強いストレスは腸の蠕動(ぜんどう)運動をコントロールする自律神経中枢にも影響を及ぼし、便秘や下痢を引き起こす要因となります。不規則な便通は腸内細菌のバランスを崩し、善玉菌を減らして悪玉菌を増殖させてしまいます。
強いストレスは腸の蠕動(ぜんどう)運動をコントロールする自律神経中枢にも影響を及ぼし、便秘や下痢を引き起こす要因となります。不規則な便通は腸内細菌のバランスを崩し、善玉菌を減らして悪玉菌を増殖させてしまいます。
 よく理想の睡眠時間は「1日8時間」と言われますが、実はこれには医学的根拠はありません。多くの人の睡眠時間が6~9時間程度という統計から出された平均値に過ぎず、また、この平均値も年々減少傾向にあるようです。国民生活時間調査(2000年NHK調べ)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間23分で、年代別に見ると30代が6時間57分、40代が6時間59分と、働き盛りの年代に特に睡眠時間が短いという現象が見られます。
よく理想の睡眠時間は「1日8時間」と言われますが、実はこれには医学的根拠はありません。多くの人の睡眠時間が6~9時間程度という統計から出された平均値に過ぎず、また、この平均値も年々減少傾向にあるようです。国民生活時間調査(2000年NHK調べ)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間23分で、年代別に見ると30代が6時間57分、40代が6時間59分と、働き盛りの年代に特に睡眠時間が短いという現象が見られます。
 テレビCMなどでご存知の方も多いと思いますが、水虫は一種のカビ。皮膚糸状菌という一種のカビによって生じる感染症を言い、多くは白癬菌というカビが原因です。高温多湿を好むカビの特性と、皮膚のたんぱく質(ケラチン)を栄養源とする性質があるため、足の裏や足指の間などが「住みやすい場所」となるようです。
テレビCMなどでご存知の方も多いと思いますが、水虫は一種のカビ。皮膚糸状菌という一種のカビによって生じる感染症を言い、多くは白癬菌というカビが原因です。高温多湿を好むカビの特性と、皮膚のたんぱく質(ケラチン)を栄養源とする性質があるため、足の裏や足指の間などが「住みやすい場所」となるようです。 ●皮膚科での診断
●皮膚科での診断 ストレス潰瘍とは、胃潰瘍(十二指腸潰瘍も含む)の中でも、ストレスの影響が強いもののことで、多発性な上、再発しやすいという特徴をもっています。潰瘍の大きさや深さは様々で、同時にいくつもの潰瘍ができるケースも珍しくありません。
ストレス潰瘍とは、胃潰瘍(十二指腸潰瘍も含む)の中でも、ストレスの影響が強いもののことで、多発性な上、再発しやすいという特徴をもっています。潰瘍の大きさや深さは様々で、同時にいくつもの潰瘍ができるケースも珍しくありません。 うつ病で特徴的なのは、「憂うつ感」「無気力・無関心」などの心の症状。うつ病とは、気分が落ち込み、これまで楽しんでいたことや好きだったものに興味がなくなり、楽しめなくなる病気なのです。それに加え、「疲れやすい」「眠れない」「頭痛がする」などちょっとした体の不調もうつが原因のことがあります。厚生労働省の報告によると、日本人の15人に1人はうつになる可能性があるといわれており、身近な病気としても注意が必要です。
うつ病で特徴的なのは、「憂うつ感」「無気力・無関心」などの心の症状。うつ病とは、気分が落ち込み、これまで楽しんでいたことや好きだったものに興味がなくなり、楽しめなくなる病気なのです。それに加え、「疲れやすい」「眠れない」「頭痛がする」などちょっとした体の不調もうつが原因のことがあります。厚生労働省の報告によると、日本人の15人に1人はうつになる可能性があるといわれており、身近な病気としても注意が必要です。 「疲れやすい」「頭痛が続く」といった体の不調も、うつが原因の場合があります。特に、診察は受けたけど原因が分からない場合などは、注意が必要です。「調子が悪いな」と感じながらも、我慢すれば済んでしまう程度の場合は、本人も周囲の人もそれがうつであると気付きにくいものです。以下のような症状が2週間以上続くような場合は、うつを疑ってみましょう。
「疲れやすい」「頭痛が続く」といった体の不調も、うつが原因の場合があります。特に、診察は受けたけど原因が分からない場合などは、注意が必要です。「調子が悪いな」と感じながらも、我慢すれば済んでしまう程度の場合は、本人も周囲の人もそれがうつであると気付きにくいものです。以下のような症状が2週間以上続くような場合は、うつを疑ってみましょう。
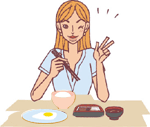 人間の体は、1日の24時間を1サイクルとして、体を構成する組織や臓器がリズムを保って活動しています。そのリズムの基となるのは太陽の光で、その明るさや暗さが脳の中枢神経を刺激し、活動を弱めたり強めたりして体の働きを調節するのです。また、食事を摂ることも神経系を刺激する作用があり、血液中の栄養成分の濃度を高めて、組織や内臓の働きを活発にします。
人間の体は、1日の24時間を1サイクルとして、体を構成する組織や臓器がリズムを保って活動しています。そのリズムの基となるのは太陽の光で、その明るさや暗さが脳の中枢神経を刺激し、活動を弱めたり強めたりして体の働きを調節するのです。また、食事を摂ることも神経系を刺激する作用があり、血液中の栄養成分の濃度を高めて、組織や内臓の働きを活発にします。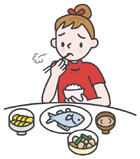 さて、朝ごはんが大切なことは分かっていても、忙しい現代人はなかなか朝ごはんを食べられないという実態があります。あるアンケート調査では、独身でひとり暮らしの女性の場合、朝食を毎日きちんと摂ると答えた人はなんと全体の半数以下という結果でした。
さて、朝ごはんが大切なことは分かっていても、忙しい現代人はなかなか朝ごはんを食べられないという実態があります。あるアンケート調査では、独身でひとり暮らしの女性の場合、朝食を毎日きちんと摂ると答えた人はなんと全体の半数以下という結果でした。