
テレビや雑誌などでよく取り上げられるリンパマッサージ。しかし、具体的にどういうものなのか分からない人も多いのでは?リンパは老廃物の除去や健康的な肌作りに重要な役割を担っていますが、滞りやすいという欠点も。そこで、リンパの働きをよくするためのマッサージが重要なのです。ここでは、リンパマッサージの詳しい効能と、自宅でやるときの注意点についてご紹介します。
◆リンパとは?
リンパとは、血液と同じように体中に存在するものです。全身に張り巡らされているのがリンパ管。その中を流れている血しょうの一部で、リンパ管に吸収されたのがリンパ液。そして、全身の要所にある、リンパ管が合流している部分をリンパ節と呼びます。これらを総称したものがリンパです。リンパの働きは、老廃物の回収と排泄、細菌の退治など。また、ウイルスなどへの抗体を作ったり、異物や細菌を除去したり、健康を維持するうえでさまざまな機能を備えています。
血管と同じように体中に張り巡らされているリンパですが、その役割は全く異なります。血管が酸素と栄養を運ぶのに対して、リンパ管は不要物を運ぶごみ箱のような存在です。また、血液は心臓をポンプとして自動的に全身に流れてきますが、リンパは筋肉の動きによって自発的に流れています。そのため、リンパの停滞は運動不足の人に多く見られます。
リンパマッサージは、溜まった老廃物を流して、体のリンパの流れを改善するマッサージです。不要物がなくなれば、健康や美容にさまざまな効果が期待できます。
◆便秘、冷え症、ダイエットに効果を発揮
まずは便秘。痛みがないので油断しがちですが、お通じが悪いと頭痛や食欲不振、肩こりや腰痛の引き金になることがあり、見逃せない症状です。便秘とリンパには密接な関係があるので、マッサージで改善できる可能性があります。腸回りのリンパに刺激を加えると、腸の働きが活性化されて、排便が促されるのです。便秘解消が目的の人は、腰回りと下腹部のマッサージを行いましょう。
 冷え症の人にもリンパマッサージは効果的です。冷え症は慢性化すると、ホルモンバランスが崩れて老化を早めたり、免疫力を低下させたりするなど、さまざまな問題を起こします。リンパマッサージは、下半身を重点にし、広い範囲で定期的に行うことが有効です。ふくらはぎや足裏、足首などをマッサージしましょう。休憩時間などにぜひ試してみてください。
冷え症の人にもリンパマッサージは効果的です。冷え症は慢性化すると、ホルモンバランスが崩れて老化を早めたり、免疫力を低下させたりするなど、さまざまな問題を起こします。リンパマッサージは、下半身を重点にし、広い範囲で定期的に行うことが有効です。ふくらはぎや足裏、足首などをマッサージしましょう。休憩時間などにぜひ試してみてください。
ダイエットにも効果が期待できるかもしれません。リンパマッサージをすると、リンパの流れだけでなく、血液の流れもよくできます。体が活発になり、基礎代謝が上がるので、痩せやすい体が作れるでしょう。また、マッサージでリンパの流れを良くすれば、老廃物が外に流れてむくみを取ることができるので、見た目が痩せて見えることも。体型が気になる方は、ぜひトライしてみましょう。
◆セルフマッサージの注意点
 リンパの流れはとても穏やかなので、あまり早くマッサージしてはいけません。心臓から出て行ったリンパ液がまた心臓に戻ってくるまでには12~24時間かかります。血液は1周40秒程なので、比べるとリンパの流れはとても遅いことが分かります。リンパ液は1秒で1センチほどしか進まないので、リンパマッサージはゆっくりと一定の速度で行うのが理想的です。
リンパの流れはとても穏やかなので、あまり早くマッサージしてはいけません。心臓から出て行ったリンパ液がまた心臓に戻ってくるまでには12~24時間かかります。血液は1周40秒程なので、比べるとリンパの流れはとても遅いことが分かります。リンパ液は1秒で1センチほどしか進まないので、リンパマッサージはゆっくりと一定の速度で行うのが理想的です。
また、早く効果を出したいからといって、強くし過ぎてもいけません。リンパ液は皮膚の表面近くを流れているので、くれぐれも強い力で押さないように。あまり強く押しすぎると、逆にむくみや血行障害を引き起こす恐れがあります。1か所の所要時間は10~15分が目安です。一度にたくさんやらずに、こまめに行って毎日続けましょう。
リンパマッサージは病院の治療とは違うので、一度に劇的な効果が出るものではありませんが、続けると体質改善につながります。無理せずこまめに続けましょう。あまり力は入れず、さするようなマッサージを心がけてくださいね。
サ ッカーにラクビー、マラソンと、冬はスポーツ真っ盛りのシーズンでもあります。体を動かす選手達には必要なくても、観戦する側が心がけたいのが、防寒対策。心は熱い気持ちでぬくもっても、体は冷たい空気と風にさらされて、体温の低下を招きます。そこで今回は、冬のスポーツ観戦で体を壊さないための防寒対策をご紹介します。
ッカーにラクビー、マラソンと、冬はスポーツ真っ盛りのシーズンでもあります。体を動かす選手達には必要なくても、観戦する側が心がけたいのが、防寒対策。心は熱い気持ちでぬくもっても、体は冷たい空気と風にさらされて、体温の低下を招きます。そこで今回は、冬のスポーツ観戦で体を壊さないための防寒対策をご紹介します。
◆冬のスポーツ観戦で気をつけたいこと
冬といえば、空気が乾燥して寒気が一段と厳しくなるため、感染症の原因となるウィルスが活発になるシーズンです。ウィルスは乾燥した空気を好むといわれますが、それは湿度が低くなるとウィルスの水分が蒸発して軽くなり、空気中に浮いて大量に飛散してしまうからです。
気温が下がると人の体温も低下し、ウィルスに対する抵抗力もダウンしてしまいます。風邪を引いた1人がくしゃみや咳をして空気中に大量のウィルスを飛散させると、周囲にあっという間に伝播してしまいます。小中学校や高校、職場など、人が多く集まる環境ではとくに注意が必要なのです。
スポーツ観戦の場所も、不特定多数の人たちが集まり、気づかないうちにウィルスを吸い込んだり、拡散させたりする怖れがあります。例えばサッカーなどの野外スポーツは2時間近く、寒風の中同じ場所に着席して観戦する必要があります。しっかり身を守るための防寒対策・風邪予防対策を事前に準備することが大切です。
◆晴れの日の防寒対策
冬の野外スポーツを観戦するときの防寒3点セットは、「帽子」「耳当て」「マスク」です。肌が露出してしまいがちな顔や頭部などをしっかり防御する上で、帽子と耳当ては必須アイテムですね。また、マスクは風邪をうつしたり、うつされたりしないための風邪予防対策用のものを使用するようにしましょう。
 また、首周りをしっかりガードするためのマフラーやストールなども、防寒対策として効果的。首や手首、足首を温めるだけで、体感温度が4度もあがるといわれています。首が冷えてしまうと周囲の筋肉へも悪影響が出ますので、厚手のマフラーもまた欠かせない防寒アイテムです。
また、首周りをしっかりガードするためのマフラーやストールなども、防寒対策として効果的。首や手首、足首を温めるだけで、体感温度が4度もあがるといわれています。首が冷えてしまうと周囲の筋肉へも悪影響が出ますので、厚手のマフラーもまた欠かせない防寒アイテムです。
首から上の部分をしっかり温めることが防寒上の大切なポイントですが、全身の着こなしに気を配ることも忘れてはいけません。
・上半身はとにかく厚着で守る
おすすめは、ヒートテックなど機能性に優れた上着を着ることです。その上は、風を通さないポリエステル素材のオーバーなどでしっかり防御します。インナーは、ハイネックのロングTシャツなどを最低1枚は合わせ着したいですね。屋根の付いたスタジアム観戦でも、冬場は相当気温が下がりますので、ちょっと暑いくらいの着こなしでのぞむのがベストです。
・下半身は、インナー準備がポイント
下半身も2重・3重の防寒対策をしてのぞんでください。こちらもヒートテックなどの機能性インナーは欠かせません。冷え症の多い女性は、膝掛け用のブランケットなどを準備しておくとなおいいですね。履物はブーツなど、しっかり足元がカバーできるものがおすすめ。できれば靴用カイロなども準備して、冷えやすい足先を温めるようにしましょう。
◆雨・雪の日の防寒対策
 サッカーの試合などは、雨や雪が降っても中止になることはありませんので、天候に左右されない防寒を心がけることも大切です。気をつけて欲しいのが、サッカー観戦での傘使用。基本的に、スポーツ観戦での傘の利用は周りの迷惑となり、マナー違反にあたります。天候が思わしくないときは、レインコートの持参を忘れないようにしましょう。
サッカーの試合などは、雨や雪が降っても中止になることはありませんので、天候に左右されない防寒を心がけることも大切です。気をつけて欲しいのが、サッカー観戦での傘使用。基本的に、スポーツ観戦での傘の利用は周りの迷惑となり、マナー違反にあたります。天候が思わしくないときは、レインコートの持参を忘れないようにしましょう。
また、フード付きジャンパーやコートなどがあると、冷たい雨から頭部を守ることができます。仮に頭が濡れたとしても、タオルなどを準備して水分が残らないようにしっかり拭き取るようにしてください。
冬のスポーツ観戦も、健康な体あってこそはじめて楽しめます。好きなスポーツを見て充実した1日を過ごした後も、元気に学校や職場に行けるよう、万全の防寒対策を心がけてくださいね。
 冬になり、寒さが厳しくなると、風邪やインフルエンザなど怖い病のリスクが高まります。喘息もその中の一つ。喘息といえば、乾燥した空気が大敵ですが、警戒すべきはそれだけではありません。“エアコンの汚れ”という意外なところにも注意する必要があるのです。
冬になり、寒さが厳しくなると、風邪やインフルエンザなど怖い病のリスクが高まります。喘息もその中の一つ。喘息といえば、乾燥した空気が大敵ですが、警戒すべきはそれだけではありません。“エアコンの汚れ”という意外なところにも注意する必要があるのです。
◆冬に注意したい咳喘息
単なる風邪とも思えないような咳が続くと、それは咳喘息かもしれません。喘息は、気道が狭くなり、外部からのさまざまな刺激に対して敏感になることで、炎症や咳の発作を引き起こす症状です。
喘息持ちの方も、風邪を引いたことがきっかけで体調を崩し、喘息の症状を悪化させる人もいます。喘息持ちでない方でも、ダニやホコリなどを吸い込んだことがきっかけで喘息を引き起こすこともあります。症状がひどくなる気管支喘息を発症するケースもあるので、注意が必要です。
急激な気温の低下や、空気の乾燥だけでなく、ダニやホコリの原因となる不衛生な環境にも気を配る必要があるでしょう。
◆手入れをしないエアコンはこんなに危険!
 夏になると、急激に増えるといわれるカビ肺炎。これは、手入れをしないエアコンのカビが原因で咳の症状に悩まされ、発熱や倦怠感も伴う病気です。エアコンのカビが原因で起こる症状はそれ以外にも、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などが挙げられます。
夏になると、急激に増えるといわれるカビ肺炎。これは、手入れをしないエアコンのカビが原因で咳の症状に悩まされ、発熱や倦怠感も伴う病気です。エアコンのカビが原因で起こる症状はそれ以外にも、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などが挙げられます。
秋が終わり、暖房に切り替えるタイミングにも気をつける必要があるでしょう。使わなくなった暖房の裏側は自然とホコリがたまり、不衛生な状態になっています。そのままの状態で作動させると、部屋中にホコリやダニが蔓延し、それを吸い込んだ喘息持ちの子どもが気管支喘息を発症させる危険性も考えられるのです。
◆家庭でもできるエアコン掃除
エアコンのホコリによる喘息を防止するには、できる範囲でエアコンのクリーニングをするのが効果的です。「フィルター」と「吹き出し口」の清掃は、家庭でも簡単にできるので、その方法を紹介します。
・フィルターの掃除法
フィルターを掃除する前に、フィルター回りやエアコンのパネル部分のホコリを掃除機で吸い取ります。ホコリが降ってくるかもしれませんので、マスクを着用してしっかり防護しましょう。ホコリはフィルターの外側についているので、外側に掃除機をかけて重点的にホコリを吸い取ります。内側からかけてしまうと逆にフィルターの目にホコリが詰まってしまいますので、必ず外側から掃除機をかけるようにしてください。その後、シャワーできれいに水洗いして日陰干しにします。
・吹き出し口の掃除方法
吹き出し口が汚れていてはここから出てくる風に汚れた空気やホコリが乗って部屋中に蔓延してしまいます。手順としては、吹き出し口のルーバーを外した後、中性洗剤を染みこませたタオルで中をしっかり拭いていきます。届かないときは、細長い棒にタオルを絡ませて奥まできれいに磨きましょう。その後、きれいなタオルで拭き上げるようにしてください。
気をつけて欲しいのは、市販のスプレー。市販の洗浄スプレーは、間違って使うとエアコンの故障にもつながります。使用方法を確認したうえで、注意して使うようにしてください。
◆プロに任せる方法もアリ
 最近では、家庭用のエアコンも、自分で無理に行わず、エアコンクリーニングの専門業者に任せるという人もいます。電気製品であるエアコンを掃除中に壊してしまうといったトラブルは少なくありません。とくに、吹き出し口のルーバーを外す操作が分からず、無理をして外すと故障にもつながります。自信のない方はプロに任せるのがベストです。
最近では、家庭用のエアコンも、自分で無理に行わず、エアコンクリーニングの専門業者に任せるという人もいます。電気製品であるエアコンを掃除中に壊してしまうといったトラブルは少なくありません。とくに、吹き出し口のルーバーを外す操作が分からず、無理をして外すと故障にもつながります。自信のない方はプロに任せるのがベストです。
また、プロであれば手の届かない場所でも専用の器具を用いてしっかり洗浄してもらえます。きちんとホコリや汚れが取り除かれないまま、エアコンを動かして喘息を悪化させてしまえば元も子もありません。万全を期したい方は、無理をせずプロの業者に任せることをおすすめします。

楽しかった夏のあとは、スポーツと食欲の秋の到来です。いつもより食欲が進む分、ダイエット目的で颯爽とランニング、という方も多いでしょう。そこで気をつけたいのが、屋外での運動に欠かせない紫外線対策。直射日光は肌に悪いばかりか、さまざまな病や症状のリスクも考えられます。そこで今回は、紫外線から目を守ることの大切さと、スポーツに適したサングラス選びのポイントを説明します。
◆紫外線対策は目を守ることから
紫外線対策といっても、「帽子や日焼けクリームがあるから大丈夫」と思っていませんか?欧米では紫外線カットが目的で使われるサングラスも、日本ではまだ“ファッション目的”というイメージが抜けきれません。目を日光から守ることには、どんな意味があるのでしょうか?
お肌の大敵ともいえるシミやソバカス。これは、角膜を通して吸収された紫外線によって脳が反応し、メラニン色素の形成を促すことで発生します。メラニンは紫外線から肌を守ってくれる大切な物質ですが、嫌なシミを作り出す原因にもなるのです。
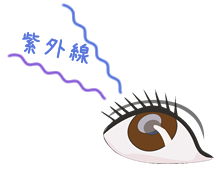 そして、目を守る組織である角膜や水晶体が紫外線を浴びると、「目の日焼け」とよばれる症状を引き起こします。具体的には、目の充血や乾燥、涙の分泌、目の異物感など。日常的にそんな状態が続けば、長期にわたって有害な成分が水晶体に蓄積され、白内障の原因にもなるのです。重度の病のリスクから身を守るためにも、スポーツ中のサングラス着用は大前提といえるでしょう。
そして、目を守る組織である角膜や水晶体が紫外線を浴びると、「目の日焼け」とよばれる症状を引き起こします。具体的には、目の充血や乾燥、涙の分泌、目の異物感など。日常的にそんな状態が続けば、長期にわたって有害な成分が水晶体に蓄積され、白内障の原因にもなるのです。重度の病のリスクから身を守るためにも、スポーツ中のサングラス着用は大前提といえるでしょう。
◆UVカットのサングラスを選ぼう
目に紫外線を当て続けることによって、白内障の他、黄斑変性(おうはんへんせい)や瞼裂班(けんれつはん)、翼状片など、さまざまな眼病のリスクも高まります。つまり、サングラスを使用することで、シミやソバカス、日焼けを防ぐばかりか、深刻な眼病を防止することにもつながるのです。
しかし、サングラスであればどれでもいいというわけではありません。紫外線カットに効果のあるレンズでなければ、角膜や目の周囲の肌を紫外線から守ることはできないでしょう。では、どのようにして紫外線カットにすぐれたサングラスを選べばいいのでしょうか。それは、紫外線を吸収する割合を示した「紫外線透過率」で判断します。
 この透過率が低ければ低いほど、そのサングラスはUVカットの性能にすぐれたレンズということになるでしょう。紫外線透過率が1.0%以下であれば、紫外線は99%カットできるといわれます。UVカットのサングラスの中には、紫外線透過率を表示したものも販売されていますので、ランニングなどのスポーツ用には透過率の低いサングラスの使用をお勧めします。
この透過率が低ければ低いほど、そのサングラスはUVカットの性能にすぐれたレンズということになるでしょう。紫外線透過率が1.0%以下であれば、紫外線は99%カットできるといわれます。UVカットのサングラスの中には、紫外線透過率を表示したものも販売されていますので、ランニングなどのスポーツ用には透過率の低いサングラスの使用をお勧めします。
◆スポーツに適したサングラスの条件
スポーツにふさわしいサングラスの条件として、UVカットに効果のあることの他、以下のポイントを抑えると、より快適にランニングなどのスポーツに専念できるでしょう。
・顔にフィットしている
体を動かしている最中にグラグラとサングラスが動いては運動に集中できないでしょう。顔にフィットしたサングラスであれば、ストレスを感じることなく、心地よい気分でスポーツに専心できます。顔のサイズや骨格に合ったサングラスをチョイスするようにしましょう。
・黒いレンズは避けよう
真っ黒なレンズのサングラスはいかにもおしゃれで格好良い印象を与えますが、黒いレンズは透過率も悪く、紫外線対策として適当ではありません。また、目の瞳孔が広がったり、視界が悪くなったりと、目にも負担がかかります。ファッション性や好みにこだわりすぎず、黒いものや色の濃いレンズのサングラスは極力避けるようにしてください。
スポーツをするにも、まずは準備が大切です。まだまだ強い直射日光も残る秋の始まりの中、ランニングや球技をするときは、目を守ってくれるUVカットのサングラスを選ぶのが大切。それをスタートに、スポーツの秋を満喫しましょう。
夏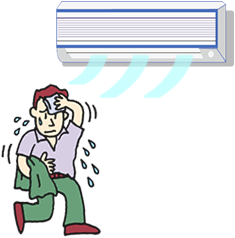 の暑さに負けて、つい冷房を強めに設定してしまう。そんな毎日をお過ごしのあなたに注意してほしいのが、冷え症です。冷え症は冬にこそ多い症状として知られますが、エアコンの効き過ぎた部屋で過ごすと、女性ばかりか男性が冷え症になるケースも。冷房を付けない日はない、というこの時期こそ、冷え症に対する理解と対策が必要です。
の暑さに負けて、つい冷房を強めに設定してしまう。そんな毎日をお過ごしのあなたに注意してほしいのが、冷え症です。冷え症は冬にこそ多い症状として知られますが、エアコンの効き過ぎた部屋で過ごすと、女性ばかりか男性が冷え症になるケースも。冷房を付けない日はない、というこの時期こそ、冷え症に対する理解と対策が必要です。
◆夏の冷え症の原因
熱い夏の盛りに、エアコンは欠かせません。しかし、ガンガンに冷えた部屋にずっといると、自分では気づかないうちに、体の中で変調が起きてしまいます。自律神経の乱れから来る冷え症がそれです。
気温も上昇する季節になると、私たちの体は血管を広げることで体内に蓄積された熱を外に放出させます。この時、働くのが副交感神経。しかし、エアコンからの冷風を浴びて体が冷えると、交感神経が働いて血管を収縮させ、熱が外へ逃げないように働きます。この2つの自律神経の逆作用によって血流が悪くなり、体の冷えを起こしてしまうのです。この状態が続くと自律神経の機能が低下、体温の調節も困難となり、夏場に限らず、年間を通して冷え症に悩まされることになります。
◆男女問わず増えてきた冷え症
・女性の冷え性
冷え症といえば女性が多いのが特徴です。なぜ女性に多いのかといえば、脂肪に対して筋肉が少ないという、体の構造上の問題があります。
脂肪は、一旦体が冷えると体の中に抱えこんでしまうという特徴をもっています。逆に筋肉は、熱を発生しやすい特質をもっていて、脂肪より筋肉の多い男性は冷えに強いという体質です。このような体の仕組み上の違いにより、冷え症に悩まされる女性が多いといえるでしょう。

・男性の冷え症
しかし最近では、男性の冷え症も増えています。それを誘発するのが夏のエアコンです。自分たちの体は冷えやすいということを知っているため、女性は冷房の効いた部屋でも厚手の服を着てしっかりと対策をとります。
それに対し、男性は冷房による冷え症に対しては無防備です。先述したように、筋肉の多い男性は熱に弱いため、ついエアコンを強めに設定しまいがちです。さらに、女性のように冷え性に対する理解不足のため、先ほど説明した自律神経の乱れを起こして冷え症を引き起こしてしまうのです。冷え症は、決して男性も無縁ではないことを知る必要があるでしょう。
◆冷房による冷え症を防ぐには
冷房による冷え症を防ぐには、室内の温度設定に気を配り、冷房から身を守る服装で対策をとりましょう。以下にその方法をご紹介します。
・設定温度は25℃前後を目安に
まず、室内温度に気を配りましょう。理想的なエアコンの設定温度は、「外の気温マイナス3℃~4℃」です。しかし、それでも体で冷えを感じたら、温度を上げるなど調整してください。また、ずっとエアコンをつけた状態はよくありませんので、適度に外に出て外気に触れたり、窓を開けて外の空気を取り入れたりするなど、体がエアコンに慣れすぎないよう注意しましょう。

・お腹や足首を冷やさない
冷房の効いた部屋の中で過ごすとき、体の特定部分を極度に冷やさないことが大切です。とくにお腹や下半身を冷やさないよう、座っているときは膝掛けをし、お腹には腹巻きなどを当てると効果的。お腹を温めると全体の体温が上昇するので、腹巻きは冷房対策に有効といえるでしょう。
・軽いストレッチ
仕事の合間、オフィスでできる軽いストレッチもまた、冷え症対策に効果的です。例えば手のストレッチ。まず、左右の手のひらをクロスして組み合わせます。そして右手で左手を外側へ反らし、3秒間待ちましょう。左右組み替えても同じことをやります。この行為を5回繰り返すだけで、冷え症を防ぎ、適度な体温維持につながるでしょう。
夏に欠かせない冷房も、頼りすぎると体調に大きな変化を及ぼします。体が本来もっている機能を失わないためにも、日常の生活でできる冷房対策をしっかり立てることで、健康体のまま夏を乗り切ってください。
 激しい日照りが降り注ぐこの時期、特に注意したいのが熱中症。水分を奪われ急激な体調不良に襲われるこの症状は、幼児や高齢者などの年齢層が多くかかると言われています。しかし、最近では野外で部活動に励む中高生が熱中症で倒れ、救急車で搬送されるという事例も。熱中症は、暑い夏では誰にでも起こりえる症状だと用心し、必要な対策を立てるようにしましょう。
激しい日照りが降り注ぐこの時期、特に注意したいのが熱中症。水分を奪われ急激な体調不良に襲われるこの症状は、幼児や高齢者などの年齢層が多くかかると言われています。しかし、最近では野外で部活動に励む中高生が熱中症で倒れ、救急車で搬送されるという事例も。熱中症は、暑い夏では誰にでも起こりえる症状だと用心し、必要な対策を立てるようにしましょう。
◆「古典的熱中症」と「労作性熱中症」
熱中症とは、体内外の熱の影響により、体温調節や発汗量のコントロール機能が失われ、めまいやけいれん、顔面蒼白、失神など、さまざまな体の不調を引き起こす症状です。その熱中症は、大きく分けて2つに分けられます。
・古典的熱中症
体の外からの熱によって体調不良が起きる熱中症です。夏になると気温が上昇し、体内温度にも影響をおよぼします。猛暑の期間が何日も続くと、熱波とよばれる現象が起き、高齢者や乳幼児が発症しやすくなります。その中でもなりやすいのは、心臓病・腎臓病・糖尿病などの持病を持っている方など。また、野外の車の中で乳幼児が発症するケースもこれにあたります。
・労作性熱中症
暑い環境の中で激しく体を動かしたり、太陽の降り注ぐ中で作業や労働に従事したりした時に起こりやすい熱中症です。若くて健康な人でも、一度に大量の汗をかいて水分が失われると臓器障害などを引き起こします。
最近とくに多くなったのが、後者の労作性熱中症です。ラクビー選手など、屈強な体格を持つ若者ですら、熱中症にかかって死亡するという例が増えています。労作性熱中症は、その多くがスポーツ・労働する環境や、その方法が原因で発生しているといえます。酷暑の中で体を動かす際は、環境面やルール作りなどを重視し、熱中症対策を立てる必要があります。
◆スポーツ環境で注意したいこと
野外でスポーツする場合、どんな環境でのぞめばいいのでしょうか。以下にまとめてみましたので、参考にしてください。
・常に温度計を準備し、35℃以上になれば屋内へ
 35℃以上で体を激しく動かすことは熱中症のリスクを高めるため、基本的には避けましょう。そのため、指導者の方は常に温度計をにらみながら管理することを怠らないでください。また、1日の中でも比較的涼しい朝や夕方でも熱中症は発症します。日照りの強い日中の時間だけ注意するのではなく、朝練習や日の沈んだ時間帯でも運動量と温度には気を配るようにしましょう。
35℃以上で体を激しく動かすことは熱中症のリスクを高めるため、基本的には避けましょう。そのため、指導者の方は常に温度計をにらみながら管理することを怠らないでください。また、1日の中でも比較的涼しい朝や夕方でも熱中症は発症します。日照りの強い日中の時間だけ注意するのではなく、朝練習や日の沈んだ時間帯でも運動量と温度には気を配るようにしましょう。
・急激な温度差に注意
熱中症の多くは、7・8月をピークに発生します。しかし、体が暑さに馴れきっていない梅雨明けや、暑さのぶり返しのある9月など、意外な時期に体調の変化を訴えるケースも目立ちます。それまでと比べ温度差を実感したときは、急激な運動は避け、徐々にペースを上げていくのがポイントです。
◆スポーツ中に気をつけること
次に紹介するのは、スポーツ中に心がける注意点。いずれも簡単に始められることなので、忘れずに実行するように努めてください。
・水分をしっかり補給
 「水分が足りてないな……」と自分の中で感じたら、無理をせず水分を補給するようにしましょう。その時、微量の塩分を含ませると回復に効果的です。スポーツドリンクの飲料でも適度の糖分を含ませるなど、成分含有量にも気を配ってください。ちなみにスポーツドリンクは100ml中40~80mlのナトリウムが適量といわれます。
「水分が足りてないな……」と自分の中で感じたら、無理をせず水分を補給するようにしましょう。その時、微量の塩分を含ませると回復に効果的です。スポーツドリンクの飲料でも適度の糖分を含ませるなど、成分含有量にも気を配ってください。ちなみにスポーツドリンクは100ml中40~80mlのナトリウムが適量といわれます。
・いきなりハードに動かない
運動に慣れた選手でも、急に体を動かすのはよくありません。熱中症が危ぶまれる中でのスポーツは特に、「体を暑さに慣らす」ことを意識するようにしてください。体力差や運動能力には個人差がありますので、周囲のペースについて行けない場合は、無理をせず申告してできるだけ自分のペースでトレーニングを行うようにしましょう。また、暑さに体が慣れてくると水分も多く失われるため、スポーツドリンクなど補給は多めに取るのが肝心です。
運動中に起きる労作性熱中症は、暑さと体力、運動量の管理をしっかり行えば防げます。若いからといって油断せず、対策をしっかり立てて心置きなく好きなスポーツに励みましょう。
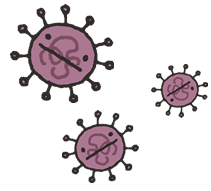
ジメジメとした梅雨時期は湿気のせいもあってか体もベタベタ。なんだか気持ちもスッキリしなくて、ついついダラダラと過ごしてはいませんか?しかし、この時期になると人間よりも活発に動き出す生き物がいます。それが“菌”です。今回は、特に食中毒を引き起こす菌についてご紹介し、合わせてその予防法についてもお伝えします。おっくうだからと言って対策を怠ると大変なことになる可能性もありますので、注意しましょう。
◆菌の種類
食中毒を引き起こす菌にはさまざまなものがあります。以下で、その代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
○病原性大腸菌
その名の通り、腸に生息する細菌です。有名なところではO157が挙げられます。媒介となる食品は魚介類や肉類など多岐にわたります。
○サルモネラ菌
地球上のさまざまな場所に生息するサルモネラ菌。特に夏場に流行する傾向にあり、免疫力の弱い幼児や高齢者などが発症しやすくなっています。特に鶏肉や鶏卵には注意が必要です。
○ボツリヌス菌
ボツリヌス菌の作り出す毒素は致死率が30%を超え、その威力は自然界の中でも最強とも言われています。また、食品原材料の汚染を防止するのは難しいので、菌の増殖をいかにおさえるかがポイントとなります。
○黄色ブドウ球菌
ニキビの原因菌としても知られている黄色ブドウ球菌。私たちの身近にある菌ですが、食品に付着し、体内に取り込まれると大変危険です。おにぎりなど、手や指で触れて作る料理の前には、手洗いを徹底しましょう。
○腸炎ビブリオ
主に海産の魚介類に生息する腸炎ビブリオ。刺身や寿司など、魚介類を生で食べるような料理が媒介になることが多いです。塩に含まれると増殖が活発になるのも特徴です。
◆予防の基本と心構え
食中毒を防止するためには、食材の適切な調理・保存が大切です。以下で、梅雨時期~夏場にかけて特に気をつけておきたいポイントをご紹介します。
○なんと言っても加熱が大切
食中毒を防ぐには加熱が効果的です。それぞれの菌によって死滅する温度と時間は異なりますが、ほとんどの菌は75℃で1分間の加熱を行っておけば問題ありません。ただし、二枚貝などの食材に関してはノロウィルスの心配があるので85~90℃で1分30秒以上の加熱を行いましょう。
 ○自然解凍は厳禁
○自然解凍は厳禁
お肉や魚などを解凍する場合は、常温による自然解凍はしないでください。冷蔵庫でじっくり時間をかけて溶かしていくか、急ぎの場合は流水にさらしながら行いましょう。
○食材によって保存温度を変える
生食用の食品は4℃以下。加熱調理をする食材は10℃以下での保存を徹底してください。また買い物から帰ったら、早めに冷蔵庫へ食材をしまう習慣をつけましょう。大切なのは、食べ物を常温のまま放置しないことです。
○常温保存OKでも油断は大敵
常温保存が許可されている食材であっても、高温の場所に長時間置かれたり、直射日光を浴び続けたりすると傷みが出る他、菌の繁殖につながる場合があります。できるだけ風通しが良く、涼しい場所で保管するようにしましょう。
◆もちろん清掃もしっかりと!
 食中毒を防ぐには、調理・保存だけでなく毎日のキッチン清掃も大切です。普段からしっかりお手入れをするのはもちろん、梅雨時期~夏場にかけてはいつもより念入りな清掃を心がけてみてください。
食中毒を防ぐには、調理・保存だけでなく毎日のキッチン清掃も大切です。普段からしっかりお手入れをするのはもちろん、梅雨時期~夏場にかけてはいつもより念入りな清掃を心がけてみてください。
また、タワシやスポンジなどの道具も、古くなったら積極的に取り替えるようにしましょう。この時期は、洗剤がついてキレイだと思われがちなこうした道具が菌の温床になりやすいです。その他、電子レンジの内部やカトラリー容器、食器棚なども菌が溜まりやすい場所なので、念入りなお手入れを欠かさないようにしてください。
 若い女性を中心に大人気のアイメイク。鮮やかで華やかなその姿からは、目の周囲をきれいに、またはかわいらしく魅せるための工夫と努力が垣間見られます。しかし、その方法には危険な落とし穴も隠れていることを知らなければなりません。そこで今回は、行きすぎたアイメイクがもたらす病や症状と、その具体的な対策、また目の性質と周辺部分の働きについて詳しくご説明します。健やかな生活の中で気持ちよくメイクを続けていただくためにも、ぜひご一読ください。
若い女性を中心に大人気のアイメイク。鮮やかで華やかなその姿からは、目の周囲をきれいに、またはかわいらしく魅せるための工夫と努力が垣間見られます。しかし、その方法には危険な落とし穴も隠れていることを知らなければなりません。そこで今回は、行きすぎたアイメイクがもたらす病や症状と、その具体的な対策、また目の性質と周辺部分の働きについて詳しくご説明します。健やかな生活の中で気持ちよくメイクを続けていただくためにも、ぜひご一読ください。
◆目の周りのメイクには、こんな危険がある
目の縁を際立たせるアイライン。その手法は、アイシャドーを目の内側に深く濃く入れ、美しさを引き立たせるといったものです。特に、目をぱっちり大きく魅せるためのアイラインは、「インサイドライン」と呼ばれ、まつ毛の生え際の奥や、粘膜の部分まで色をつけていきます。ここまで深くラインを入れると、化粧品の成分が目に入ったり、粘膜に付着したりするなどのリスクも考えられます。
 また、まつ毛の上から人工のまつ毛を付け足していく「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」にも、トラブルの元になるリスクが潜んでいるので注意が必要です。まつ毛エクステとは、美容師の資格を持つ施術者が専用の接着剤を使ってまつ毛を貼り付けていく手法のこと。経験のある女性ならこの施術がいかに高度な技術が必要か、お分かりでしょう。
また、まつ毛の上から人工のまつ毛を付け足していく「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」にも、トラブルの元になるリスクが潜んでいるので注意が必要です。まつ毛エクステとは、美容師の資格を持つ施術者が専用の接着剤を使ってまつ毛を貼り付けていく手法のこと。経験のある女性ならこの施術がいかに高度な技術が必要か、お分かりでしょう。
まつ毛エクステは、まぶたから1~2ミリの間隔でまつ毛を取り付けていきますので、難易度の高さから施術の失敗による被害やトラブルなどが多数報告されています。国民生活センターによると、まつ毛エクステを経験した女性のうち、4人に1人が目やその周辺などに痛みやかゆみなどの異常を訴えたとのことです。
◆アイメイクするときに注意したいマイボーム腺
次に、目の周辺にある機能やその働きについてご説明します。私たちの目は、通常、油脂成分の保護膜がかかっており、この機能が涙の蒸発を防ぎ、一定の水分を保っているといえます。
この眼球を覆う保護膜は、マイボーム腺とよばれるまつ毛の生え際にある器官によって形成されます。マイボーム腺には数十個の分泌腺があり、そこから油脂成分が分泌されるという仕組みです。
しかし、この部分に不純物などが入って穴がふさがれると、涙の蒸発を防ぐ油脂の供給がストップしてしまいます。これがドライアイの原因となり、目の渇きや充血などの症状に見舞われるのです。
アイメイクでまつ毛の内側にアイラインやアイシャドーを施すと、マイボーム腺に化粧品の成分が付着し、油分を分泌するという重要な働きが損なわれることになってしまいます。ドライアイから目を守るには、まつ毛の内側までメイクを施すようなきわどい手法は避け、できるだけ外側部分にとどめるよう注意してください。
◆誰でも簡単にできる目のケア
 最後に、手軽にできる目のケアについてもお伝えしておきましょう。目の働きに重要なマイボーム腺のケアポイントは、目を温め、清潔を保つことです。この方法は、入浴の際のシャワーを浴びるときに試すと効果的。目を閉じて、まぶたの上から適温のシャワーをあててください。温めた後、軽くまぶたをマッサージするとより効果的です。この際、目を痛めないようやりすぎには注意して、やさしくほぐすようにしましょう。
最後に、手軽にできる目のケアについてもお伝えしておきましょう。目の働きに重要なマイボーム腺のケアポイントは、目を温め、清潔を保つことです。この方法は、入浴の際のシャワーを浴びるときに試すと効果的。目を閉じて、まぶたの上から適温のシャワーをあててください。温めた後、軽くまぶたをマッサージするとより効果的です。この際、目を痛めないようやりすぎには注意して、やさしくほぐすようにしましょう。
◆アイメイクは、目を痛めない範囲で
目とはとてもデリケートで、過敏な器官です。そこに化粧品など、化学成分の入った異物が混入すれば、大変な事態になることは想像に難くありません。美しいメイクも、健康な体があってこそ生きるもの。目の働きと病のリスクに留意して、健全なメイクアップを心がけましょう。

現在、ドラッグストアを覗くと実にさまざまな種類のシャンプーが棚に並んでいます。しかし、「どれが自分の頭皮に合っているのか?」というのはなかなか分からないもの。そこで今回は、ご自身の頭皮のタイプの調べ方と、その結果を基にしたシャンプーの選び方についてご紹介します。「今使っているシャンプーが、本当に自分に合っているのか知りたい」「フケやかゆみが出ているので、シャンプーを見直したい」という方は、ぜひ参考にしてみましょう。
◆まずは自分の頭皮のタイプを知りましょう
一口に頭皮と言っても、人それぞれに実はタイプというものが異なります。ちょっと脂っぽかったり、乾燥しがちだったり。シャンプー選びをする場合には、まずこの頭皮タイプを把握することが大切です。とは言え、手で触った程度では自分がどのタイプなのかは分かりません。そこで、以下の手順に沿って、自分の頭皮の状態を確認してみましょう。
 ■Step1:
■Step1:
まずは一日シャンプーをしない状態で過ごします。なお、この日だけは、整髪料をつけるのを控えてください。
■Step2:
両手をお椀のような形に丸めて、指の腹を頭皮につけてください。
■Step3:
指を使って頭皮を揉み込むように動かします。
■Step4:
頭皮から指を離し、指の腹を確認します。
もしも指の腹がベタベタと脂っぽくなっている方は「オイリータイプ」。人より皮脂が出やすい体質です。逆に、脂がほとんどつかない方は「乾燥タイプ」と言えます。なお、多少脂っぽいといった程度の方は「通常タイプ」に分類されます。
◆タイプ別・オススメシャンプー
 それでは、前述のチェック結果を踏まえたうえで、それぞれの方にオススメなシャンプーをご紹介していきます。
それでは、前述のチェック結果を踏まえたうえで、それぞれの方にオススメなシャンプーをご紹介していきます。
【オイリータイプ】
比較的皮脂の分泌が多いオイリータイプの方は、フケやかゆみが出やすいという傾向にあります。そのため、普通のシャンプーよりも効果の強い専用のシャンプーを使ったほうが良いかも知れません。ケースにもよりますが、医薬部外品の薬品シャンプーを利用すると、さっぱり清潔な頭皮が維持できます。ただし、石油系や高級アルコール系の界面活性剤が含まれているシャンプーだと洗浄力が強すぎて、必要な脂まで取り除いてしまうことがあります。この場合、より皮脂の分泌が大きくなる原因にもつながりますので注意しましょう。
【乾燥タイプ】
頭皮が乾燥しやすいタイプの方の場合は、シャンプーで脂を過剰に落とす必要はありません。むしろ脂が不足気味になる可能性もあるので、オイリータイプのシャンプーを選ぶほうが良いケースもあります。なお、フケやかゆみが気になる方は、弱めの界面活性剤が含まれたシャンプーを使うと改善が期待できるでしょう。これで効果がない場合は、「ホホバオイル」を使った頭皮マッサージをシャンプー前に行ったり、頭皮ローションをシャンプー後に付けたりすることで、乾燥を防ぎいでください。
【通常タイプ】
基本的にはアミノ酸系や天然素材由来の植物系シャンプーを使っておけば問題ありません。フケやかゆみが気になる際は、乾燥タイプ同様、シャンプーを替えたり、シャンプー前後にオイルやローションを使ったりすることで改善できることもあります。
◆シャンプー選びの注意点
自分の頭皮のタイプが分かり、それぞれに適したシャンプーを用意できたら、あとはそれを1週間程度使ってみて、自分に合っているかどうかを確認しましょう。どんなに相性がいいと言われているものであっても、実際に使ってみなくてはその効果は分かりません。また、感じ方はその日の体調によっても異なるものなので、できるだけ調子の良いときの感触を信じるようにしましょう。1週間ほど使ってみて「自分に合っているな」「フケやかゆみがなくなってきたな」と思ったら、そのまま使い続けてOKです。また、少しでも異変を感じたらすぐに使用を止めてくださいね。
 「コーヒーを飲むと高血圧症になるよ」といった噂を聞いたことはありませんか?確かに以前まで、コーヒーと高血圧症には密接な関係性があると考えられていました。しかし、近年の研究によると、こうした症状が起こる可能性は低く、むしろ血圧を下げてくれる場合がある、ということが分かってきています。
「コーヒーを飲むと高血圧症になるよ」といった噂を聞いたことはありませんか?確かに以前まで、コーヒーと高血圧症には密接な関係性があると考えられていました。しかし、近年の研究によると、こうした症状が起こる可能性は低く、むしろ血圧を下げてくれる場合がある、ということが分かってきています。
そこで今回は、コーヒーと高血圧症の関係について紹介するとともに、摂取する際にはどのようなことに気をつけるべきか?また、どんな症状が起こったら飲むのをやめるべきか?といった話題をお伝えします。大好きなコーヒーを安心して楽しむために、ぜひご覧ください。
◆「コーヒーは高血圧のもと」という噂について
まずは、なぜ「コーヒーを飲み過ぎると高血圧になる」という噂が広まっていたのかについて解説しましょう。これは、コーヒーに含まれるカフェインに理由があります。カフェインは刺激物です。そのため、摂取すると交感神経が優位に働くようになり、血圧上昇につながるのです。
受験勉強や残業などで、眠気覚ましや気合いを入れるためにコーヒーを飲んだ経験のある方も多いでしょう。気分が高まったり、やる気が出たりすることにつながるのは、こうしたカフェインの作用が理由です。しかし、そのせいで「コーヒー=高血圧症」という噂が広まってしまった、と考えられます。
◆コーヒーと高血圧症に関する研究結果
 では果たして、本当にコーヒーを飲み過ぎると高血圧になるのでしょうか。実は、このことについて調査した研究がアメリカで行われています。
では果たして、本当にコーヒーを飲み過ぎると高血圧になるのでしょうか。実は、このことについて調査した研究がアメリカで行われています。
ある施設で高血圧症の約3万人の助成に12年間、コーヒーの摂取を習慣的に行ってもらい、それに伴う血圧上昇を調査したというこの研究。その結果はなんと、ほとんどの人にコーヒーと高血圧症の関連性が認められなかったのだとか。それだけでなく、なんと高血圧症になるリスクが低下した、という傾向についても分かったそうです。
「でも、これは外人の話でしょ?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。実は、こうした研究は日本でも行われています。
その研究は、飲酒習慣のある20~79歳の男性を対象に行われました。彼らをいくつかのグループに分け、コーヒーと高血圧症について調べた結果、なんとコーヒーを飲んだグループのほうが高血圧症の人の割合が少なかったそうです。
こうした事例を見てみると、コーヒーが高血圧症の原因になるとは考えられません。さらに言えば、高血圧症の予防に効果があるかもしれない、とも予想されます。なお、その理由のひとつに挙げられるのが、コーヒー豆に含まれるクロロゲン酸と呼ばれるポリフェノール。これには、血圧を下げる作用があるのだそうです。
◆飲み過ぎには十分ご注意ください
 前項の結果を見ると、「コーヒーは高血圧症の予防につながるから、どんどん飲むべき」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それには少し注意が必要です。
前項の結果を見ると、「コーヒーは高血圧症の予防につながるから、どんどん飲むべき」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それには少し注意が必要です。
どんなものでも、摂りすぎは良くありません。特に缶コーヒーには大量の砂糖が入っているものが多いため、飲み過ぎると肥満の原因になります。結果、血圧上昇を引き起こす可能性もあるので十分注意しましょう。また、カフェインの過剰摂取も基本的には厳禁。「カフェイン中毒」という言葉もあるくらいですから、飲み過ぎには注意が必要です。1日1~2杯程度が適量とされていますので、その分量を守りましょう。
なお、カフェインの過剰摂取によって以下のような症状が現れると非常に危険、と言われています。心当たりのある方は、コーヒーを飲む習慣について見直したほうが良いかもしれません。
- 胸がドキドキして、心拍数が上がる
- 胸焼けがしてくる
- 不安感が泊まらない
- 集中力がなくなって、考えがまとまらなくなる
- まぶたや筋肉にけいれんが起こる
- 手や指が震え出す
- 頭痛に見舞われる
- 喉が異常に乾く
- 寝つきが悪くなってくる
- 幻聴、幻覚が出る
コーヒーは決して健康に害を及ぼすものではありません。適量であれば、むしろ健やかな生活を後押ししてくれます。飲み過ぎには注意して、良い香りを楽しみながら愛飲するようにしましょう。

 冷え症の人にもリンパマッサージは効果的です。冷え症は慢性化すると、ホルモンバランスが崩れて老化を早めたり、免疫力を低下させたりするなど、さまざまな問題を起こします。リンパマッサージは、下半身を重点にし、広い範囲で定期的に行うことが有効です。ふくらはぎや足裏、足首などをマッサージしましょう。休憩時間などにぜひ試してみてください。
冷え症の人にもリンパマッサージは効果的です。冷え症は慢性化すると、ホルモンバランスが崩れて老化を早めたり、免疫力を低下させたりするなど、さまざまな問題を起こします。リンパマッサージは、下半身を重点にし、広い範囲で定期的に行うことが有効です。ふくらはぎや足裏、足首などをマッサージしましょう。休憩時間などにぜひ試してみてください。 リンパの流れはとても穏やかなので、あまり早くマッサージしてはいけません。心臓から出て行ったリンパ液がまた心臓に戻ってくるまでには12~24時間かかります。血液は1周40秒程なので、比べるとリンパの流れはとても遅いことが分かります。リンパ液は1秒で1センチほどしか進まないので、リンパマッサージはゆっくりと一定の速度で行うのが理想的です。
リンパの流れはとても穏やかなので、あまり早くマッサージしてはいけません。心臓から出て行ったリンパ液がまた心臓に戻ってくるまでには12~24時間かかります。血液は1周40秒程なので、比べるとリンパの流れはとても遅いことが分かります。リンパ液は1秒で1センチほどしか進まないので、リンパマッサージはゆっくりと一定の速度で行うのが理想的です。

 ッカーにラクビー、マラソンと、冬はスポーツ真っ盛りのシーズンでもあります。体を動かす選手達には必要なくても、観戦する側が心がけたいのが、防寒対策。心は熱い気持ちでぬくもっても、体は冷たい空気と風にさらされて、体温の低下を招きます。そこで今回は、冬のスポーツ観戦で体を壊さないための防寒対策をご紹介します。
ッカーにラクビー、マラソンと、冬はスポーツ真っ盛りのシーズンでもあります。体を動かす選手達には必要なくても、観戦する側が心がけたいのが、防寒対策。心は熱い気持ちでぬくもっても、体は冷たい空気と風にさらされて、体温の低下を招きます。そこで今回は、冬のスポーツ観戦で体を壊さないための防寒対策をご紹介します。 また、首周りをしっかりガードするためのマフラーやストールなども、防寒対策として効果的。首や手首、足首を温めるだけで、体感温度が4度もあがるといわれています。首が冷えてしまうと周囲の筋肉へも悪影響が出ますので、厚手のマフラーもまた欠かせない防寒アイテムです。
また、首周りをしっかりガードするためのマフラーやストールなども、防寒対策として効果的。首や手首、足首を温めるだけで、体感温度が4度もあがるといわれています。首が冷えてしまうと周囲の筋肉へも悪影響が出ますので、厚手のマフラーもまた欠かせない防寒アイテムです。 サッカーの試合などは、雨や雪が降っても中止になることはありませんので、天候に左右されない防寒を心がけることも大切です。気をつけて欲しいのが、サッカー観戦での傘使用。基本的に、スポーツ観戦での傘の利用は周りの迷惑となり、マナー違反にあたります。天候が思わしくないときは、レインコートの持参を忘れないようにしましょう。
サッカーの試合などは、雨や雪が降っても中止になることはありませんので、天候に左右されない防寒を心がけることも大切です。気をつけて欲しいのが、サッカー観戦での傘使用。基本的に、スポーツ観戦での傘の利用は周りの迷惑となり、マナー違反にあたります。天候が思わしくないときは、レインコートの持参を忘れないようにしましょう。 冬になり、寒さが厳しくなると、風邪やインフルエンザなど怖い病のリスクが高まります。喘息もその中の一つ。喘息といえば、乾燥した空気が大敵ですが、警戒すべきはそれだけではありません。“エアコンの汚れ”という意外なところにも注意する必要があるのです。
冬になり、寒さが厳しくなると、風邪やインフルエンザなど怖い病のリスクが高まります。喘息もその中の一つ。喘息といえば、乾燥した空気が大敵ですが、警戒すべきはそれだけではありません。“エアコンの汚れ”という意外なところにも注意する必要があるのです。 夏になると、急激に増えるといわれるカビ肺炎。これは、手入れをしないエアコンのカビが原因で咳の症状に悩まされ、発熱や倦怠感も伴う病気です。エアコンのカビが原因で起こる症状はそれ以外にも、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などが挙げられます。
夏になると、急激に増えるといわれるカビ肺炎。これは、手入れをしないエアコンのカビが原因で咳の症状に悩まされ、発熱や倦怠感も伴う病気です。エアコンのカビが原因で起こる症状はそれ以外にも、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などが挙げられます。 最近では、家庭用のエアコンも、自分で無理に行わず、エアコンクリーニングの専門業者に任せるという人もいます。電気製品であるエアコンを掃除中に壊してしまうといったトラブルは少なくありません。とくに、吹き出し口のルーバーを外す操作が分からず、無理をして外すと故障にもつながります。自信のない方はプロに任せるのがベストです。
最近では、家庭用のエアコンも、自分で無理に行わず、エアコンクリーニングの専門業者に任せるという人もいます。電気製品であるエアコンを掃除中に壊してしまうといったトラブルは少なくありません。とくに、吹き出し口のルーバーを外す操作が分からず、無理をして外すと故障にもつながります。自信のない方はプロに任せるのがベストです。
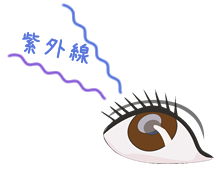 そして、目を守る組織である角膜や水晶体が紫外線を浴びると、「目の日焼け」とよばれる症状を引き起こします。具体的には、目の充血や乾燥、涙の分泌、目の異物感など。日常的にそんな状態が続けば、長期にわたって有害な成分が水晶体に蓄積され、白内障の原因にもなるのです。重度の病のリスクから身を守るためにも、スポーツ中のサングラス着用は大前提といえるでしょう。
そして、目を守る組織である角膜や水晶体が紫外線を浴びると、「目の日焼け」とよばれる症状を引き起こします。具体的には、目の充血や乾燥、涙の分泌、目の異物感など。日常的にそんな状態が続けば、長期にわたって有害な成分が水晶体に蓄積され、白内障の原因にもなるのです。重度の病のリスクから身を守るためにも、スポーツ中のサングラス着用は大前提といえるでしょう。 この透過率が低ければ低いほど、そのサングラスはUVカットの性能にすぐれたレンズということになるでしょう。紫外線透過率が1.0%以下であれば、紫外線は99%カットできるといわれます。UVカットのサングラスの中には、紫外線透過率を表示したものも販売されていますので、ランニングなどのスポーツ用には透過率の低いサングラスの使用をお勧めします。
この透過率が低ければ低いほど、そのサングラスはUVカットの性能にすぐれたレンズということになるでしょう。紫外線透過率が1.0%以下であれば、紫外線は99%カットできるといわれます。UVカットのサングラスの中には、紫外線透過率を表示したものも販売されていますので、ランニングなどのスポーツ用には透過率の低いサングラスの使用をお勧めします。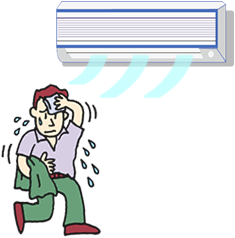 の暑さに負けて、つい冷房を強めに設定してしまう。そんな毎日をお過ごしのあなたに注意してほしいのが、冷え症です。冷え症は冬にこそ多い症状として知られますが、エアコンの効き過ぎた部屋で過ごすと、女性ばかりか男性が冷え症になるケースも。冷房を付けない日はない、というこの時期こそ、冷え症に対する理解と対策が必要です。
の暑さに負けて、つい冷房を強めに設定してしまう。そんな毎日をお過ごしのあなたに注意してほしいのが、冷え症です。冷え症は冬にこそ多い症状として知られますが、エアコンの効き過ぎた部屋で過ごすと、女性ばかりか男性が冷え症になるケースも。冷房を付けない日はない、というこの時期こそ、冷え症に対する理解と対策が必要です。

 激しい日照りが降り注ぐこの時期、特に注意したいのが熱中症。水分を奪われ急激な体調不良に襲われるこの症状は、幼児や高齢者などの年齢層が多くかかると言われています。しかし、最近では野外で部活動に励む中高生が熱中症で倒れ、救急車で搬送されるという事例も。熱中症は、暑い夏では誰にでも起こりえる症状だと用心し、必要な対策を立てるようにしましょう。
激しい日照りが降り注ぐこの時期、特に注意したいのが熱中症。水分を奪われ急激な体調不良に襲われるこの症状は、幼児や高齢者などの年齢層が多くかかると言われています。しかし、最近では野外で部活動に励む中高生が熱中症で倒れ、救急車で搬送されるという事例も。熱中症は、暑い夏では誰にでも起こりえる症状だと用心し、必要な対策を立てるようにしましょう。 35℃以上で体を激しく動かすことは熱中症のリスクを高めるため、基本的には避けましょう。そのため、指導者の方は常に温度計をにらみながら管理することを怠らないでください。また、1日の中でも比較的涼しい朝や夕方でも熱中症は発症します。日照りの強い日中の時間だけ注意するのではなく、朝練習や日の沈んだ時間帯でも運動量と温度には気を配るようにしましょう。
35℃以上で体を激しく動かすことは熱中症のリスクを高めるため、基本的には避けましょう。そのため、指導者の方は常に温度計をにらみながら管理することを怠らないでください。また、1日の中でも比較的涼しい朝や夕方でも熱中症は発症します。日照りの強い日中の時間だけ注意するのではなく、朝練習や日の沈んだ時間帯でも運動量と温度には気を配るようにしましょう。 「水分が足りてないな……」と自分の中で感じたら、無理をせず水分を補給するようにしましょう。その時、微量の塩分を含ませると回復に効果的です。スポーツドリンクの飲料でも適度の糖分を含ませるなど、成分含有量にも気を配ってください。ちなみにスポーツドリンクは100ml中40~80mlのナトリウムが適量といわれます。
「水分が足りてないな……」と自分の中で感じたら、無理をせず水分を補給するようにしましょう。その時、微量の塩分を含ませると回復に効果的です。スポーツドリンクの飲料でも適度の糖分を含ませるなど、成分含有量にも気を配ってください。ちなみにスポーツドリンクは100ml中40~80mlのナトリウムが適量といわれます。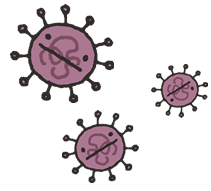
 ○自然解凍は厳禁
○自然解凍は厳禁 食中毒を防ぐには、調理・保存だけでなく毎日のキッチン清掃も大切です。普段からしっかりお手入れをするのはもちろん、梅雨時期~夏場にかけてはいつもより念入りな清掃を心がけてみてください。
食中毒を防ぐには、調理・保存だけでなく毎日のキッチン清掃も大切です。普段からしっかりお手入れをするのはもちろん、梅雨時期~夏場にかけてはいつもより念入りな清掃を心がけてみてください。 若い女性を中心に大人気のアイメイク。鮮やかで華やかなその姿からは、目の周囲をきれいに、またはかわいらしく魅せるための工夫と努力が垣間見られます。しかし、その方法には危険な落とし穴も隠れていることを知らなければなりません。そこで今回は、行きすぎたアイメイクがもたらす病や症状と、その具体的な対策、また目の性質と周辺部分の働きについて詳しくご説明します。健やかな生活の中で気持ちよくメイクを続けていただくためにも、ぜひご一読ください。
若い女性を中心に大人気のアイメイク。鮮やかで華やかなその姿からは、目の周囲をきれいに、またはかわいらしく魅せるための工夫と努力が垣間見られます。しかし、その方法には危険な落とし穴も隠れていることを知らなければなりません。そこで今回は、行きすぎたアイメイクがもたらす病や症状と、その具体的な対策、また目の性質と周辺部分の働きについて詳しくご説明します。健やかな生活の中で気持ちよくメイクを続けていただくためにも、ぜひご一読ください。 また、まつ毛の上から人工のまつ毛を付け足していく「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」にも、トラブルの元になるリスクが潜んでいるので注意が必要です。まつ毛エクステとは、美容師の資格を持つ施術者が専用の接着剤を使ってまつ毛を貼り付けていく手法のこと。経験のある女性ならこの施術がいかに高度な技術が必要か、お分かりでしょう。
また、まつ毛の上から人工のまつ毛を付け足していく「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」にも、トラブルの元になるリスクが潜んでいるので注意が必要です。まつ毛エクステとは、美容師の資格を持つ施術者が専用の接着剤を使ってまつ毛を貼り付けていく手法のこと。経験のある女性ならこの施術がいかに高度な技術が必要か、お分かりでしょう。 最後に、手軽にできる目のケアについてもお伝えしておきましょう。目の働きに重要なマイボーム腺のケアポイントは、目を温め、清潔を保つことです。この方法は、入浴の際のシャワーを浴びるときに試すと効果的。目を閉じて、まぶたの上から適温のシャワーをあててください。温めた後、軽くまぶたをマッサージするとより効果的です。この際、目を痛めないようやりすぎには注意して、やさしくほぐすようにしましょう。
最後に、手軽にできる目のケアについてもお伝えしておきましょう。目の働きに重要なマイボーム腺のケアポイントは、目を温め、清潔を保つことです。この方法は、入浴の際のシャワーを浴びるときに試すと効果的。目を閉じて、まぶたの上から適温のシャワーをあててください。温めた後、軽くまぶたをマッサージするとより効果的です。この際、目を痛めないようやりすぎには注意して、やさしくほぐすようにしましょう。
 ■Step1:
■Step1: それでは、前述のチェック結果を踏まえたうえで、それぞれの方にオススメなシャンプーをご紹介していきます。
それでは、前述のチェック結果を踏まえたうえで、それぞれの方にオススメなシャンプーをご紹介していきます。 「コーヒーを飲むと高血圧症になるよ」といった噂を聞いたことはありませんか?確かに以前まで、コーヒーと高血圧症には密接な関係性があると考えられていました。しかし、近年の研究によると、こうした症状が起こる可能性は低く、むしろ血圧を下げてくれる場合がある、ということが分かってきています。
「コーヒーを飲むと高血圧症になるよ」といった噂を聞いたことはありませんか?確かに以前まで、コーヒーと高血圧症には密接な関係性があると考えられていました。しかし、近年の研究によると、こうした症状が起こる可能性は低く、むしろ血圧を下げてくれる場合がある、ということが分かってきています。 では果たして、本当にコーヒーを飲み過ぎると高血圧になるのでしょうか。実は、このことについて調査した研究がアメリカで行われています。
では果たして、本当にコーヒーを飲み過ぎると高血圧になるのでしょうか。実は、このことについて調査した研究がアメリカで行われています。 前項の結果を見ると、「コーヒーは高血圧症の予防につながるから、どんどん飲むべき」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それには少し注意が必要です。
前項の結果を見ると、「コーヒーは高血圧症の予防につながるから、どんどん飲むべき」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それには少し注意が必要です。