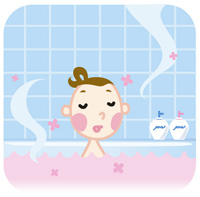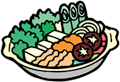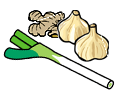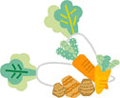|
|
|
| |
○糖尿病になる人が増え続けています。 |
| |
日本人の多くは体質的に糖尿病になりやすい遺伝子をもっていますが、この半世紀余りの間に食生活が急速に豊かになりすぎたことなどが皮肉にも、糖尿病患者数を20倍にも増やす事態をまねきました。
2007年に厚生労働省が発表した糖尿病実態調査の結果によると、糖尿病予備軍を含めて、全国で「糖尿病が強く疑われる」あるいは「糖尿病の可能性を否定できない」人が、2210万人もいるのです。5年前の調査に比べて600万人も増えています。
| 血糖値が少々高くても、自覚症状はまったくありません。しかし、血糖値が高い状態が続くと、さまざまな合併症をまねきます。成人の失明の原因の第1位、人工透析を受けなければならなくなる原因の第1位はいずれも糖尿病です。
血糖値が高めと指摘されたら、生活習慣の見直しを始めましょう。糖尿病の誘因は、肥満、食生活の偏り、運動不足などの生活習慣と深く関わります。したがって、糖尿病は一人ひとりの生活習慣の見直しと改善によって予防し、進行を遅らせることが可能になります。 |
 |
|
| |
|
| |
日本人は糖尿病になりやすい!?
日本人は2型糖尿病になりやすいと言われています。これは、日本人のインスリン(血液中の糖を細胞に取り込み、血糖値を下げる働き)分泌能力が、欧米人に比べ低いからです。欧米人の中には高カロリー、高脂肪の食生活をしている為に、日本では考えられないくらいの肥満体をした人を見かけることがありますが、欧米人のインスリン分泌能力はその高カロリーの食生活に対応でき、過剰に摂取した栄養は脂肪として体につき、血中に糖として残る事はないそうです。ところが日本人はインスリン分泌能力が欧米人よりも低いために、過剰に取った栄養が糖として血中に残ってしまいます。つまり、私たち日本人は欧米人よりも太りにくいかわりに、糖尿病になり易いのです。
もう一つの理由としては、飢餓に強い遺伝子的な要因を持っている為とされています。栄養状態が悪い状態が長く続いた時代に、飢餓に強い遺伝子が残り、子孫に伝わったと考えられていますが、現在では、この節約遺伝子が裏目にでてしまい、高カロリー、高脂肪の食事に対応できず、肥満や糖尿病に陥ってしまうのです。
|
| |
|
| |
糖尿病を予防する食事 |
| |
○野菜はたっぷりとろう |
| |
野菜に含まれる食物繊維は、肥満を防ぐ働きをします。野菜は1日に350g以上とり、このうち緑黄色野菜を120g以上とるようにしましょう。 |
| |
|
| |
○食事は決まった時間に、時間をかけて食べよう |
| |
 |
朝食を抜いたり、食事時間が不規則だったり、寝る前3時間の間に食べるのはよくありません。ゆっくりよくかんで、一家団らん、会話を楽しみながら、時間をかけて食べましょう。 |
|
| |
|
| |
○甘いものや脂っぽいものは食べ過ぎない |
| |
甘いものや脂っぽいものは太りやすい食品です。食べ過ぎに気をつけましょう。 |
| |
|
| |
○ひとり分ずつ、取り分けて食べよう |
| |
大勢で大皿から食べると、どのくらい食べたかわかりづらいため、たくさん食べてしまいがちです。 |
| |
|
| |
○薄味にしよう |
| |
濃い味のおかずはごはんをたくさん食べてしまいがちです。素材の味をいかした薄味料理を。 |
| |
|
| |
○ながら食いはやめよう |
| |
テレビを見ながら、新聞を読みながらといったながら食いも、食べた量がわかりづらいもの。またよく味わえないため、満足感もありません。 |
| |
|
| |
○多いときは残そう |
| |
多いと感じたら、無理せずに残しましょう。 |
| |
|
| |
○お茶碗は小ぶりのものを |
| |
お茶碗を小さくすると、1膳の量が少なくなるため、食べ過ぎを防げます。 |
| |
|
| |
○調味料はかけずにつける |
| |
マヨネーズやドレッシングは、油が多く、太りやすい食品。お醤油などの塩分は、高血圧の原因になり、糖尿病を悪化させます。直接料理にかけず、小皿にとってつけましょう。 |
| |
|
| |
○食品のエネルギーを知ろう |
| |
毎日食べるものがどのくらいのエネルギーなのかを知り、食品を選ぶときや食べるときの参考にしましょう。
|