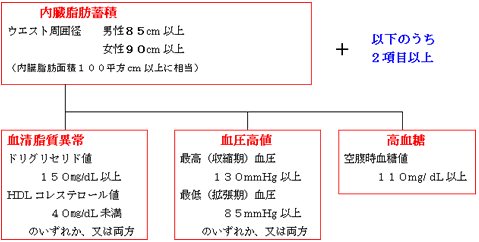|
食物アレルギーと診断されても、一般的には、小学校に入るまでにはほとんどの子が食物制限を必要としなくなります。特に食物アレルギーによるアトピー性皮膚炎は3歳以降は急速に減少するといわれています。
実際、卵アレルギーでも3歳を過ぎると食べ過ぎなければ、症状がでない子どもが多いとも聞いています。
しかし、いつかは治るのだからといって、原因食物を食べ続けていると、なかなか症状が良くならないのも真実です。
食物除去を行う場合は、
主治医の判断に従って必要最低限の制限を必要期間のみ行うのが原則です。決してお母さんの自己判断で行わないで下さい。
検査と食物日誌から食物アレルギーと診断されたら、ある一定期間は食物除去を行います。
その間、代替食物について医師から十分な説明をうけ、食物日誌をつけながら栄養バランスに気をくばり、食物除去を続けることが大切です。
特に、乳児では市販のベビーフードは控え、食物内容がわかる手づくり離乳食にし、必要に応じて新たな食材を追加しながら食物除去を続けます。
幼児の場合は、食べ物を制限することによる精神的ストレスを念頭において食物制限をしなければなりません。
食べ物を制限することによって、一時的に症状が良くなっても、食べられないストレスが強くなると、さらに症状が悪化してしまうことがあります。
食べることによって多少症状が悪くなっても、得られる満足感が勝るなら多少は食べてもよいなど、ケース・バイ・ケースの対応を主治医とよく相談しましょう。
★ 食物除去の注意点
食物除去療法によって症状がどんなに改善しても、心身の発育障害があっては何の意味もありません。 食物アレルギーで食物除去をする場合も厳しい食物制限は行なわず、必要最低限の食物制限をするのが最近の除去食療法の考えです。
除去食療法のポイント
| ① |
お母さんが一人で悩まない
医師と二人三脚で除去食内容を考え、必要以上の制限をしない。 |
| ② |
代替タンパクあっての除去食療法
代替食品を使って、成長、栄養障害を起さないようにする。 |
| ③ |
スキンケア、環境整備をきちんと行う
たとえ食物除去中でも、スキンケアと環境整備が重要。 |
| ④ |
重症の場合は完全除去療法を行う
アナフィラキーショックを起こしたことのある食品に関しては、徹底的な除去を行う。 |
| ⑤ |
定期的に発育、発達をチェックする
特に、乳幼児期の成長障害は大人になっても、その障害が残ることがある乳児では1ヵ月ごとに身長、体重を測定し、母子健康手帳についている発育に記入して発育の遅れがないように気をつける。幼児期では急速な変化はないため3ヵ月毎にチェック。体重の増加不良があった場合は食物除去をゆるめる必要がある。特に、身長の伸びが悪い時は要注意。身長の増加不良が認められた場合は即座に除去食療法を中止。 |
| ⑥ |
勝手に除去食を始めたり、中止しない
除去食療法は食物アレルギーの療法の一つなので、自己判断は禁物。 |
★食物アレルギーと給食について
食物制限のために皆と同じ給食が食べられないということは、子どもにとって大きな心理的負担になります。
食物制限のある場合は、食物アレルギーについて、園や学校側の理解と協力が不可欠です。同級生には担任から理解と協力が得られるよう説明してもらいます。
除去給食を行う場合は、
「人には色々な悩みや苦手なことがあります。○△さんは皆と同じ給食が食べたいのだけれど、お医者さんから食べてはいけないといわれている食べ物があります。本当は全部食べたくても少ししか食べられないことをわかってあげましょう。」
除去給食が不可能な場合は弁当持参となりますが、その場合は
「しばらくの間、お弁当で頑張ると、きっと皆と同じ給食が食べられるようになるので応援しましょう。」などと学校の先生に説明していただくとよいでしょう。
お弁当の場合は、あらかじめ給食の献立表をみて、給食と似た内容の除去食弁当を持たせる気配りをすることも大切です。
しかし、食物アレルギーは5~6歳になるとかなり症状が軽くなり、多少なら食べても症状がでないこともあります。
多くは、牛乳だけが飲めない場合や、特定の食物だけを食べなければよい場合がほとんどです。
残す必要があることを前もって皆に理解しておいてもらえば、給食を食べることができます。
しかし、そばアレルギーの子は命に関わることがあるので、そば給食の日には弁当を持参しましょう。
|


 薄毛とは、髪が生えかわるたびに細くなり、頭髪にコシやハリがなくなって全体や一部的にボリュームがなくなってくる状態のことで、頭髪の量のことを指す言葉ではありません。つまり、髪の生える密度自体は変わらなくても、頭髪が細くなることで量が減ったように見えることも多いのです。
薄毛とは、髪が生えかわるたびに細くなり、頭髪にコシやハリがなくなって全体や一部的にボリュームがなくなってくる状態のことで、頭髪の量のことを指す言葉ではありません。つまり、髪の生える密度自体は変わらなくても、頭髪が細くなることで量が減ったように見えることも多いのです。
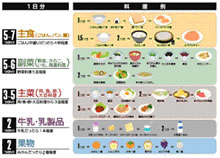
 PTSDとはPost-traumatic Stress Disorderの略称で、戦争や自然災害、事故、家庭内暴力や性的虐待など、自分自身や身近な人の生命や身体に脅威となる外傷的な出来事を経験した後に長く続く心身の病的反応を指します。日本では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件に関連して大きく取り上げられ、注目されるようになりました。
PTSDとはPost-traumatic Stress Disorderの略称で、戦争や自然災害、事故、家庭内暴力や性的虐待など、自分自身や身近な人の生命や身体に脅威となる外傷的な出来事を経験した後に長く続く心身の病的反応を指します。日本では阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件に関連して大きく取り上げられ、注目されるようになりました。 障害のある子どもの摂食機能を改善するためには、健常な子どもの発達過程との違いをよく理解したうえで、発達を促すような食物形態や介助方法を実践していくことが大切です。専門の医師・歯科医師による摂食・嚥下機能の診断を受け、専門家による指導のもとで、個々に合った食物形態や訓練の方針を決めるのがよいでしょう。適切な食物形態と食事介助が行われると、障害のある子どもの発達を促すことができます。
障害のある子どもの摂食機能を改善するためには、健常な子どもの発達過程との違いをよく理解したうえで、発達を促すような食物形態や介助方法を実践していくことが大切です。専門の医師・歯科医師による摂食・嚥下機能の診断を受け、専門家による指導のもとで、個々に合った食物形態や訓練の方針を決めるのがよいでしょう。適切な食物形態と食事介助が行われると、障害のある子どもの発達を促すことができます。
 「骨粗しょう症」とは、骨を構成するカルシウム不足が原因で骨の密度が減り、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。現在日本では約5,000万人もの患者がいると言われ、高齢の女性に特に多い病気でもあります。
「骨粗しょう症」とは、骨を構成するカルシウム不足が原因で骨の密度が減り、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。現在日本では約5,000万人もの患者がいると言われ、高齢の女性に特に多い病気でもあります。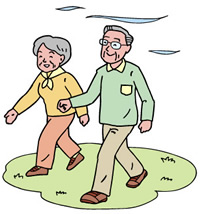 ○生活編
○生活編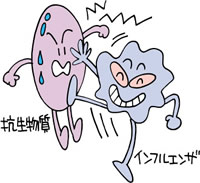 インフルエンザと風邪は、そもそも原因となるウィルスの種類が違います。インフルエンザは高熱が出るだけでなく、筋肉や関節の痛みなど全身に出る症状が強く、気管支炎や肺炎を併発しやすいなどの特徴があり、抵抗力のない乳幼児や高齢者にとっては生命にかかわる危険も。また、突然大流行することもある、恐ろしい病気です。
インフルエンザと風邪は、そもそも原因となるウィルスの種類が違います。インフルエンザは高熱が出るだけでなく、筋肉や関節の痛みなど全身に出る症状が強く、気管支炎や肺炎を併発しやすいなどの特徴があり、抵抗力のない乳幼児や高齢者にとっては生命にかかわる危険も。また、突然大流行することもある、恐ろしい病気です。
 「風が吹いただけで痛い」ほど足の関節が痛む病気、として知られる痛風。ある日突然足の親指の付け根が腫れ、立ち上がれないほどの痛みが発作的に起こります。この発作はたいていの場合1週間ほどで治まりますが、半年から1年の期間を経てまた同じような痛みが起こり、繰り返すうちに足首や膝の関節まで広がってくるように。怖いのは、この痛みと併行して内臓が侵されていくこと。間接の強烈な痛みだけでなく、腎臓などの内臓にも障害が起こってしまう病気と覚えておきましょう。
「風が吹いただけで痛い」ほど足の関節が痛む病気、として知られる痛風。ある日突然足の親指の付け根が腫れ、立ち上がれないほどの痛みが発作的に起こります。この発作はたいていの場合1週間ほどで治まりますが、半年から1年の期間を経てまた同じような痛みが起こり、繰り返すうちに足首や膝の関節まで広がってくるように。怖いのは、この痛みと併行して内臓が侵されていくこと。間接の強烈な痛みだけでなく、腎臓などの内臓にも障害が起こってしまう病気と覚えておきましょう。 痛風を防ぐには、尿酸値を下げることが大切。それには尿酸のもとになるプリン体という物質を減らすのが第一です。
痛風を防ぐには、尿酸値を下げることが大切。それには尿酸のもとになるプリン体という物質を減らすのが第一です。