|
平成 15 年の国民栄養調査の結果では、食物繊維源として重要な野菜の摂取量は、全国の平均で
277.5 gでした。
年齢が増えると増加傾向にあり、最も多い 60 歳代では、平均で 339 gでした。しかし、若年の摂取量が少なく 20 歳代では 249 gでした。
このような結果が出た原因を考えてみると、重要な供給源だった穀物(米)の摂取量も減ってきていますし、加えて精製された穀物は、食物繊維をあまり含んでいないのです。
若い人は、年々野菜を食べなくなってきているようなので、野菜の摂取量の多少が食物繊維量に関係しているようです。
食物繊維の総量は、 20 歳代では 12.4 g 60歳代では、 17.5 gでした。
特に 20 歳代の女性は、 12 gと少ない結果でした。ちなみに 1951 年の結果では 23 g、 1960 年には 20 g摂取されていました。現在の食事摂取基準では 20 g程度の食物繊維を摂ることを進めています。ちょうど 1960 年当時と同じく野菜や穀物を食べるように勧めていることですね。
このように、 50 年の年月を経て8gも少なくなった食生活ですが、さてどうすれば、食物繊維を十分に摂ることができるでしょうか。 1960 年代に戻るのは、至難の業でしょうか。生活習慣病の予防のためにも、米や麦を主食に芋や野菜類をたくさん摂るようにお勧めいたします。そして 規則正しい食事が健康への早道だと思います。
茨城県は、日本でも有数の農業が盛んな地域です。新鮮な地場産の野菜をたくさん召し上がって食物繊維の不足を解消しましょう。表のように食物繊維量の多い食品を上げてみました。参考にしてください。
|



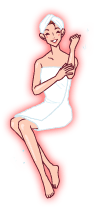 ・摩擦の多いナイロンタオルは使わない。
・摩擦の多いナイロンタオルは使わない。 ・化粧品にも気を配る
・化粧品にも気を配る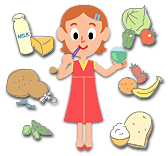 大方の人は1日3食の食事をほぼ規則正しく摂り、日々繰り返される食事が健康とかかわりを持っていることを、おぼろげながら理解しつつ生活を続けていると思います。健康を損なってはじめて毎日の食事がいかに大切なものかを知るという方もいるはずです。
大方の人は1日3食の食事をほぼ規則正しく摂り、日々繰り返される食事が健康とかかわりを持っていることを、おぼろげながら理解しつつ生活を続けていると思います。健康を損なってはじめて毎日の食事がいかに大切なものかを知るという方もいるはずです。
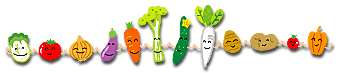

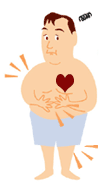

 ダイエットを始める前に、まずは自己分析。自分の肥満度や体脂肪を計り、自分に必要なダイエットを知ることからはじめましょう。
ダイエットを始める前に、まずは自己分析。自分の肥満度や体脂肪を計り、自分に必要なダイエットを知ることからはじめましょう。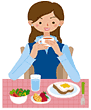 食べることは、とっても楽しくかつうれしいものです。今夜が大好きな献立とわかったらその時から、お腹がグウ、グウ、心はわくわくするものです。
食べることは、とっても楽しくかつうれしいものです。今夜が大好きな献立とわかったらその時から、お腹がグウ、グウ、心はわくわくするものです。



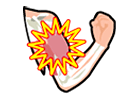
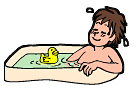
 『サンマ』がおいしい季節になりました。今年は豊漁でサイズも大ぶりです。よく脂ののった胴が丸々と太ったサンマが手頃な値段で手に入ります。
『サンマ』がおいしい季節になりました。今年は豊漁でサイズも大ぶりです。よく脂ののった胴が丸々と太ったサンマが手頃な値段で手に入ります。
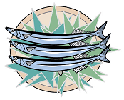


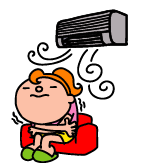 夏風邪かな?と思ったり、だるさを感じたときは無理せず身体を休めましょう。そして
夏風邪かな?と思ったり、だるさを感じたときは無理せず身体を休めましょう。そして
 そんなことはありません。健康が気になる人や健康診断などを受けて生活習慣病のことが気になっている人が保健の効果を期待して食べる食品ですので、誰でも利用できます。
そんなことはありません。健康が気になる人や健康診断などを受けて生活習慣病のことが気になっている人が保健の効果を期待して食べる食品ですので、誰でも利用できます。

 便秘の予防・解消(整腸作用)があります。
便秘の予防・解消(整腸作用)があります。
